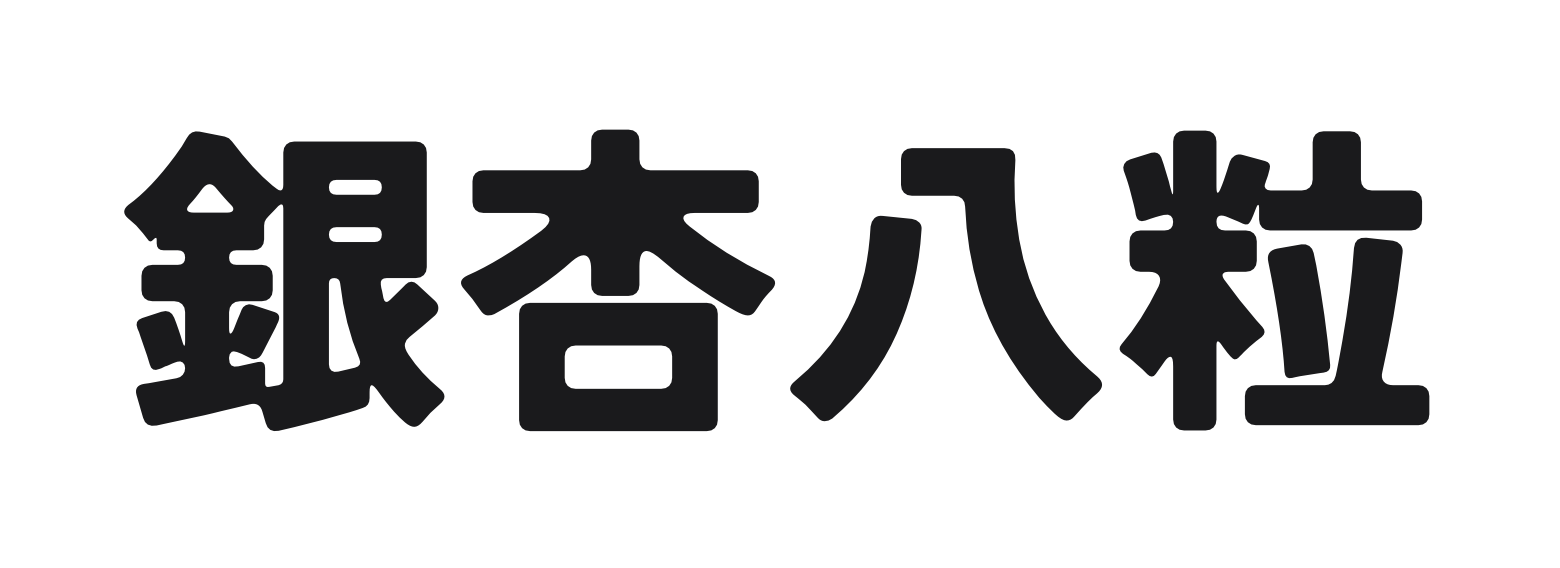夕暮れ時に人々が家路を急ぐというのは、古今東西変わらないらしい。残照が西の空を黄金色に染め上げるなか、大勢に逆行するように歩く魔法使いが二人いた。
「レノの影、いつ見ても大きいよね」とフィガロが眼の前にある大きな影を見ながらぼやく。その半歩後を歩くレノックスは、「言うほど身長は変わらないでしょう」と返事をする。夕焼け特有の暖かな光が、二人の影を前に長く伸ばしていた。
そのとき、ぴょんとレノックスの鞄から羊が一匹飛び出した。羊飼いの影の中をまっすぐ走ると、そのふちでこちらを向いてメエと鳴く。まるでその大きさを示しているかのようだ。賢いなあと無意識に呟いたフィガロはそのまま隣を見て、何もしない羊飼いを覗き込む。
「意外だな。すぐに回収しに行くのかと思った」
「あいつは好奇心旺盛なやつです。でもそこまで危険なことはしないので、ある程度は好きなようにさせてます」
鞄から頭をいつも出しているでしょうと彼は言う。そういう意味だったかと納得しかけたところで、羊の頭上は見知らぬ影に覆われた。
少女が羊を見つめていた。まるで運命に惹かれたかのように小さな羊から視線が外れることはなく、羊もまたつぶらで大きい瞳をきょとんと少女に向ける。そして少女はしゃがみ込み、ふわふわの毛を指先でゆっくりと撫でた。恐れはなく、けれど大切なものに触れるかのような慎重さが滲む手付きだった。
女の子は羊の愛らしさに恋に落ちたのだろう。夕明りのなか誰もがわかるように演出された舞台の一幕のような光景を目にして、隣の同行者は歩幅を大きくしてそこに向かう。彼は羊飼いとしてその運命の赤い糸をほどかねばならないのだ。
面白い場面にあったな、とフィガロはその場で立ち止まる。自分が行ったら話を複雑にするし、彼女を引き離すのに手こずったらそのとき向かえばいい。言い訳を考えながら、フィガロは観衆の一人としてその場面を見守ることにした。
はてさて、彼はどのように解決するのか、そして少女は泣かないですむのか気になるところだ。レノックスは無理に笑うと怖いからなあと考えるその口元には、穏やかな笑みが浮かんでいた。
残った今日を踊り明かして
レノ、散歩に行こう。
いつの日かレノックスが散歩に誘って以来、フィガロからもそう言って散歩に誘うことがいくらかあった。初めはそれぞれ相手の運動不足を心配してだったり、気分がいいからだったりと理由があったものだが、回数を重ねるうちに理由の確認もなくなった。言い訳があろうがなかろうが、目的もなく歩くのに苦にならない二人だったとお互いに理解したのだ。
ただし、二人が出かける時間帯はもっぱら夕方から夜、遅くても夜明けまでなのは初めから変わらなかった。昼間は忙しいし、朝はときどきミチルに起こされたいフィガロが――直接本人がこういったわけではないがレノックスはこう考えている――難色を示したためだ。
二人の散歩は適当に始まって適当に過ごして適当に終わる。今日の散歩もまた、そういう始まり方だった。
魔法舎で賢者がパーティー料理を作ってみたいと呟き、大鍋をわざわざ買って十数時間かけて作られたオードブルは案の定、全員が食べたがったので、争奪戦になった。あわや物理的な魔法舎崩壊の危機かと思われたが、今日の分の人選はくじで決めることと後日全員分を作ることを賢者が即座に宣言したので、争奪戦は一応水面下で終わった。材料の量が読めずに中途半端な量を作ってしまったが、今度からは食材をたくさん用意して作りますと言った賢者は少し嬉しそうだった。
そういう訳で引いた南の面々でのくじの結果は、フィガロとレノックスははずれでミチルとルチルは当たり。ついでに言えば、ミスラも当たっていた。
ちなみに魔法使いの間で行われるくじ引きは、各々が本気を出せば運要素はあってないようなものだ。魔法を使えばいくらでも改ざんできる。恐らく当たりにする魔法を使えば北の誰かしらに文句は言われただろうが、わざとはずれにする者は咎めても意味がないとして、黙殺されたようだった。
当たった魔法使いを眺めると年少の割合が高いのは、たぶんきっとそういうことだ。
くじに外れたメンバーは各々外食にすることに決まった。申し訳なさそうな賢者の好意で増額された小遣いにしては太っ腹な額の銅貨を手に、フィガロはレノックスに一緒に食べないかと誘った。特に断る理由もなかったので、レノックスは頷いたのだった。
「せっかくだから、あの橋までまた行かない?」提案したのはフィガロだった。彼が指すあの橋とは、前に行ったことのある、中央の国にあるとはいえ往復でそこそこの距離がある橋だ。具体的に言えば、夕方から行きはじめて帰るころには日付を跨ぐかどうかというところである。確かにこんな機会でもないと気軽に行こうと言いにくい。初回は強行したけれど。
ということで、二人は橋に向かって散歩をすることになった。散歩と言うにはずいぶんと壮大な散歩である。もちろん食事は買い食いで、歩きながら食べることになった。
中央の国の大通りに一歩足を繰り出すと、ふわりと夕餉のいい匂いが二人の鼻腔をくすぐった。ちょうど一日の仕事を終えた職人や役人が、そこらの店で夕食を買って帰る頃合いであり、酒盛りでもしている店もいくつかあるはずだった。道に面した店はどこでも賑やかで、その中には持ち帰りに適した串焼きや揚げ物を売っている店もあった。
こういう毎日食べるものを売る店に関して、人々の向ける目は驚くほど厳しい。この通りに店を構えていられるという事実だけで、味の太鼓判は押されていると言ってもよかった。
別々に買おうと一旦解散して、十五分後にまた同じ場所に二人は戻った。レノックスは串焼きをいくつか、フィガロはオズ饅頭のような饅頭を買ってきた。饅頭を持つ手の反対にちゃっかり麦酒もあるのを見て、レノックスはため息をつく。
「中央では合法だろう?」
視線に気がついた酔っ払い予備軍はそう言い放った。ちなみに規則がかっちりしている東の国で路上飲酒をしようものなら、問答無用で役人に連れて行かれる。咎める理由を先んじて封じられたレノックスは、結局半端な注意を口にするしかできなかった。
「……橋から落ちないでくださいね」
「落ちても大丈夫だよ」
箒で飛ぶし。そう呟きながらフィガロは酒をすすった。
串焼きをひとくち食べるごとに、絶妙な火加減で炙られた皮とじゅわっと旨味が溢れる肉の食感に、レノックスは美味いなといちいち思わざるを得ない。串焼き屋の店主はわりと雑な手付きで串を扱っていたように見えたが、逆に熟練の巧みであったということか。わかってはいたが料理の世界は奥が深いらしいということに思いを馳せつつ、炭火の香ばしさがしっかりとついた串焼きを噛みしめる。ふつうに美味い。
「食べますか?おいしいですよ」
視線を感じて、レノックスは自然にそう言葉が出た。珍しいことだ。フィガロとレノックスは端的に言えば食の嗜好がかなり違う。そもそも自分の一番好きなものが相手の嫌いな食べ物である同士、おいしいと思った料理を勧めることはあまりなかった。少なくとも主菜は。悲劇を防ぐためだ。
それでも今日言ってみたのは、あまりに串焼きが美味かったことと、フィガロがさりげなく横目でちらりと串焼きを見ていたためだ。香ばしく焦げたような芳香は食欲をそそるのは言うまでもないし、夕焼けの橙色の光が肉の見た目を数段よくしているのも多分理由の一つだろう。
食事をシェアすることに関して、不思議な感覚がしたのはおそらく相手もそうだったらしい。わずかに間があいてから、「レノって賢者様の肉まん食べられたっけ?」と聞いてきた。
「ああ、はい。美味しかったですね」
「じゃあ多分これも大丈夫だと思うよ。交換しよう」
酒のカップを魔法で浮かせてから、フィガロは肉まんに似ているらしい饅頭を割って、三分の一ほどをこちらに寄越した。等価交換となると、串焼き一本というところだろう。レノックスは素直にまるまる一本手渡した。
饅頭の断面には、挽肉がこれでもかと詰め込まれていて、日暮れの色に照り映えた脂が優しい色に染まっていた。ほかほかと立つ湯気でさえ美味しそうなそれに一息にかぶりつけば、予想通りの味わいが口いっぱいに広がる。美味い。
「おいしいかちょっと心配だったけど、安心したよ。……レノって顔に出るときと出ないときがあるよね」
フィガロは鶏肉の皮をパリパリと齧って、美味いな、と呟きながらそんなことを口にした。それほどわかりやすくおいしそうな顔をしていたんだろうか。自分ではわからない。
もう一口でフィガロの饅頭を食べきって、分け合うのも悪くないな、とレノックスは思った。
二人の好き嫌いはかけ離れてはいるけれど、たまになら聞いてみてもいいかもしれない。
食べ終わってからしばらくして、話は冒頭に戻る。
羊と少女の運命の赤い糸をあっさり解いた羊飼いは、偉大な魔法使いのもとに帰るなり文句を言われた。
「面白くない」
「はあ」
そんなことを言われてもレノックスははあ、としか言いようがない。対してフィガロの言葉に抗議するように鞄から顔を出した羊のひと鳴きが、メエとその場に響いた。
レノックスはフィガロの予想に反して、何も手こずることなく羊を無事回収することに成功した。聞けば、魔法使いの家に自分と羊は顔を出すことを教えたらしい。魔法使いだからいつもいることの約束はできないが、そこでまた会うことはできるだろうと。ダメ押しで今日はもう帰らなければいけない時間ではないかと促せば、少女は素直に帰ったそうだ。
大男の彼自身を怖がって泣くか、羊と引き離されることに泣くか予想していたフィガロにとってはあまり面白くはなかったが、誠実な彼らしい結末ではあった。見事な手腕だったと素直に称賛してもいい。
「……おお、レノックス。偉大な男の名よ……」
「そのひやかし気に入っているんですか?」
「せっかく作ったからね」
わざとらしい節回しの詩をぱちんとウインクを決めて言ってやれば、どうでもいいことを覚えているな、という顔を露骨にされた。真実どうでもいいことだったので、フィガロはとくに咎めなかった。
ふと、彼が顔を上げながら思い出したかのように呟いた。
「魔法使いだったみたいです」
「女の子が?」
はい、と返事をしながらレノックスが眼鏡の奥の目を細めた。視線の先には、少女が帰っていった石畳の道がある。
なるほど魔法使いならば、あの恋に落ちる速さも頷ける。駄々をこねずにあっさりと次の機会を狙っているところも見るに、きっと将来彼女は恋多き魔女になるだろう。そうなれば面白みも出てくるものだ。へえ、とフィガロはからかった。
「じゃああの子はこれからレノたちに会いに魔法使いの家に来るのか。もしかしたらきみの弟子になるかもしれないね」
「完全に羊目的でしょう。それに弟子だとか、どう転んでもそんなことにはなりませんよ」
やけにはっきりと言うものだ。頬にあたる夕暮れ時の涼やかな風が、その言葉に少しばかりひっかかるものを感じさせる。それがなんだろうと軽く考えて、
「あれ、ずっと弟子は取らない主義だっけ?」
そう訊くことにした。
齢を重ねた魔法使いはふつう――多分人もそうではないかと考えているが――自分がやってきたことを継承したい、端的に言えば弟子を取りたいと思うものだ。まさかそこを突かれるとは思っていなかったであろう彼は、わずかに戸惑っているように見えた。
「主義というほどのものでは」
「今の五倍生きたとしても取らない?」
「俺が二千年生きられるとは思いませんが……。そうですね、おそらく」
戸惑いを覗かせながらもきっぱりとした物言いに、フィガロはわずかに驚いた。
レノックスは何もやってこなかったというわけではない。それこそ彼が彷徨っていただけだと自称する四百年の旅路だって、得た何かはあるはずだった。言葉や本には書き表せない、彼だけの経験が存在するはずだった。弟子を取らないというなら消えていくだろうそれらを、彼はどうするというのか。
「どうして?」
訊いた瞬間は純粋な問いかけだった。
が、もしかして、フィガロとファウストの師弟関係を見て弟子を取ることはやめようと思っているのかもしれないと思い至る。どの口が言うんだという話ではあるが、そうだったとしたなら、こんなことを訊くのはレノックスには申し訳が立たないことに今更気付いた。
しかし、幸か不幸か予想は外れることになる。
レノックスにかかる影がしだいに濃くなっていく。夕陽が落ちたあとの真っ赤な名残さえも消えゆく黄昏時と夜の狭間、彼の顔が見えにくくなる。唇の動きさえ読めないなか、声だけが確かにフィガロに届く。
「俺がこのさき、遺したいものはないので」
いまが黄昏時でよかった、とフィガロは心から思った。夕闇で彼の顔が見えないということは、こちらの顔も見ることができないということだから。
レノックスを見る自分の目はきっと、信じられないものを見るかのような目をしている。
とっぷりと日が沈んで、街灯の明かりがほのかに足元を照らす時間になった。ある場所を境に仕事熱心な火付け役が担当しているようで、完全に日が暮れる前から橋に向かう道のすべてのガス灯はきちんと明かりがついていた。
南の国ではめったにないその光景を横目に、二人は黙って歩いていく。
弟子を取るか否かの話のあとにも話題を変えるかのようにいくつかの雑談を挟んだものだが、だんだんフィガロの歯切れが悪くなって、ついには考え事がしたいから黙っててほしいと申し出るまでになった。無言が苦にならない程度に気心の知れた仲だからこそ散歩をしている節があるのでレノックスはそのまま了解して黙っているが、明らかに自分の回答が腑に落ちてない彼の様子に思うところはある。
今まで微妙にニュアンスが噛み合ってないな、と思おうがそのまま会話を続けることはしばしばあった。レノックスが自覚しているところでも思い当たる会話はいくつかあったので、知らずに食い違っている、あるいはフィガロだけが噛み合っていないと感じて受け流している話はこれ以上にあるだろう。
それでもわざわざ会話を止めるとは、よほど看過できない何かがあるということだ。口が達者な彼ならばすぐさま反論は出そうなものを、黙ったままなのは理解の範疇を超えているからか。それともレノックスの考えを尊重したいのか。それはわからない。
鞄の中、一定のリズムで揺られ続けた羊はとうとう眠ってしまったようだ。あたりの街は一時間ほど前の賑やかさが嘘だったかのように、まばらな足音しか響かなくなっていた。考えてみればこれは当然のことで、とっくのとうにこの道は大通りからは外れている。それでも営業中の店の中は騒がしく、時折壁の向こうでどっと歓声がわく。それが余計に石畳に吸い込まれる足音を静かにさせる。
この環境がいくぶん、レノックスの思考を澄み切って透明なものにした。
「自分の死を前にして、継承したいものも継承させたいものもない」。かつてファウストに語ったことだ。このことは四百年間の旅路で悟っていた。何を残さずに死のうとも、誰かに覚えてもらえずとも、ファウストの幸福を一目見られればそれでよかった。
思えばそれから、フィガロからはたくさんのものを受け取ってきた。四百年の旅の疲れを癒す雄大な風景。穏やかな日々を思い出させてくれた職業。目を合わせればぴたりと息の合う相方と、人類のよき友である羊との出会いのきっかけ。与えられたこれらは、彼を尊敬する理由の一角を成している。もちろん与えられただけでなく、それを守る手助けも工夫もたくさんしてきた。編み出したものもあった。気がついたこともあった。
それでも想いは、変わらなかった。
積み重ねた日々を未来に繋げたいと思わないとは、繋げることができないからと諦めた先にあるただの強がりではないのか? この世界のどこにも繋がっていないような矛盾と虚しさに蓋をして、ただそれを見つめていないがゆえに張っている虚勢なのではないか?
――違うのだ。これはそんな表面上の話ではない。
こころの奥底で明瞭に理解しているものほど、言葉で表現することは難しい。
触れた瞬間に融ける雪の結晶みたいなものだ。どんなに丁寧に扱おうとも、すべてが精細を欠いてしまうことは誰よりもレノックス自身が知っていた。
レノックスが理解していることを、フィガロも理解していると信じたかった。そうであるなら、この想いをぐちゃぐちゃにしないで済む。
だが、もしも。
フィガロがそれを無責任だとかなんだとか、なんとか言ってその真意を訊いてくるのならば。そういうことではないと、言葉を尽くす覚悟は出来ていた。
一定のリズムを刻み続ける彼の足音の半歩あとを、レノックスは変わらずに歩き続けた。
現れては消えゆく街灯の下を、後ろから追いかけてくるリズムに合わせてフィガロは歩く。レノックスの歩調は心地よい。さすが歩き続ける羊飼いだというべきか、速すぎることも遅すぎることもなく疲れないのだ。
歩くペースを委ねながら、フィガロはアルコールを摂取したにしては冴えた頭で思考を空転させていく。
そういえば彼は、不思議な男だった。わかりやすいところで言えばふとした瞬間ふつうに笑えるくせに、笑顔は苦手だとか。わかりにくいところで言えば無欲でいるようでいて、しっかり執着しているところはあるだとか。
そんな彼が、「このさき遺したいものはない」という。それはかつて持っていた叡智すべてをファウストに残そうとした自分と、それこそが自分の天命だと思っていた自分と、真っ向から対立する考えに思えた。
いや、彼は対立させようとして言ったわけではない。それはわかっている。心の中にある事実を言っただけだろう。しかし、弟子だとかなんだとかの話の先に、もっと本質的な何かがその一言に隠されているような気がしてならなかった。
真実の愛に手が届くだろう、実直な男。かつて自分はそう思った。その確信に近い予感を抱かせるまでの理由の一端を、この一言が担っているのではないか。フィガロはそれを暴きたかった。
彼の考えは腑に落ちないけれど、噛み砕かないまま考えてみても、なるほどそれは彼らしい愚直な考えであると思う。レノックスはどこまでも今を見つめているのだ。後悔以外は。
いつも彼を単純すぎるとひやかすこともあるけれど、自分より素直で勇敢であることの裏返しであることは知っている。知っているがしかし、皮肉を込めて幸せな男であると思う日もある。
今晩はどちらだろう。やっぱり幸せな男だろうか。
繋がるものを考えず、今のことだけを考えて行動できるということは、幸せなことだと思う。自分は未来にも、過去にさえも思考が向く。ただ救いたいと願っても、頭の中は自動的に膨大な疑問で埋めつくされる。
世界はこれを、民を救えなかった悪神にしては大仰な高望みだと笑うのではないか? 結局死に際においてしか大切なことが分からなかった愚か者だと、後ろ指をさして嘲るんじゃないか? 皆のためと嘯きながらさんざん大事なものを手放してきたくせに、今さらその手を価値あるものに伸ばそうだなんて、あまりにも虫が良すぎる話だと罵るのではないか?
誰にも褒められない類の卑下は、もちろんそれだけでは止まらない。これを全て打ち返すぐらいの確固たる自尊も心の中で反論を声高に叫び出す。なにせ生まれたときから神様だったのだ。たとえ自分によってでさえも、自らを軽んじるのは許せない。
フィガロはため息を吐いた。
彼はいちいちこんなことを考えなくて済むのだ。これが幸せなことでなくて何なのだろう。
だが、幸せな男だからといって真実の愛に手が届くと感じたのかといわれると、そうではないのだ。おそらくまだあの一言の本質を突いていない。
思考は空転を続けるが、それ以上考え込む猶予はもはやなかった。とうとう橋が見えてきたのだ。
誰もいない石造りの橋の表面を、ポールライトが等間隔に照らしていた。二台分の馬車でも通れそうな傾斜がなだらかな橋に、二人分の足音だけが響く。フィガロは何かを言わなければならない。黙ってほしいと頼んだのは自分なのだから。
自分は何を問いかけて、レノックスからどんな言葉を引き出したいのか。「そんなのありえなくない?」ありえなくないことは知っている。「お前は本当に幸せな男だね」皮肉が言いたいわけではない。「きっとそれは思い違いだよ」自分でもわかるが、最低な選択肢のうちのひとつだろう。
言葉が浮かんでは消え、ちょうど橋の中央にさしかかる。くるりと振り返り、自らの白衣が翻るのを目の端でとらえた。レノックスの赤い瞳が真っ直ぐに自分を見ている。その瞬間、何かがかちりと噛み合わさり、フィガロは思考を介さず言葉を零した。
「おまえ、自分が死んだあと、永遠になれるとして。それでも永遠にならないの?」
彼の真意を暴くための問いかけでさえ、神のような物言いで内心笑えた。どうやらあやふやで曖昧でいい加減な聞き方をするのは、自分の悪癖の一つのようだった。永遠。この世に未来永劫続くことなんてないのだから、どうにだって取れることは彼もわかってくれるだろう。
オズのように長きにわたって歴史書に記述されることも永遠だし、後世に残る生活の知恵を生み出すことだって永遠だ。師弟の系譜に関わることも、誰かに名前を覚えてもらうことも、人生を本に書き残すことも。何にだって永遠に思えてくる。
未来に何かを残すことであるならば。
それでも彼は、そのまま視線を動かすことなくはっきりと答えた。
「俺のいない世界で、俺がやったことが永遠になったとしても。……なにも嬉しくありません」
――こういう考え方ができるやつの方が、真実の愛に手が届くんだろうな。今まで目にしてきた数多の物語を思い返しながら、フィガロは口の端で笑った。自分はこんなにきっぱりと言い切ることはできないだろう。
自分の生き方は、間違っていたのかもしれない。
フィガロが抽象的な聞き方をしてきたので、レノックスも自分の考えをそこまでぐちゃぐちゃにしないで済んで、ほっとする。やはり彼は聞き方が上手い。ともすれば自分でさえも言葉にしにくいものを、自覚するきっかけを与えてくれる。
自分の言葉を聞いたフィガロは、不思議な表情をしていた。わかりやすく不機嫌そうな顔ではない。呆れたような顔でもない。感情が読み取れない顔。つまり、推察は不要だということだ。
そんな彼がこんなことを言うので、レノックスは考えるより先に言葉が口をついて出た。
「俺もおまえみたいに、……生きられたらなって思うよ」
「嘘ですよね」
ほとんど脊髄反射だった。すぐに反応した理由は、いつか聞いた言葉だったから、そしてそんなことは分かりきっているから。
二千歳が四百歳を見習うはずもないのだ。
若干返答が食い気味だったせいか、フィガロはちょっと瞠目した。そして瞬きにしては長い一瞬、目を閉じて――開いたときには、レノックスにも読み取りやすい、いつものフィガロの瞳になっていた。
「ばれたか」
――嬉しそうだな。これまたいつかのように呟く彼を見て、なぜだかレノックスはそう思った。悪戯っぽく細められた目元も、わずかにシニカルな笑みを滲ませた口元も、ふわふわとした髪の揺れ方も、ばれたかというその声音でさえ変わらないというのに。
その瞬間、二人の間で緊張していた糸がふっと緩んだ。フィガロはとん、と軽やかに一歩レノックスへの距離を詰める。それだけでこれまでの奇妙な空気は塗り替えられ、まったくいつもの調子に戻っていた。
二人の考え方がまるきり違うことなんて、いまさらのことだったので。
「ねえ、レノ。こんなところまで来たんだし何かしない?」
「できること、ありますかね?」
レノックスは空を見上げた。前回来たときにはムルに笑われそうな天体観測をしたのだ。夜の闇が深く、ガス灯の明かり越しでも大きな星はいくつか見えていたため、適当な星を結んで星座を作って遊んだ。南の子どもたちがよくやる遊びだ。フィガロが作った「小さくなったレノックスの羊座」は、満場一致で素晴らしい出来栄えだった。
けれど、今晩は真夜中にさえ差し掛かっていない。星の瞬きは弱く、吹けば飛びそうなほどだ。
そう思った瞬間、ぱちんとフィガロの指を鳴らすきれいな音が辺りに響き、レノックスは視線を彼に戻した。すると突然辺りが急にまばゆく輝き、眩しさのあまり反射的に目を細める。光に目が慣れたとき、フィガロが自分へ向けて差し出した手が、視界にいの一番に飛び込んできた。
橋の上すべてのガス灯が、二人を照らすスポットライトに替わっていた。すさまじい光量はまるで舞台の上のようで、全ての方向から照らされているため足元には影すらない。気がつけば眠っている羊は鞄ごとスポットライトの外側に置かれていて、その用意周到さにレノックスは呆れながら目の前の手を取った。
「役人になんて言われるか」
「幻を使わないほど馬鹿じゃないさ」
どうやらこの劇場は、演者も観衆も真実二人だけらしい。ひとときの夢みたいな舞台だが、「二拍子。ステップは基本のやつね」なんてやたら具体的な指示が飛ぶのでもはやロマンスの欠片もない。リードを取るのは背が高いレノックスの方なのに。
ワルツにするなとの指示通りに軽くメロディを口ずさみながら、レノックスはフィガロの手を握りステップを踏み出した。追いかけるフィガロの足がぶつからないのを確認して、踊りはなめらかに滑り出す。
熟達したダンサー同士であるならば、軽い重心移動で相手が何をしたいのかわかったり、四足の動物みたいにぴたりと踊り切ったりすることができるだろう。逆に初心者であるならば、慎重かつ大胆な足取りで、相手になんとか合わせようとするだろう。
けれどこの場にいる二人は本業ではないくせに、魔法使いなので各々がリズムを崩さない程度にやりたいことを主張した。適当なタイミングで「右!」と鋭く言ったり、「それ結局左じゃないですか」と文句を言ったりしながらなんとか足を踏まないのがせいぜいだ。
それでも二人は笑っていた。それでよかった。
基本のステップを踏み続けるレノックスに合わせて、フィガロが繊細で技巧的なステップを刻むように挟んでいく。誰もが見惚れる足さばきのくせに、誰も見ていないのが可笑しくてまた笑う。
その贅沢なステップに応えたくて、フィガロの足先が宙に浮かぶ一瞬を見計らってそのままぐるりと一回転する。腕につかまった子どもたちを回すのと要領は変わらない。それに気付いたフィガロは「やるじゃないか!」とけらけら笑った。
二人の頭上にある星々は遠く、スポットライトの遥か彼方で光っている。
あまりに広大すぎて怖いくらいの夜空とは反対に、二人が踊る場所はせまく、しかし確かな明るさがあった。
天上にある何もかもを置き去りにして、それでも二人は踊り続けた。
Fin.