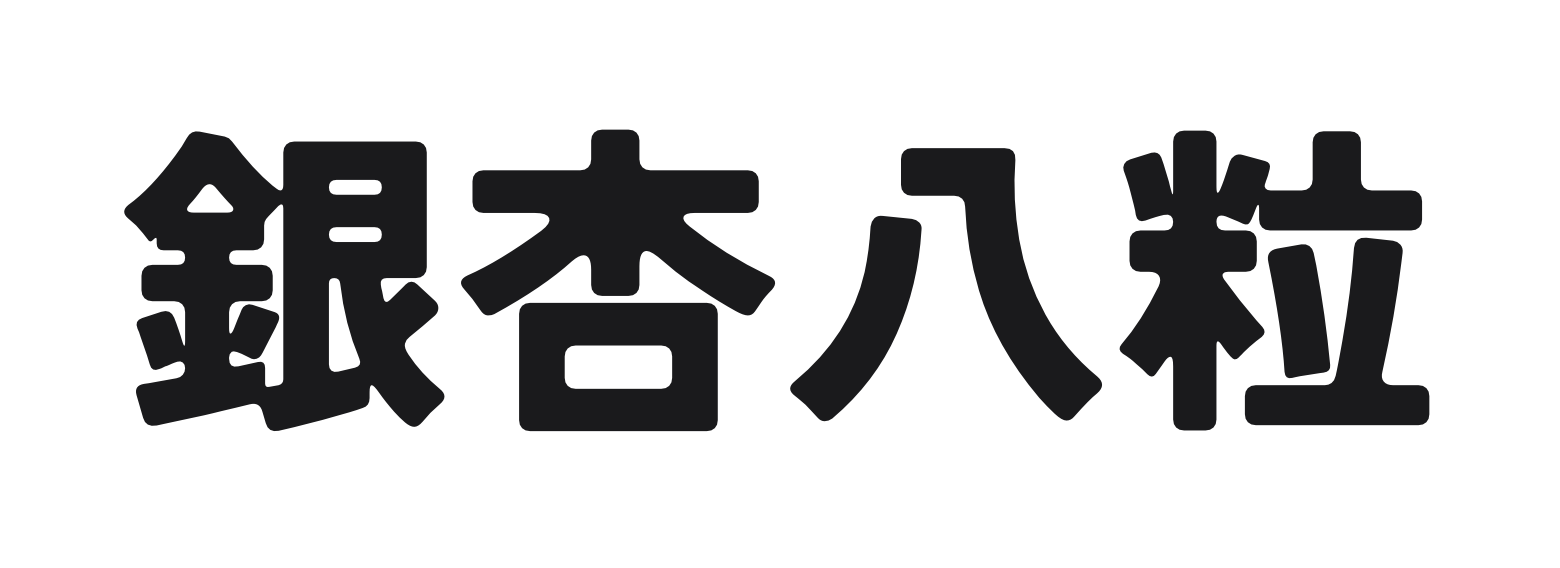かつて主人の手を離したその師匠のことを、いざというときには偉大で頼りになる魔法使いだと思い直したきっかけのいくつかを、レノックスは何年経ってもよく覚えている。そのうちの一つは月日を遡って、南の国で羊飼いの仕事を斡旋された年のことだ。
「カーテンくらい開けなよ」
その日、春風のように軽い調子でレノックスの小屋を訪れたフィガロは、部屋の中を見るや否や、そう一言呟いてぱちんと指を鳴らしてしまった。当然部屋の全てのカーテンが魔法にかけられて、勢いよく開く。薄暗かった部屋に眩しい午後の日差しが窓から差し込んできて、明るさの変化に眼鏡の奥の目を細めながら、レノックスは口を開いた。
「仕事の間はこの小屋にはいないので、別に開けなくてもいいんです」
言いながら、ソファに掛けたままだった自分の上着を取った。突然の来客に対応する準備もできていなければ、突然の来客から突然言われる生活上のアドバイスを素直に受け取る準備もできていなかった。
そもそもレノックスの小屋の中でのカーテンの役割といえば、標高が高いために若干強くなってしまう午後の日差しを遮ることにある。これをふまえれば無人だった部屋のカーテンが閉まっていたことなど咎められることではなく、むしろそうするべきだろうとも思われた。
しかし意外なことに、フィガロはきっぱりとした態度で反論した。
「そうは言ってもね。きみ、朝食はここで食べているんだろう」
「ええ、まあ」
「今カーテンが開いてないということは、暗い中で食べてる」
「まあ……」
段々と彼の言いたいことがわかってきた。
確かにこの小屋のカーテンをレノックスが開けるタイミングはごくわずかしかない。日が昇る前に起きて、仕事をし始めて、仕事が終われば日は落ちている。そんな生活リズムになると、カーテンを開ける動作すらも億劫になってしまって、何日かに一度の換気くらいしか窓は開けない生活をレノックスは送ってしまっていた。
長い旅路を歩んできた影響で、生活を送るにあたって生死に差し障りのない作業が杜撰になってしまっているのは自覚がある。カーテンの他にも、ソファの背もたれに上着は放ったままであったし、キッチンの流しにもいくつか食器が重なったままだ。
ばつが悪くなって、言葉を重ねた。言い訳じみていることに気が付いたのは、言った後のことだった。
「朝食を食べるころにカーテンを開けても、この辺りは暗いままです」
「べつに、暗いとか暗くないとかが問題じゃあないよ」
ぎい、と音を立ててフィガロは日の当たるスツールに腰掛けた。
その光景を見て、意外だ、とレノックスは思った。偉大な魔法使いは、カウチに寝そべるとまではいかなくても、正面にあるソファに座るのが自然だと思った。だがしかし、足を組みもせずに背もたれのない椅子に座る莫大な魔力を持つ男が、変な表現にはなるが、様になっているようでもあった。
しばらく考えて、思い至る。
そういえば彼は、この国では医者をしているのだ。
「生きるために必要なことだけやってても、味気ないものだよ。とりわけ俺たちは魔法使いだし――座りなよ、レノックス。どうせこの小屋には珈琲豆もないだろうから、手土産として持ってきたんだ」
「……仕事があります」
「三十分ぐらい羊も待ってくれるさ。安心してよ、結界を張ったし狼も襲ってこないから」
そうして陽だまりの中で、彼と二人で向かい合って珈琲を飲むことになった。
この奇妙な経緯で始まった茶会の中で、彼はよく喋った。誰それがこの小屋の近くに住んでいて、その妻が実は診療所近くの出身で、またその家はよい群青レモン畑を持っていて、等々。こんな調子でいつまでも喋っていられるようだった。
そのとき聞いていたレノックスに登場人物の名前は誰一人として覚えられず、また口を挟むこともしなかった。どこか遠い土地で出版された新聞の読み聞かせに、適当に相槌を打っているのと大差なかった。なにせ一年後のこの時期、この国にいるかさえ定かではないような頃合いだったからだ。
現金なことに、レノックスが唯一自ら口を開いたのは、フィガロが羊を守るために張った結界が自分にもできないかと尋ねたときのことだった。それでも彼は笑って親切に答えた。その魔力量じゃ無理。だけど柵に鈴を括って、柵が壊されたときにどんな場所でもその鈴の音が聞こえるようにはできるかもね。
そうするうちに、手元の珈琲はみるみるなくなっていった。土産の珈琲は、驚くほど美味しいと感じられた。旅の中で自分が淹れることもあったが、ここまで香り高くも味わい深くもなかった気がする。というより、かつては嗜好品の出来に気を配っていなかったので、いまフィガロが淹れた何倍もの速さで淹れていたはずだ。
次はゆっくり淹れてみよう、と密かに思った。どうせ羊飼いの仕事を引き受けている間は、急ごうが急がなかろうがどちらも変わらないのだ。
一息ついたところで、先ほどの自分の態度の無礼さに思い至った。その頃にはもう、時計の長針は半周ばかり進んでしまっていた。
「今日は、ありがとうございました」
玄関先で箒を出すフィガロを見送りながら、レノックスは言った。単なる社交辞令以上に聞こえるように言ったつもりだったが、それが伝わったのか伝わっていないのか、フィガロは来たときと変わらない完璧な笑みを見せた。
「明日はカーテンを開けてみるといいよ」
お医者さんの勘だけど、多分晴れてるから、と告げて去っていった。
翌朝、レノックスは目覚めて一番にカーテンを開けた。窓枠から見える空は、まだ夜空と言っても遜色ない暗さだった。晴れてはいるが、当然明るくはない。想像通りのものであった。
見慣れない光景を期待して、僅かに緊張していた糸がふっと緩む。いつも通りに手元の蝋燭に火をつけたところで、ふと、遠くの山岳の稜線が燃えるような橙色に染まっていることに気が付いた。
この国に来て、初めて見る空の光の色だった。
それもそのはず、この時間帯は刻一刻と常に空の表情が変化する。同じ朝でも、目覚めた瞬間と羊たちを放牧する瞬間の朝焼けは違う。そのことをすっかり思い出して、レノックスはしばらく、透き通った夜明けの空を眼鏡のレンズ越しに眺めていた。
眠気がすっかり消えた頃になって、昨日フィガロから受け取った珈琲豆を棚からこぼさないように取り出した。蝋燭台の火を移して水を沸かして、時間をかけて珈琲を淹れ、注いだマグを手に取れば、自然と窓際に足は向いた。
珈琲を飲みながら、窓を開ける。ひやりと冷たい早朝の風がひとすじ髪を撫でていって、珈琲の湯気と一緒に通りすぎていく。湯気がのぼる先に目をやると、取り残された月が青白く薄っすらと光っていた。
この月を見上げた瞬間、フィガロの言っていたことが、レノックスの中ですとんと腑に落ちた。
冴え冴えとした空気を湛えた南の国の空は、それほどまでに美しかった。
これがフィガロを見直したきっかけの一つだと本人に言えば、ずいぶんとロマンチックに覚えているね、と茶化すに決まっているので、話してはいない。
ただ、レノックスに言わせれば、何かに好意を寄せるきっかけなんて、決まってそういうものだろうと思っている。
いつかの告白
何ということもない一日に、レノックスとフィガロの二人が北の海まで遠出するようになった経緯は、さほど難しいものではない。
精霊の歌を聴いて空に踊った不思議な夜も明けて、世界の異変の解決や、賢者の魔法使いとしての責務を果たすいつもの日常が帰ってきた。とはいっても毎日厄災による異変や事件が舞い込むわけではなく、とくに魔法使いの家が出来てからというもの、厄災の絡まない依頼もしばしば見られるようになった。新聞記者のインタビューに応えることもあれば、今日レノックスとフィガロが受けた依頼のように、北の国の潮風が当たる崖でしか採取できない薬草が欲しい、という比較的平和な類のものもあった。
何を隠そう、これはファウストからの依頼である。何かと浄化作業や儀式の準備に白羽の矢が立つ呪い屋は、それ相応に呪具に対して手入れを怠ることはない。薬草の備えもその一つで、中央の市場の路地裏にある怪しげな店でいつも買い揃えていたらしいが、入荷の目処が立たないと断られたらしい。
運が良いのか悪いのか、今晩は満月だった。呪いの媒介になるようなものは、満月の夜に作った方が良い質になるものが大半だから、ファウストの手が離せない。
僕が日を改めて行ってもいいんですが、と相談を持ちかけられたのがフィガロである。当の師はほとんど間髪入れずに了承した。単純に採集など散歩が少し遠くなる程度の手間だったし、何より、相談されたのが嬉しかったのだ。
かつてのファウストなら、問答無用で自分でなんとかしていただろう、それが頼ってくれるようになってすごく嬉しくってね、と出立の準備をしながらべらべら喋っているフィガロを黙って見ていたのがレノックスである。
お供しましょうか、とレノックスはなんの気はなしに尋ねた。まあ人手はある方がいいよね、とあっさりした調子でフィガロは了承した。
羊たちを賢者に預けて、エレベーターに乗って、北の国に着いたとき、レノックスは北の厳しさをすっかり忘れていたことを悟った。フィガロの補助がなければ、海まで到達することはできないであろうほどの大荒れの天気だった。
そんなことは織り込み済みだったらしいフィガロは、さっさとレノックスに防寒やら防御やらを強化する魔法をかけて、軽快に箒に乗って、あっという間に海まで着いてしまった。そしてその後の採集もレノックスを荷物持ちにして難なく終え、颯爽と見晴らしのよい岬に軽やかに降り立った。
レノックスはといえば、張り切って動く彼に着いていくのが精一杯だった。エレベーターを出てから吹雪いていた周りの様子が岬に近付くにつれてだんだんと弱まっていたことに、採集が終わってからようやく気がついたほどである。
「とってもいい気分」
ちらちらと細かい雪が舞う中、彼は心底晴れ晴れとした表情をして伸びをする。眼下に広がる崖には、ときおり大きい波がぶつかって、腹に響くような低い音を立てて飛沫を上げながら砕けていく。そんな中で彼のように心からくつろいで伸びをすることは難しかったが、それでもフィガロの魔法に守護されている安心感のおかげで、周りの景色は素直に美しいと思えた。
人や魔法使いが滅多に訪れない地であるためか、雪が本当に白い。曇り空の下でさえ、多少きらきらと光っているように見える。雪の色、岩肌の黒ぐろとした色、枯れ草の色、海の色、曇り空の色。澄み渡ったそれらの色が渾然一体となって、レノックスの眼鏡のレンズに映った。
「あれ、俺のマナエリアって言ったことあったっけ?」
「こんな景色だって、言ってましたよね」
「そうそう。もうちょっと波が穏やかだと俺好みなんだけど」
何はともあれいい景色だろう、と笑うフィガロはいつもより無邪気に見えた。ポケットからハンカチを取り出して、軽く一振りすると、簡易的な椅子の形になった。レノックスも真似をして魔法を使ってみたが、だいぶ不格好なものができたので、フィガロが笑いながら座りやすい形に直してくれた。
「どうせ来たんだし、しばらくここにいたいな。無理強いしないけどレノもいるといいよ。もう少しすればあの辺りから、黄金色の光が差してきそう」
何も載せたことのない平たい雪の上に、ためらいなくさっくりと即席の椅子を載せ、そこにフィガロは腰掛けた。レノックスもそれに倣いながら、あの辺り、と見るからに上機嫌そうに雲の切れ目を指差す彼を見て、笑って応えた。
「ご相伴にあずかります」
「……そういえば、いつもと反対だね」
「どのあたりがですか?」
「いつもレノが好きな高原の景色とか、羊の放牧を見ながら喋ることが多いじゃない。俺の好きな景色を見ながら喋るのは珍しいよ」
フィガロの言葉を受けて頷きそうになったが、立ち止まって考えてから、レノックスは言った。
「そうでもなくなってきたかもしれません」
確かめるように賢者の魔法使いになってからの出来事を指折り数えていく。中央の国の橋から真夜中の景色を見た、ボルダ島で釣りをするために船に乗った、そして再び訪れたときにはファウストと共に系譜の流星雨を見上げた。そのひとつひとつに、嬉しそうに景色を眺める彼の横顔も一緒に浮かんだ。そうやって数え上げる指が片手を往復してから、そうだろうというようにフィガロを見た。
彼は少し、変な顔をしていた。驚きと照れが混じったような、不思議な顔だった。その表情を見ることができたのは一瞬で、すぐに彼は視線を海に戻してしまった。
「俺、そんなに色々嬉しそうにしてた?」
「ええ、まあ。見ていればわかる程度には」
「そう。……レノって、本当に、実はモテるタイプだよな」
「……? 今の繋がりありましたか?」
わからないならそのままでいいよ、と彼は口笛を吹くように返してきた。本当に気分がよさそうなので、わからないままでも別にいいか、とレノックスもすっかり納得させられてしまうような調子だった。
それから二人の間に、しばらく心地よい沈黙が降りた。
釣りをするにしても羊が草原に散らばっている様子を見るにしても、幾度となく訪れている沈黙で、気まずさはなかった。レノックスは海を見ながらぼんやりと、いつから沈黙が苦にならなくなったのだろうと思う。
気が付けば、喋りたくなった方が何となく喋りはじめるのが、いつものことになっている。
フィガロはまるで海の果てまで見通すように目の前の光景を見つめていたが、おもむろにレノックスの頭をみて、わ、と呟いた。それから髪の毛をいじるような動きをしたので、吹雪で乱れていたのかと思いきや、直す時間が少々長い。耐えかねて、「どうしましたか」と声をかけた。
「頭に雪が積もりそう。レノの魔法のかけ方だと限度があるな」
直していい?と尋ねてきたので、もちろんですと応える。すぐに《ポッシデオ》と呪文が呟かれたと思うと、確かに頭の冷たさが幾分かふわりと和らいだ。
彼に礼を告げながら、この地の環境の過酷さを改めて実感する。レノックスの魔法の技量では、北の国で生きていくための魔法でさえも永続して使うことが難しい。四百年前にファウストと共に来た頃は若さと使命感から来る勢いで何とかしたが、それ以降、旅の途中で北の国に向かおうとすれば必ず無理が生じて、分不相応な環境だということが身に沁みてわかっていた。
今もフィガロがいなければ北の海は恐ろしいものだな、と思うに違いない。
どこまでも海原が広がる光景は壮観だが、波のうねりはどこか生きているように不気味で、岩礁に波が叩きつけられる音は海水の重さがどれほど大きいかを克明に伝える。
のどかな高原にはない、こちらを脅かしてくるような美しさが北の海にはある。フィガロが北の海を好むのも、当人が危険をものともしない力があるからだろうか。
「どうして北の海が好きなんですか?」
唐突な問いかけになったが、フィガロはいつものように茶化してきた。
「何、急に。フィガロ先生のことがもっと知りたくなった?」
「いや、俺は海というより、山の方が性に合っているので気になって」
ここはどんな理由であったとしても知りたくなったと頷いておくところだろう、と彼は小さくこちらを小突いた。
身を守るための魔法をかけられたレノックスが、すぐに質問してきたことからなぜそう尋ねたくなったのかは察せられたのか、一拍おいてから彼は真面目に語り始めた。職業病なのか、雑談であってもどこか授業を行う教室を思い出させる口ぶりになった。
「単刀直入に言ってしまうと、なんとなくなんだけど。――海の良さがわからない山派のレノに、海の好ましいところを教えてあげよう」
「……どうも」
「じゃあレノ、目を閉じて波の音を聞いてごらん」
三百年前の自分にあの危険な北の国で穏やかに波の音に耳を傾ける日が来ると伝えても、まさかそんなことは起こらないだろうと端から疑うだろうな、と他人事のように考えながら、レノックスは目を閉じた。
いまいる位置からずっと下の方で、波が砂浜を洗う音が聞こえてきた。どうやら一部は砂浜になっているようで、水が岩肌を叩く低い音に混じって、崖の下の方から聞こえてくる。ずっと遠くから近くへとだんだん寄せてくる低い音に、自然と凪いだ心地になってくる。
「フィガロ先生」
「うん?」
「俺が寝そうです」
「あはは、北の国で肝が据わってるね。目を開けて」
目を開けると、冷たく鋭い北の風がひとすじだけ頬を掠めていった。きっとフィガロの悪戯だろう。起きたかと問うてくる目線にしっかりと頷く。一瞬で眠気も吹き飛ぶ、刺すような冷気だった。
「波の音って、眠たくなるくらいリラックス効果があるんだよね。リズムもそうなんだけど、耳に聞こえない音も発せられてて、それが心身に良い影響を及ぼすんだとか」
「そういえば、ムルも同じことを言っていました」
「何を隠そう、ムル・ハート氏の著書からの引用だからね。海洋学者なんじゃないかと思うくらい、他にも色々言っていたな。全ての生物の元は、海から生まれたとか」
「……そうなんですか?」
レノックスは少々驚いて聞き返してしまった。直感的に、あまり信じられない話だったからだ。
自然とともにある精霊さえ、魔法使いの呼びかけに応えなくなっていくのが海だ。全ての生物の祖先が生まれたところならば、逆に精霊がたくさんいるところなのではないだろうか。何もないなんて、言われないのではないだろうか。
そういったことをフィガロに話すと、南の国の先生役らしい顔つきで頷いた。
「ムルの話は仮説の一つだからね。レノの仮説が正しいかもしれないし、どちらも間違っているかもしれない」
「先生はどう思いますか」
「うーん、ムルの言う通りなら、海を見てなんだか落ち着く理由になって面白いかな。……ああ、話が堂々巡りしたか。他のアプローチも行こう」
そう言って彼は、「海が好ましい理由」をいくつか挙げていった。哲学書から有名な詩の一節、そしてレノックスが読んだことのある小説からも。最強の魔法使いであっても打ち壊すことができないから、海水をどれだけ掬っても海はなくならないから、海は途方もなく広くて未知の領域が尽きないから――浪漫があるよね等々、コメントしながら引用していった。
フィガロの授業はどんな切り口であっても意見していい授業だった。長生きの魔法使いらしく、年下のどんな意見でも面白がって聞いているのがよくわかる。レノックスはフィガロよりも複雑に考えることはできないものの、疑問に思ったことをいくつか質問して、議論を少しずつ深めることに貢献した。
立て板に水の勢いで、海に関する様々な解釈をフィガロは語った。二千年も生きていればこの手の話題はあらかた考えられて引き出しは尽きないようで、レノックスの質問にも淀みなく答えていった。
いつもよく喋るフィガロだが、機嫌がいいと輪をかけて饒舌になる。レノックスは長い付き合いでよくわかっていた。だがそのことを思って、なぜだかふと、一抹の不安が胸によぎった。
なぜだろう、とレノックス自身も不思議に思う。上機嫌そうなフィガロ。尽きない話題。楽しそうに語る彼の話に自分も耳を傾けている瞬間。不安を抱く要素は何もないはずなのに、胸の内の不安を拭うことはできない。
しかし概して、直感というものは正しいことが多い。胸の中のざわめきの正体をあれこれ探り、似たようなときはなかったかと突き詰めていくと、違和感の影を掴むことができた。
――こういうときこそ、目の前の彼は、冗談を言ってしまう癖があるのだ。
轟音が辺りを震わせた。崖下で一際大きい波が押し寄せてきて砕けたのだ。それに眉根をひそめるように、フィガロの表情にも憂うような色が差す。
端から見ている者からすれば、それはまるで今から言うことが冗談であることを大げさに示すような、ひどくわざとらしいものであった。
「まあいろいろ言ったけどさ、結局は海って退屈だよね。寄せては返す波の動きが百年も千年も一万年も、永遠に続いてさ」
「まあ、わからなくもないです。単調なので」
「そう。だから海って、永遠に退屈なところが牢獄と似てる」
「……」
「そんな牢獄にいれば、どんなに洗い流せない重い罪だって許される気がするから、俺は海が好きだよ」
「……ミチルやルチルに言わないでくださいね。冗談といえど、困ってしまうでしょうから」
わざわざ物憂げにしていた表情を崩して、フィガロは「やっぱりレノは真に受けないね」と微笑んだ。本当に際どい冗談を言う人だと思う。彼やファウストが経験してきたことを思うと、彼のように笑うことなんてできない冗談だった。海が牢獄のようだなんて、そして牢獄が救済に繋がっているようだなんて、レノックスからすれば呪いのような連想ゲームだとしか思えない。
だがしかし、連想は連想で、どんなようにも作ることができる。無理なこじつけに近い連想も、フィガロの手にかかればあたかも綺麗な等式が成り立っているように語ることができるはずだとレノックスは理解していた。
これ以上彼が際どい冗談を重ねなくて済むように、レノックスはきっぱりと言った。
「わざわざそれらしい理由を並べなくとも、なんとなく好きだという理由に、俺は納得しましたよ」
「俺らしいから?」
「はい」
「あはは、それ、賢者様にも言われた。俺もそう思うよ」
これで海の話はおしまい、というように彼は静かに笑った。
この世界にいる住人よりも遥かに海のことを知っているはずなのに、なんとなくマナエリアになるほど好きだ、と言うのがフィガロらしいといえばフィガロらしかった。
だからレノックスは、語られる「海が好ましい理由」がただレノックスを納得させるためのもので、それらはフィガロにとっても特に重要でなく、冗談も冗談だとすぐわかったのだ。
肩に軽い重みがかかる。隣を見ればフィガロが寄りかかってきていて、「喋り疲れたから肩貸してよ。あったかいし」と事後報告として言われる。寄りかかりやすいように調整してやると、彼は「ありがとう」と呟いた。
「……いまいちピンとこないんだよね。その土地にいるとリラックスできたり、力が湧いてきたりする理由がはっきりあることが」
理解はできるんだけど実感はないというのが正しいかな、とフィガロは付け足すように語った。反対に、レノックスもそうだった。なんとなく落ち着く場所があるというのは理解できるが、理由もなしに落ち着ける場所があったことは、実体験としてはあまりない。
「レノのマナエリアは生まれ故郷で、やっぱり理由があるだろう。……そうだ、南の国はどうだった?」
「どう、とは」
「気に入った具体的な理由があったかってこと」
榛色の虹彩に縁取られた菱形の瞳孔が、興味深そうにレノックスを覗き込む。南の国を気に入った理由、と考えると、南で暮らして見てきた景色がいくつも頭に浮かんだ。羊たちとクーリールが穏やかに過ごしていた青々とした草原。幼いルチルがこれまた幼いミチルを箒の後ろに乗せて飛んでいた空。ファウストにまた必ず会えるとチレッタに励まされながら見た夕焼け。
どうやらやはり、彼と違って、なんとなく好きだというのでは済まないらしい。
「……俺が南の国に来たとき、何かをひと目見て気に入った、というわけではありません。色々なことが積み重なって、それが旅の疲れを癒やしてくれていたんだと思います」
「例えば?」
そうフィガロに問われて頭に浮かんだのは、冷涼な風を受けながら見た、美しい朝日のことだった。ちょうど目の前にいる相手のアドバイスがきっかけのことだ。あの日も今日と同じくらい空気が澄んでいて、また眠気を攫ってしまうほどに冷たい風が吹いていた。
「昔、フィガロ先生がカーテンを開けて朝日を見るといいと言ったことがあったじゃないですか」
そこで言葉を切った。これは覚えていたことを絶対にからかわれると思って、本人に言っていないことだったと思い出したのだ。いつもフィガロほど複雑に考えずに口に出してしまうから、こういうことが度々起こってしまう。レノックスはそのまま黙って、彼の反応を伺った。
意外なことに、彼はしばらく考えた後、「俺が言ったのはカーテンを開けろってことだけだったよ」と訂正した。覚えていることに驚いたレノックスが思わず聞き返してしまうほど、当然のことのようにあっさりとした返事だった。
「そうでしたか?」
「そうだよ。そうか、俺のおかげでレノは綺麗な南の朝日を見たんだ。善いことをしちゃったなあ」
肩に寄りかかる彼は小さく笑った。軽い言葉とは裏腹に、少し照れているようでもあった。
なぜだかレノックスはその様子を見て、これからどれだけ茶化されたとしても、あの日見た景色がどれだけ美しかったかをもっと伝えたくなってしまった。何せ南の国のみならず、フィガロに抱く印象を変えた出来事の一つだったからだ。
「……綺麗なのは、朝日だけではありませんでした」
あの日見た山岳の稜線も、薄くたなびく雲も、夜と朝が混ざったような空の色も、わずかばかり溢れるように見える朝日も、全て美しいものだった。それは全部、レノックスが暮らす小屋の閉じたままだったカーテンを開けた、フィガロが気付かせてくれたものだ。
伝わるだろうか、と思った。今日話していて垣間見えたように、どうやらお互いに物事を好ましいと思う基準が違うようだから、伝えるのが難しいのかもしれない。なるべく正確に伝えたいから、多くの言葉と時間を必要とするのかもしれない。だがそんなものは、今更のことだ。たとえ見方が違ったとしても、きっとフィガロは耳を傾けてくれる。そう思えた。
「少し長い話になります。いいですか」
「いいよ。夕飯前にファウストに薬草を届けられるくらいならね」
フィガロが指差す太陽の傾き加減をみて、レノックスは頷いた。高い位置にあって、先程彼が言っていた雲の切れ間から光も差していなかった。まだ存分に時間はある。
レノックスは記憶の引き出しから美しい景色を丁寧に取り出して、その欠片を一つずつゆっくりと語り始めた。
Fin.