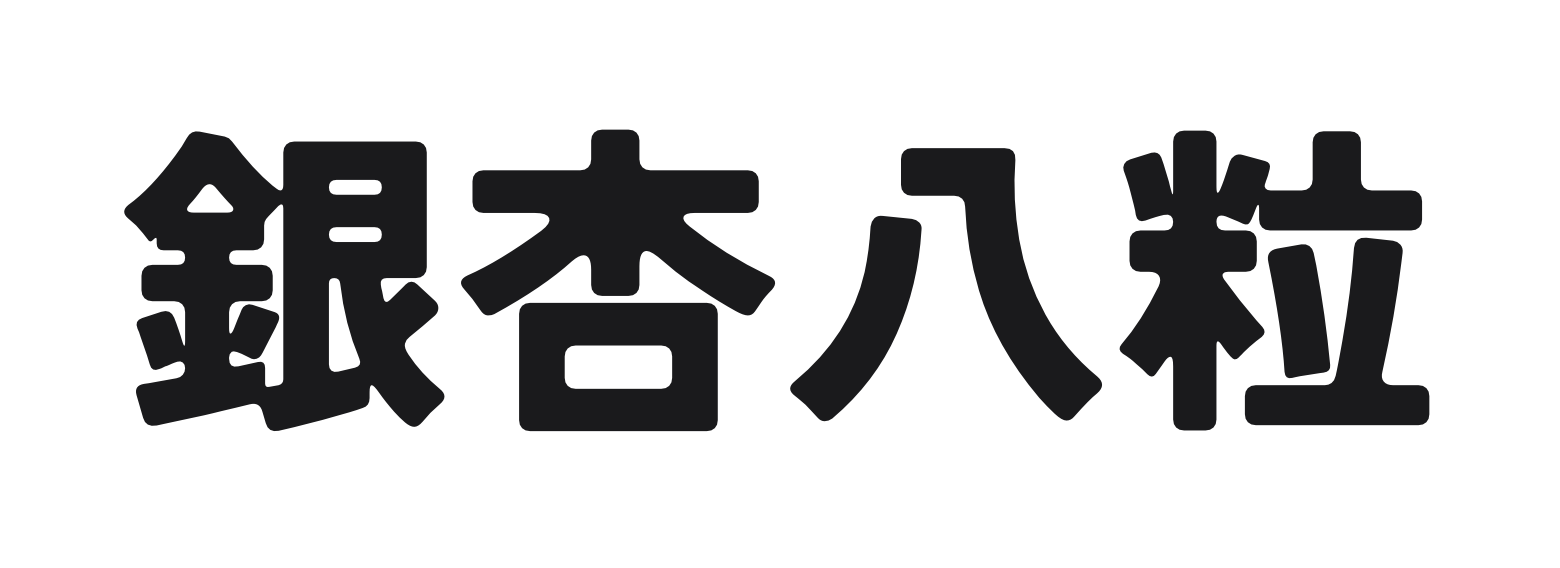フィガロ先生は運動不足だから、少しは身体を動かした方がいいと思うんです。
レノックスからの有難い小言を、フィガロはグラスを傾けることによって聞き流した。夕食後、レノックスの部屋で、こうして二人でだらだらと飲み交わしているとき。今晩と同じようなシチュエーションで、同じようなセリフを過去何十回と聞いている。もはや正確な回数を思い出すことは不可能なほどだ。今回もまたその過去と同様に、何気ないフィガロの発言が大本のきっかけだった。
たまたま受けた依頼が大っぴらに箒に乗れないもので、足を使って調査を進めていたら、久々にかなり歩くことになり、結果として筋肉痛になってしまった。この世間話のエピソードトークはフィガロとしては労うか笑うかして酒の肴にしてほしかったのだが、真面目なレノックスはこくりと頷き、間髪入れずに生活習慣の改善を促してきた。
真摯な赤い瞳を向けられて、面倒だなあと思ってしまうきまり悪さとは別に、胸がすくくらいの心地よさを感じてしまうものだからこうした失言を完璧になくすことはできない。
レノックスが自分を思いやって慮る言葉をくれるのは、柔らかい羽根でくすぐられるみたいに嬉しい。しかしながら、うっかり口を滑らせてしまってあまりやりたくない運動という現実的な話を聞くことになったのは正直なところ、結構嫌だ。酒が入っているのなら、どちらの思いも倍増してフィガロを襲う。
相反する感情を持て余していると、開き直りとも呼べる感情がじわじわ沸き上がってくる。毎朝トレーニングを重ねる彼からすれば大抵の魔法使いは運動不足のはずで、そうなったらもう、仕方がなくない?
頭の回転が速いことが災いして、嵐のように胸を駆け抜けていったこれらのことを全て詳らかにするわけにもいかず、フィガロは黙って手元の酒を飲むことにした。文句ひとつ零さないので、傍から見れば小言を受け入れる殊勝な態度といえる。しかしながら、レノックスは聞いているふりをしているだけだとあっさり看破してしまう。長年の付き合いは伊達ではなかった。
正確にこちらの心情を読み取ったのであろう彼は少し考えて、こんなことを言ってきた。
「フィガロ先生、これから散歩に行きませんか。以前夜通し橋に行けたなら、今からでも行けるはずです」
「ええ、筋肉痛になった相手にそれ、勧めるの?」
「三日前の話でしょう、痛みももうないはずです」
こちらの雑談に積極的に口を挟まないのでそうとはわかりにくいが、彼は話をよく聞いてよく覚えているタイプである。鎌をかけてもなお運動を勧めてくる相手に観念して、どこに行くつもりなの、とワインボトルから残りの酒を注ぎながら尋ねた。
あと少し遅かったら二本目が空いていて、もったいないからと外出することもなかっただろう。あっさり空になったボトルを恨めしく眺めていると、控えめに彼が提案した。
「植物園はどうでしょう。中央の王立なら、箒に乗らずに行けると思います」
「へえ、なかなかいいチョイスだね。でも今、閉園してると思うよ」
フィガロは時計に目をやった。長針を見るまでもなく、窓から覗く外の暗さが公共施設はとっくのとうに閉まっていることを示している。
その疑問を見越していたように、彼はひとつ頷いた。
「今月は、夜まで開くそうですよ。魔法使いの家に来ていた人から聞きました」
「ふうん。何時まで?」
レノックスが口にした時刻は意外なほど深夜で、フィガロの方が驚いてしまった。聞けば、ランタンで植物園をライトアップし、いつもと異なる植物の姿を見ようという試みが行われているらしい。
本当にやっているのかと確かめるように訊けば、レノックスは机の上から一枚のビラを取り出して見せた。それは城下町の出来事がいくつか載っている地域新聞のようなもので、少し探すと目立たない程度の大きさで植物園はしばらく夜間開園します、と確かに記載されていた。日付と時刻も彼の言葉と一致している。夜中に開くのもあり、治安が悪くなってもいけないからと、大々的に公開されていないようだった。
検分するようにその小さな紹介文を眺めて、フィガロは顔を上げた。
「やたら用意がいいね。レノってそんなに植物が好きだったっけ」
「この話を聞いたとき、フィガロ先生と行きたいと思ったので」
さらりと恥ずかしげもなく、口説き文句を告げられる。予想だにしない不意打ちに、フィガロもからかうタイミングを逸してしまった。
――真夜中にひそやかに開いている植物園の話を聞いて一緒に行きたいと思ったのは、あなたでした。
そういう、フィガロが言うとしたら湾曲させて伝えるようなシンプルな好意を、彼は惜しみなく伝えてくれる。
だが、同時に忘れてはならないところもあるのも事実である。
「先生の運動不足解消のために行くとは、思っていませんでしたけど」
例えば、現実を思い出す台詞をしっかり付け足してくるところとか。
ため息をつき、フィガロは文句を言った。
「その一言、必要だった?」
「言わないと、これからも先生は運動しないじゃないですか」
表情を崩さずに、机の上に残ったつまみをつつきながら彼は言う。
レノックスはこういうやつだった。言われたこちらも照れるような台詞でさえ、ひたむきで真面目な自分のペースの延長線上で言えてしまう。こちらが必要とする矜持との折り合いや自然なきっかけを必要とせず、その他もろもろの発言に至るまでの障害をないものとして、ストレートに好意を伝えることができる。そしてそのあと、しれっとした表情で雑談に戻ることができる。
最後のはともかく、全体的には間違いなく彼の美徳なのだが、フィガロとしてはかねてからずるいだろうと思っている。
彼の素直で混じりけのない言葉に、多少なりとも弱い自覚があったので。
手元のグラスを一気にあおり、行こう、とフィガロは宣言した。
モンステラは語らない
植物園は各国それぞれに点々と存在している。個人が所有するところもあれば、国が管理するところもある。魔法がかかって人知れず年中移動し続けるものもあれば、魔法の一つさえかからず、常にそこにあり続けるものもある。
レノックスが誘ってきた中央の王立植物園は、一般公開されるために丁寧に管理され、当然のことながら魔法がかけられていない植物園だった。そういう公共施設の例に漏れず、魔法使いの家があるような街の中心地よりかはいくらか離れた場所に広い土地を持っている。
レンガ造りの立派な門が、植物園の入り口だった。掲げられている地図によると、広大な中庭のほかに、豪勢にもいくつかの気候を再現するためのドームや温室があるという。フィガロはさすが国王の威信をかけているものだと感心した。
「アレクは設立に関わってないみたいだね」
レノックスの目線がそれとなく植物園の説明書きの上を動いていたので、独り言のように言った。
「グランヴェル王朝中期に文化的な活動が活発になったから、設立はその時期だろう」
「……今でも続いている王家に向かって中期と表現するのは、不敬かと」
「そう? でもきっとアーサーなら許してくれるよ。王朝より年長の俺を立ててね」
レノックスは困ったように笑った。肩の力が抜けたのを確認して、フィガロは券売所の受付のベルを鳴らした。無人だったが、明かりがすぐについてチケットを二枚買うことができた。
威圧感さえある大きな正門は当然ながら開くことがなく、隣に控えめにある小さな通用門をくぐることになった。頭をぶつけないでよ、と言ったら思い出したように彼は屈んで通ったのが、なんだか可笑しかった。頭をぶつけないように常に確認する癖をつけるのは、四百年経とうが不可能らしい。
入ってすぐの中庭には、道を示すように点々とランタンが置かれていた。平日ということもあってか人はまばらにしかおらず、隣人以外の喋り声は夜風に紛れてほとんど聞こえない。
確かに花壇や樹木がランタンのほのかな明かりに照らされているのは幻想的であったけれど、フィガロがいっとう興味を惹かれたのは光の揺らめきではなかった。
まず広葉樹の樹液の香りがして、それから花壇にあるであろういくつかの花の香りが混ざり合うように溶け込んで香った。木の葉が擦れる音に紛れて梟の声が遠くで聞こえて、耳を澄ませば足元の虫の鳴き声が聞こえてくる。
人工的に整えられた場所だからこそ、気持ちいいほど吹き抜けていく風が色々な情報を運んでくる。夜中の濃密な暗闇も相まって、この場では全ての存在の気配が色濃く感じることに気が付いた。
もちろん隣で歩いている相手の存在も例外ではない。足音がいつもより近くで聞こえてくる気がする。小枝を踏みながら闇の中でもなお一定のリズムを崩さないその足音が、昼間のそれよりもなんだか落ち着く響きを持っていた。
花壇に目を向けると、ランタンに照らされた花々は、少し歩けばたちどころに種類を変えて現れては消えていく。あまりにも多くの種類の花々が植えられているためだ。それを眺めて、フィガロは思い出すことがあった。
「賢者様がさ、前に俺たちを連想して植物を選んでくれたときあったじゃない」
「はい。俺はモンステラで、フィガロ先生は……」
「アカツメクサ。なんだか絶妙だよね」
かつて賢者が賢者の魔法使いらしいと思っている植物を、二十一人それぞれ伝えてくれたことがあった。自分に告げられたアカツメクサについて、バラやコスモスといった分かりやすいものではないところをフィガロは気に入っている。賢者らしく、ひとりひとりに時間をかけて考えてくれたものだということがわかるからだ。
「ねえ、レノってアカツメクサのこと知ってた?」
たまたま現れた”多年草”の花壇にかがみこみ、フィガロは訊いた。知らないと言われても大して気にしないような質問だったが、隣にかがんだ相手は迷いなく、フィガロの奥にあったアカツメクサを指さした。
「知ってましたよ。羊たちがよく食べていますから」
「……俺らしいと思う?」
「思いました」
その先の理由を促すように、ランタンの炎を反射する眼鏡の奥の瞳をじっと見つめた。
視線に気付いたレノックスは、考えるように黙ったあと、立ち上がって手を差し出してきた。答えをうやむやにしたくて歩きたいというわけではないというのはわかっていたから、フィガロはその手を借りて立ち上がり、彼に並んで歩いた。
花壇に置かれた明かりに照らされたときに見た表情は、取って付けた理由を考えるのではなく、思っていることを正確に示す言葉を探っているようだった。少し経ってからもまだ考えているような声音で、探りながらも彼は答えた。
「アカツメクサやシロツメクサ……クローバーは、生えているときには土に栄養をもたらしますし、そのまま耕しても栄養になります」
「うん」
「そんな力を持っていても、子供たちが花冠をつくれるくらいに身近にあります。そういう身近さが、フィガロ先生らしいと思います」
フィガロは口角を上げた。寡黙なレノックスがこんなにも言葉を尽くしてくれたことが、どれだけ貴重なことかはよく理解している。理解してなお、今宵吹き抜ける夜風のような心地よさを持つ彼の言葉だからこそ、フィガロは欲深くもそれ以上を求めた。
「ありがとう。じゃあ、賢者様が俺に選んだのはシロツメクサじゃなくてアカツメクサなのは、どうしてだと思う?」
きっと相手は難しい顔をしているだろう。暗闇の中でもわかった。白い花のクローバーか赤い花のクローバーかなんて、花言葉をよく知らないだろう彼にとって、はっきりとした違いは感じられないはずだった。
それでも想像よりずっと早くに、フィガロ先生の望むような答え方ではないかもしれませんが、と前置きして彼は続けた。
「……俺個人の感想でいうと、アカツメクサの方が、実用的で南の国らしいと思っています」
「実用的」
「はい。羊飼いからすれば、羊がクローバーを本当に食べ過ぎたときには毒になるので、草原で色がついていた方がわかりやすいです」
赤色が減り過ぎていたら放牧する場所を変えます、と至極真面目な羊飼いの声音をして言うので、フィガロは思わず声を上げて笑ってしまった。羊の食べ過ぎを防ぐようなところに南の国らしさ、ひいてはフィガロらしさを賢者が見出したとは思えない。それでも笑ううちにフィガロは、レノックスの答えをすっかり気に入ってしまった。
南の子どもたちが作る花冠にはシロツメクサが選ばれることが多いだろう。クローバー探しをする花畑にもシロツメクサが多く群生しているだろう。それと比べると、アカツメクサの出番は少ないのかもしれない。けれども確かに、南の国の暮らしをひっそりと支えているものの一つに、アカツメクサはあるのだ。
彼の答えに感化されて、頭に思い当ることがもうひとつあった。
「そういえば、俺のハーブティーにもたまに入れてるよ。羊の餌としての便利さは初めて知ったけど、実用的なのは確かだね」
「知らなかったです。入れられるのは、アカツメクサだけなんですか」
「そう、そっちだけ。味がないから俺も忘れてたんだけどね」
自分でも見落としていたアカツメクサへの一面をレノックスが見抜いたことに、フィガロは素直に感心した。それから付け足すように、かねてより考えていたことを口にした。
「賢者様はたぶん、シロツメクサの花言葉に”約束”ってあるから避けてアカツメクサにしたんだと思うけど」
「……フィガロ先生、それは賢者様に一回ちゃんと聞いた方がいいですよ」
案外深刻な声音で返事をされたので、そう? と返しながら考える。確かにあの賢者がシロツメクサを避けるためという消極的な理由でアカツメクサを選んだ、というのは若干の疑念があるかもしれない。誤った思い込みで決めつけるのは、賢者にこそ失礼なのかもしれない。
それじゃあ後で聞いてみるよ、と呟くように口にした。気が付けば広い中庭を越えて、温室が暗闇の中に現れ始めていた。なぜわかったのかといえば、一部がガラス張りになっていて、そこから明かりが漏れていたからだ。温室の中は屋外より明かりに恵まれているらしかった。
やはりレノックスと喋っていると、いつのまにか時間が過ぎてしまう。
あの、と引き止められて、フィガロは立ち止まって後ろを振り返る。一番近い光源のランタンは地面に置かれているので、ぼんやりとした光でレノックスの表情はよく見えなかった。けれどもその影の立ち姿にさえ、彼の真摯さがよく現れていた。
「アカツメクサのことについてたくさん言いましたが、フィガロ先生らしいと思うのは……土地が豊かになるのを支えているところだと、俺は思います」
素直で混じりけのないその言葉を聞いて一瞬、息が詰まった。
「結局全てそこに行き着くなと思いまして」
「それは……ありがとう」
色々言いたかったけれど、結局言えたのは一言だけだった。どうして彼はいつも、無意識にもこちらの琴線に触れてくる言葉をくれるのだろうと不思議に思う。
思えばいつかに鹿の話をしたときでもそうだった。村人から崇められ大事にされてきたにもかかわらず、襲ってきた災厄に庇護すべき誰をも守れず己だけが生き残ってしまった鹿の話。フィガロが語ったのはここまでだったけれど、レノックスの手腕により、またたくまに前向きな結末へと昔話は変貌した。きっとその鹿はその後丈夫な住処を作っていて、そこには災厄に負けない村があるはずだと。
そんな風に話を締めくくってくれた彼が、今晩はこんなことを語ってくれる。
フィガロは小さく笑った。胸に湧くあたたかく澄んだ気持ちを言葉にするのは何もかも野暮だったけれど、こんな暗闇でそれでは彼に何一つ伝えられないのがもどかしかった。それでも彼は伝えたいことは伝えきったとでもいうように歩き始める。やはり彼はずるい、このもどかしさを自分にだけ残していってしまうとは。
胸を駆け巡る複雑な感情をどうにかしたくて、彼の肩を二回、軽く叩いた。
「どうしたんですか、急に」
「……機嫌がいいから」
その一言だけで押し通した。鈍いレノックスにそれだけでこちらの機微が伝わるとも思っていないが、幾らかの用をなさない言葉を使って中途半端に伝えるよりも、いっそどうやったって完全に伝わらない方法をとるのが遥かにマシな選択だと思った。意外にも困惑していた雰囲気があっさりと柔らかくなって、「それはよかった」と告げられた。
きっと彼も小さく笑っていたに違いない。先ほどまでよりほんの少し、並んで歩く距離が近くなったから。
***
フィガロと共に入った温室には、教会に似た静謐さがあった。
まばらに入っている客の足音と、どこかで流れる水の音が微かに聞こえてくる。フィガロの硬い革靴が石畳を踏むたびに、足音がどこかで小さく反響しているのがよくわかる。道に等間隔で置かれたランタンの中の火が、ぱちぱちと小さく爆ぜる音がした。
この誰も生きていないような空間には、その実、数えきれないほどの種類の植物が生きていて、呼吸をしている。風も吹かず自然とはかけ離れている状態だというのに、レノックスはそれが不思議でならなかった。
元々暗がりになりやすい温室では、屋外よりもよほど潤沢に明かりが灯っていた。街灯のような高さのランプが全体を照らしているし、花壇だけではなく木々の間にランタンが置かれている。
薄明りの中ほのかに見えるようになったフィガロの表情は、先ほど彼が言ったように上機嫌そうで、口数が僅かに増えているのがレノックスにもわかった。あの木の種は綺麗な青色なんだよとか、バナナの種類って信じられないくらいあるよねとかいったことを、それぞれタビビトノキやバナナの木の解説文に先走って喋っていた。静かなこの場所ではそれが足音のテンポと重なり、心地よく響く。
頷きながら聞いていると、レノックスに問いかけられた賢者に選んでもらった植物についての質問が、彼だったらどう答えるだろうと次第に気になってきた。博識な彼のことだから、レノックスの知らない植物の一面を知っているはずだ。
温室の中でモンステラが見えたら切り出そうかと思ったが、あいにく室内で育てられることくらいしか知らず、分類上はどこになるのかもよくわからない。仕方ないので、彼の喋りの合間に挟むことになった。
「あの、俺って、モンステラみたいですか?」
フィガロは振り返って榛色の瞳をこちらに向ける。これでは彼の視線を植物から自分に向けたいみたいだと、言ってから気が付いた。からかわれるかもしれないと思ったが、彼はすぐに頷いた。
「みたいだと思うよ」
からかわれなかったことに安堵しつつ、何故かと目線で訊くと、視線を外してしばらく考えてから一息に答えてくれた。
「観葉植物の代表格だから、みんなから親しみを持たれている。枯れにくくて育てやすいから、世界中のどんな家の環境下でも育てることができる。あと花言葉が確か……嬉しい便りだったかな。レノにぴったり」
歩きながらフィガロは指折り数え、それから首を傾げた。
「なんだかレノが言ってくれた理由より弱いな」
「そんな。とても嬉しいです」
レノは欲がないね、とまるでもっと欲を持てと言わんばかりの口調で言われる。そうは言うものの、本心からレノックスは嬉しかった。モンステラについて知らなかったことを知ることができたし、そこになぞらえて「らしい」と言ってくれたことが嬉しかった。もう三つも理由を貰っておきながら、これ以上を望む強欲さは持ち合わせていなかった。
それでもフィガロは自身の回答に納得いかない様子だった。
「でもレノは自分の経験から言ってくれたから、そうだな、俺も個人的な話をしようかな。モンステラの話か……」
「無理に捻らなくても」
「いや、あるんだよ。あるんだけど、どこから喋ったらいいかなって思ってる」
悩むようにフィガロは腕を組んだ。それでも歩くペースは変わらない。角を曲がると、突然背丈の倍はある滝と、そこに生い茂る草木が現れた。彼は口を閉じたままその風景を眺めていたけれど、滝つぼに落ちる力強い水音が沈黙を埋めた。
珍しくも迷いのある彼に興味を惹かれて、気が付けば言葉が口をついて出ていた。
「最初から最後まで聞きますよ。フィガロ先生の話なら」
「……口説いてる?」
話題を逸らさないでほしかったので、そのままフィガロをじっと見つめるに留める。しばらくしてから彼は降参して、「口説いてくれるんじゃあしょうがないね」と軽い口調で語り出した。
「もう過ぎた話だし本題じゃないからここはあまり突っ込まないでほしいんだけど。昔、自分の部屋に置いてある植物を全部森に返したことがあってね」
「手放したんですか?」
「そう。『植物は愛をあげた分だけ返してくれるからいい』とか言われ始めた時代だったかな。俺のエゴに付き合わされるのも可哀そうだと思って」
植物ばかりのこの場所で、いまも自身の部屋に一つも植物のない彼は、凪いだ瞳をしている。もはやその感情全てを味わいつくした瞳だ。今語っているのはあまりに遠い過去の出来事であるということは、その表情を見たレノックスにもわかった。
突っ込まないでほしいという彼の言葉をレノックスは律儀に守り、それ以上は何も言わなかった。言わなかったが、想像してみることにした。
最初はそんなつもりもなかったのに、植物を育てることに妙な意味合いを見出されてそれにうんざりしてしまう。けれど心の奥底では確かにその意味合いで育てていたのかもしれないと疑い始める。疑いは大きくなり、何かの代替品のように自分に付き合わされる植物が可哀そうだと、手放してしまう。
自分はしないだろうが、わかるような気がするとレノックスは思った。実際には、突っ込みたいところは多々あるけれど。
彼は目配せしてこちらの様子を伺った。絶対にこちらが何か言いたいに違いないだろうことはわかっていたようだ。それでも黙ったままでいると、一息ついて続けた。
「その後も薬草を育てなきゃいけなかったり、診療所に植物を置いた方が何かと患者の気分転換になるだろうって置いたりして、もう別に気にしなくなったんだけど」
「……けど?」
「診療所にはモンステラが置いてあるじゃない」
急な話題転換で、レノックスは面食らって咄嗟に思い出すことができなかった。
「ありましたか」
「こんな立派なやつじゃないけど。机の上に」
足を止めた彼が指さした先をぱっと見上げる。
目に飛び込んできたのは勢いよく水が流れる滝と、モンステラの特徴的な切れ込みが入った大きな葉だった。滝の存在には先ほどから気が付いていたけれど、モンステラの方は視界に入っていたはずなのに気が付かなかったことに驚いた。それほどまでに、いつも見る観葉植物の姿とは違っていたのだ。
そもそも滝の近くにモンステラが育つことが意外だった。背が高くなく、どちらかといえば大きな蔦の葉ように茂っている。茂った葉が、滝のそばにある岩肌を隠しているほどだ。
縦に伸びる種類だけではなくて横に葉を増やしていく種類もあるのかと考えたところで、診療所の窓辺の日差しを浴びるモンステラが頭に浮かんだ。
「……思い出しました。確かにありましたね」
「今も枯れてないはずだよ。魔法をかけてあるから」
レノックスの記憶にあるモンステラは、確かにたっぷり日光を浴びて葉が艶々としていて元気だった。自分にあてがわれた植物が南の診療所で手間をかけて育てられていたとは、なんだか不思議な心地がする。
そこで彼は、小さく息を吸った。
「レノに選ばれたのがモンステラだって聞いたとき、診療所にあることが嬉しかったよ。逆説的だけど……いま診療所にいてくれているところが、レノらしいと思う」
はじめは彼の言葉を文字通り受け取って、素直に嬉しく思った。けれど、これまでの話を思い出して彼の言葉を改めて反芻すると、それは、とレノックスは言いかけた。
――昔部屋に置いてある植物には苦い記憶があったけれど、それでも、いま診療所に置いてある植物がきみらしいと選ばれて嬉しい。そしてそんな過去を経たのちのいま診療所にあるところが、きみらしいと思う。
それは、ずいぶんな口説き文句じゃないですか。言ったところで彼は真面目に取り合わないだろうが、どうしても聞きたくなった。けれどもその問いかけは、ついぞレノックスの口から出ることがなかった。
フィガロが胸に飛び込んできて、キスをしてきたのだ。
触れ合わせただけだったけれど、微かな塩味が唇に残った。きっと人に見られない魔法を使ったのだろう。辺りに誰もいなかったけれど、彼はどこまでも抜かりがない。
抜かりがないけれど、耳がほのかに赤く染まっているのが青灰色の髪の隙間から見えた。
「内緒ね」
滝の音に紛れることなく、その一言ははっきりと聞こえた。それで話はおしまい、というように彼は歩き始める。
もう誰にも今夜のことは話せなくなってしまったな、とレノックスは思う。正確に言えば、誰に対して何が内緒なのかを彼は明示していないので、約束でも何でもなく、強制力のない一言だった。しかしながら、彼が口説き文句ともとれる純粋な好意を口にしたことも、モンステラがレノックスらしいと思った理由も、診療所で育てている植物がレノックスらしいと選ばれて彼が嬉しく思った事実も、全て誰にも明かさない予感がしている。
どうして彼が照れながら告げてくれた一連の顛末を、誰かに明かすことが出来るだろう。
ふと、「診療所にいてくれている」と彼が表現したモンステラを瞼の裏に思い描いた。いてくれていると彼は言うが、丁寧に手入れされているから枯れずにそこにあるのだろう。何枚もの葉がみな等しく爽やかな緑色をしていて、触れば艶々とした手触りがする。フィガロの診療所のカーテンはいつも開いているから、きっと今日も、葉に月光を湛えているに違いない。
改めてその姿がらしいと言われた事実に、胸に小さな火が灯るような心地がした。
レノ、と焦れたように呼ぶ声がする。彼がくれたあたたかな気持ちを抱きながら、レノックスは彼を追って緑の中を進んだ。
Fin.