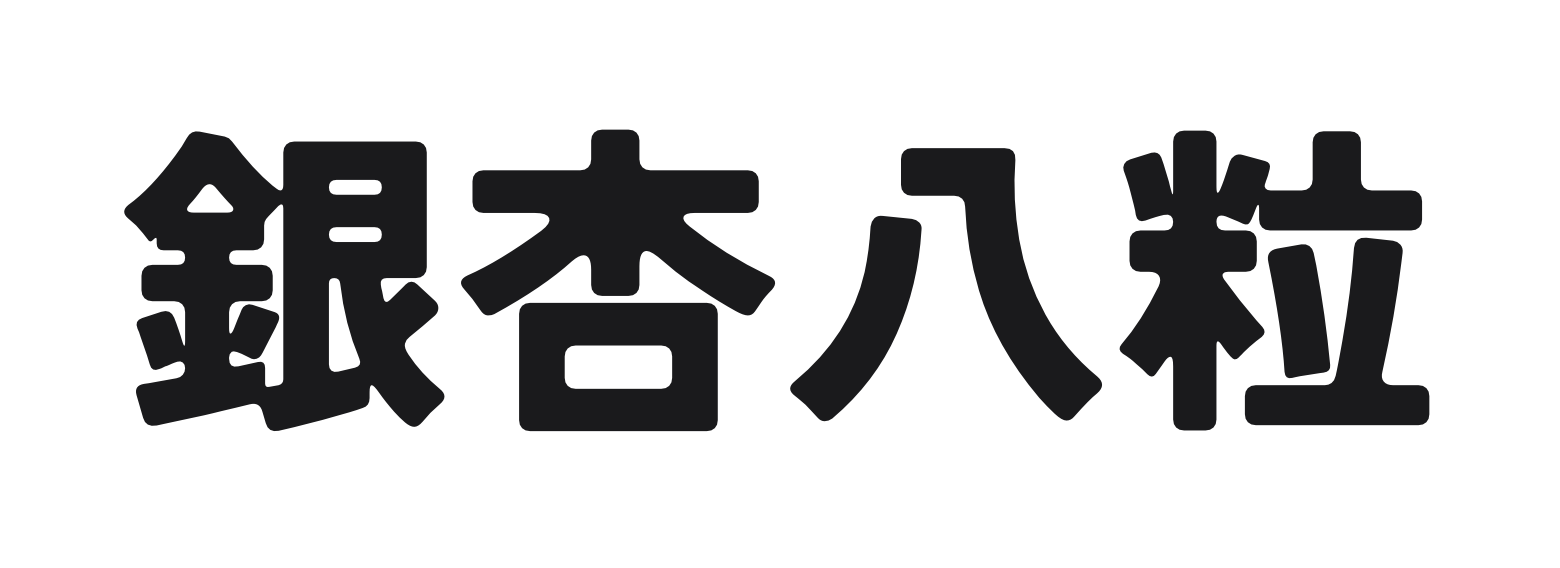少なくとも雲の街に行くときは、雨の日には傘を差して行くといい。
レノックスが南の国に移住するとき、フィガロが伝えたアドバイスの一つにこんなものがあった。当時のレノックスは律儀に頷いて聞いていたが、仕事を覚えたり新しい生活を始める中ですっぱりと忘れてしまって、小雨のなか一度傘を忘れて出かけたことがあった。というより、そもそも傘を買うことすら忘れていた。南の国で暮らし始めて、本当に最初の頃の話だ。
そもそも魔法使いというのは雪が降っても槍が降っても、自分の身を守る魔法を使えば普段着と変わらない軽装で過ごすことができる。雨が降った際も言わずもがなのことで、魔力が少ないレノックスでさえ旅の途中は着たローブに魔法をかける程度で過ごしていた。人間のふりをする必要があれば傘も差したが、南の国のおおらかさに限ってその必要はないだろう。それなのに、わざわざフィガロが傘を差すように言うのには、確実に雨よけ以外の理由があると察するべきだったのかもしれない。
いつものようにローブにフード姿で雲の街へ買い出しに向かってしまったレノックスは、行く先々で声をかけられるようになる。道ですれ違った住人の六割くらいからと、立ち寄った店の店員のほぼ全員に「傘がないが、大丈夫か」といったことを尋ねられた。弱い雨にも関わらずのことであった。
三人目くらいまでは律儀に「魔法使いなので大丈夫だ」と返していたが、だんだん「これから買うので大丈夫だ」と答えるようになった。傘を貸そうとしてきた住人もいて、すこし良心が痛みながら断った。そのころにやっと、フィガロのアドバイスを思い出し、その意味を理解することになった。つまるところ、傘は住民を安心させるわかりやすい目印なのだ。
その日は無事に傘を購入して、後日フィガロと会ったときにしっかりとからかわれた。南の国で起こったことはあっという間に伝播して、情報通のフィガロのもとに届く。その町医者曰く、大雨のときにローブ姿の大男の幽霊が街を徘徊する都市伝説が生まれそうになったが、無事に噂の火消しはできたので感謝してほしい、とのこと。
丁重に感謝して、それはそれとして南の国の住人の親切心が親切すぎて心配になると零した。レノックスが旅をしていたころ、大雨のなか立ちっぱなしならまだしも、小雨でしかも道行く人にそんな風に声をかける人間はいなかった。似たようなことは精霊相手にあったぐらいだ。しかしフィガロは、みんなただ親切心からやっているわけじゃないだろうね、と冷静に返した。
見覚えが特にない人物が街の中に入れば、まず声をかけてその人物像を探るのがこの国の風土だと彼は語った。確かに住民同士の馴染みが深ければかなり効果的な不審者に対する防衛策だと思うと同時、あることが気がかりになった。
「俺はいま、雲の街で不審者扱いになっているでしょうか……」
「大丈夫じゃない? それでも話しかけてきた全員としっかり会話したんだろう」
「しっかりと言っても、二言三言程度です」
「十分だよ。たぶんそれで人柄は伝わってる」
それはどんなものか、と聞けば、真面目だってこと、と返ってきた。
実際のところ、その通りだった。何年かもすれば職業柄人付き合いの少ない羊飼いにしては珍しいくらいに大勢から婿養子になることを嘱望される。が、そんな未来も知らない当時のレノックスはフィガロの言葉を若干疑いつつも、今後は同じようなことがないように彼の言いつけはしっかり守るに越したことはないと認識を改めた。
その後、村の言い伝えで肌に紋章を描かないと警戒されるよ、という彼のでたらめをわりと無防備に信じて実際に村に向かってしまうのだが、これはまた別の話だったりする。
ともかく、雨の日にフィガロの診療所を訪ねて、傘を持つレノックスの姿を見たフィガロが開口一番に「南の国にすっかり染まったね」と発言するのには、そういう背景も含めたからかいがあった。
小雨の湖畔で待ち合わせ
だらだらとした雨が二日間続いた。三日目の朝に目覚めたとき、それでも止まない雨を窓から眺めて、レノックスはフィガロの診療所を訪ねることにした。
「雨の日、診療所」。レノックスの小屋の玄関扉には、忘れないようにとフィガロが書いたメモが貼られている。旅路の途中、手紙のやり取りをしていたときには何度も見ていたので特にその文字自体に物珍しさはなかったが、直接彼がペンを取ってそれを書いているのを見るのは初めてで、なんだかもったいなく感じて捨てられなかったのだ。結局その内容のシンプルなメモを見ずとも予定を忘れることはなかったことに自分で小さく笑って、役割の済んだそれを日々の雑事が書かれたノートに挟んだ。
家に水魔の標本があるから見に来るかとフィガロに聞かれて、反射的にはいと答えたのが半月ほど前。取り留めのない会話をしていたのでその話題が出てきた流れはあまり思い出せないが、旅の中で見た砂浜に埋もれたガラスのようなあれは結局なんだったのか気になっている、と自分が発言したことがきっかけだったように思う。少し考え込んだフィガロが、海月か水魔かもしれないと検討をつけたのだ。
そういうわけで相手の提案を断るという選択肢はほぼなかったが、じゃあ雨の日に来なよ、という約束にも満たない適当な取り付けをしたメモを受け取って何日か経った後、レノックスはその提案を受けてよかったと感じるようになった。
基本、雨の日には困らされて憂鬱になる。いつも放牧している羊は雨が強ければ羊舎に入れなければならないし、他の仕事も雨の制限を受けてできなかったり、やりにくかったりする。同じようによほどの急患でもなければ雨の日に診療所を訪れることもないので、フィガロは雨の日を指定したのだろう。そのおかげで、うんざりする雨の日もいつもとは異なる何かがあるということで、多少待ち遠しくなった。
雨が降ったからといって、羊飼いの仕事を完全に止めるわけではない。諸々の仕事をこなし、外に出られない羊をなだめ、クーリールの頭を撫でて、やれることが買い出し以外に何もなくなった三日目、箒と傘を持ってレノックスは外へ出た。
雲の街での買い物を終えて、診療所の扉を叩いたのは午後のことだった。幸いなことに雨脚は本降りだった昨日よりもだいぶ弱まり、だいぶ弱まったおかげで、買い物をするうちに箒に乗るタイミングを逃し続けたレノックスは丘の上のフィガロの診療所まで歩いて行くことができた。
訪問客を知らせるベルを鳴らしながら扉を開けたフィガロが、わざとらしくレノックスの傘に目をやった。
「順調に南の国に染まってるね。あれ、歩きで来たの?」
「雲の街から歩きで、これは土産です。……その冗談の時効はまだですか?」
手土産を渡しながら傘の件は忘れてくれないかと聞き返したが、この医者は二千年生きているとは思えないくらいに物覚えがいいので、おそらく時効は来ないことは薄々感じている。冗談じゃなくて、からかっているんだよという悪びれのない医者の言葉を聞きつつ、傘を傘立てに差し込んだ。もはやため息をつく気力すら湧かない。
ちなみに傘立てには診療所の傘しかなかったので、雨の日にでも駆け込まなければならないような急患はいないようだった。
「なに飲む? ああ、この茶菓子なら合うハーブティーがあるね」
「それでお願いします」
せっかくならとフィガロが出すハーブティーが飲みたくなり、レノックスは土産の茶菓子として甘めのビスケットを選んでみた。じつはこれは彼の真似でもあった。フィガロはレノックスの小屋に訪ねてくるとき、コーヒーが飲みたいときにはコーヒーが飲みたいと主張しつつ手土産にはそれに合う茶菓子を、そしてワインが飲みたいときにはつまみかそもそもワイン一瓶を抱えてくる。
雲の街で甘党を根こそぎ虜にしているというこっくりとした甘みのあるビスケットを持っていけば、苦みが深い特製のハーブティーが出てくるのはほとんど決まったようなものだ。
いつも話すように診察室の椅子に座ろうとしたところ、フィガロから呼び止められる。
「標本を見るんだろう、先に二階に上がって適当に座ってて」
ポッシデオ、と呪文を残して彼は奥に引っ込んでいった。何に対して魔法を使ったのだろう、と辺りを見回したところで何も変化はなかった。改めて自分も含めて検分してみると、ズボンの裾の湿り気がなくなっていることに気付く。どうやら水気を飛ばす魔法をかけられたらしい。
「階段はまっすぐ行くとあるよ」
おそらくキッチンがある辺りから声が響いてきた。どうやらこの診療所には、高名な魔法使いの家にありがちな魔法を使わないと見つけることのできない部屋やたどり着くことのできない階段はないようだった。
南のお医者さん魔法使いを律儀にここでも守っている彼に「ありがとうございます」と声をかけて、レノックスはまだ見ぬ二階へと足を踏み入れることにした。
適当に座るところ、といってもその部屋には椅子は二脚しかなかったので、座る場所に困ることはなかった。椅子のうち一脚は窓際の机に沿って置かれていて、なおかつ白衣がかかっていたために、レノックスはもう一脚の椅子に座った。
そうっと周囲を見回してみる。誰しもが他人の家のつくりを面白く感じるように、レノックスにとってもフィガロの部屋は興味深いものに映った。
診療所の二階にあるフィガロの部屋は、診療所よりも物が少なくシンプルで、より家主の趣味を反映しているようだった。カーテンは薄いレースで、床は明るめの木目調のために部屋全体が光を反射して明るい印象を放つ。本棚の上半分にはラベルが見えるように並べられた薬品がきっちりと詰まっていて、下半分には分厚い医学書が仕舞われていた。
個性的な何かを使ったり飾ったりする趣味はないらしいが、微妙なところでルールがあったりなかったりするようなところが見えるのがフィガロらしかった。
たとえば医学書はぱっと取り出せればどんな置き方をしても構わないと思っているらしいこと。また、白衣は丁寧に椅子にかけられているがシワになることは確実なので、魔法でなんとかすればいいだろうという思惑が透けて見えること。
ほどほどに手を抜いているが、手抜かりがない。そんな部屋に対して何かしらのコメントをするのが難しくて、支度が済んだフィガロに「何見てた?」と聞かれて少し迷ったあと、「ラッセル湖を」と答えた。
フィガロの診療所はラッセル湖の湖畔にある。そのため、窓の向こうにはさざ波の立つ水面が絵画のように広がっていた。対岸の山々といくつかの民家さえ見えなければ、窓からのぞく景色は海だと見間違えるほど、湖は今日も豊かに水を湛えている。
「晴れれば今日は釣りができるかもね」とフィガロはハーブティーを啜る。何の感慨もなく飲んでいるので、もしや普通のハーブティーを淹れたのかと疑ってレノックスも一口飲んでみたが、しっかりだいぶ苦かった。滋養強壮に効きそうで何よりである。
そこでワンテンポ遅れて、彼の思い違いに気付いた。
「雨の方が釣れます」
「えっ、そうなの?」
驚く医者を横目に、テーブルに置かれたビスケットをつまむ。素で食べるとかなり甘く、どちらかといえば辛党のレノックスは胸やけがしてきそうな味だと感じるはずだったが、ハーブティーとうまい具合に中和されることとなり、ちょうどよいほのかな甘さになった。
味の調節がうまくいったと内心喜んでいたところで、「冗談じゃないよね?」と再度確認が入った。失敬な、という言葉が喉元まで出かかって、ギリギリのところで変換に成功した。
「俺はフィガロ先生ではないので」
「おまえもたまに冗談を言うわりに、結構言うね。……ああでもそうか。確かにそうかもしれない」
雨の日に魚が釣れる理由は色々とあるが、一番単純な理由として挙げられるのは魚がこちらを認識しづらくなるということだ。水面に打ち付けられた雨は表面だけでなく、水中も適度に濁らせる。濁りすぎると魚が餌さえわからなくなるので逆効果だが、今の時分の小雨ならば釣人を見えなくするだけに留まるだろう。
「正確に言うと、人によります。雨だと集中できなくて釣りにくいと言う人もいます」
「まあそうだろうね。でも試さないことにはなんとも言えないから、後で付き合ってよ」
レノックスはカップを傾けながら頷いた。釣果があれば保存食にできるので、願ったり叶ったりの提案だった。
それから二人は他愛のない会話を続けた。
レノックスが南の国に住むようになって、フィガロと会話をする機会が増えて気付いたことが一つある。彼はいつどんなときに会っても、まるで週に何度も顔を合わせる隣人みたいな気楽な話題を選んでくるのだ。より具体的に言うと、久しぶりに会った者たちがするような「最近の仕事は上手くいっているか」とか、「これからの季節はどう過ごしていくつもりなのか」とか、そういった形式ばった話題を振ることはあまりなかった。そんな取り留めのない雑談をする彼が、南の国の医者として親しみを持たれるのは当然のことだと妙に納得したものだ。
そしてレノックスも、そんな会話を心地よく思う一人だった。
「ここに標本はあったと思うんだけど」
そう案内された部屋は、物置の見本のような部屋だった。四方の壁にぴったりと棚が配置され、その中には大小さまざまな木箱が収められている。前方にある壁にだけは小さな窓があって、そこが唯一の光源だった。物置らしく一度箱の中身を取り出したままで蓋が開けっ放しのものもあったが、換気もまめにしているのだろう、埃は積もっていなかった。
魔法を使って探すのかと思いきや、フィガロはあっさりと左から二番目の棚の最下段から箱を取り出し、蓋を開け、そこからさらに小さな薄い箱を取り出した。持ってて、と差し出されたそれを受け取って、水魔の名称らしきものが書かれたラベルを指でなぞる。どうにも覚えられそうにもない、複雑な名前だった。
とりわけ価値ある標本だから置き場を把握していたというわけでもないらしく、それを隣から覗き込んだフィガロがひょいと気軽な動作で蓋を開けた。あまりにも軽い動作だったので、レノックスは心の準備もせずにその中にある標本の姿に目を奪われることになる。
「綺麗だよねえ」
「はい。……とても」
気の利いた言葉が出てこないのが、少し悔しかった。
海月のような水魔の標本は水中を生きたままの姿で、透明な樹脂に閉じ込められていた。青白く発光する頭部は艷やかに薄く輝きを放ち、触手である幾筋もの細い糸は絡まりもせずに優雅にたなびいている。
水魔にも色々種類があり、自力で発光するのはかなり珍しい種類に分類される。そうフィガロは説明しながら物置の中を進み、窓際に腕を組んでもたれ、目線で隣を指した。レノックスも側に移動すると、標本の輝きが単純な青みからよりいっそう複雑な表情へと変化する。曇り空の光に照らされた姿でさえこんなにも美しいのだから、晴れ間の水辺で泳ぐ姿はその何倍優雅なのだろうかという予想はつく。
旅で見たやつと同じだった? と隣から尋ねられて、以前見た砂浜での姿と頭部の透明な部分が似ているように思えると答えたところ、フィガロに笑われた。そんな大雑把なくくりだったらガラスとの判別もつかないだろうと返されて、確かにあれはただのガラスだったかもしれないと言ったら、また笑われた。
旅の中での記憶ははっきりとしないところもあるので、かつて見たものとは見当違いだったのかもしれないが、そのおかげでこの美しい標本を見ることができたと思うと、不思議な心地がする。
「水魔の泳ぐところに見とれて、溺死した例が後を絶たなかったところがあるから気をつけるんだよ」
フィガロ自身は標本の美しさに対してそこまでの興味がわかないらしく、まじまじと標本を見つめるレノックスを見ながら、思い出したように付け足した。海月は海に、水魔は主に湖や池にいる。そのため、海月の形を見たことのない南の国の人間がその形に興味を惹かれて事故を起こしてしまうことが多々あるのだという。
「気持ちはわかりますね。何か魅了する魔法でも使うんでしょうか」
「いや、この水魔自体にそんな力はないよ。魔物にも分類されない」
死んで標本になってもマナ石になっていないのがその証拠だった。さらに聞けば、あるのは正直者に恩恵を与える伝承くらいだという。習性もわかっていることが冬の寒い時期に眠ってしまうとのことくらいで、本当に珍しい希少種であることが伺えた。
自然と、ある種単純な疑問がレノックスに浮かぶ。
「どうしてこの標本を持っているんですか?」
「どうしてだと思う?」
人当たりのいい笑みで聞き返してきた。声のトーンは全く変わらないが、付き合いも積み重なると、こちらを試すように疑問形に疑問形を重ねるときのフィガロの思惑もぼんやりとわかるものだ。
――おそらくこの標本の出どころは、あまり言いたくないのだろう。だから他人に考えさせようとしている。
言えないなら言えないと言ってくれればいいものを、とはもちろん言わなかった。ひとまず先ほどフィガロが説明したこととつじつまを合わせて予想する。
「……湖畔の住人にこの水魔を注意するよう呼びかけるために、行商人から買ったのかと」
この水魔が原因となって事故が起こりがちならば、南のお医者さん魔法使いは周囲にその危険を呼びかけるだろう。それを聞いて彼はわずかに目を見開いてこちらを見た。意外だとでもいうように。
「思ったより俺のことちゃんとした南の国の医者だって思ってるね。あはは、嬉しいなあ」
「いまの予想って、そう取られるんですね」
「そうだね。チレッタとかなら『人間可愛さにラッセル湖に住んでいた水魔を全滅させた記念に作ったのね、悪趣味』とか言うと思うし」
「流石に嫌われすぎじゃないですか」
フィガロは苦笑した。そんな風には言っても、その歯に衣着せぬ物言いは北出身同士としてかなり長い付き合いから来る親しみのようなものであることは容易に想像がついたし、当人同士もよくわかっている様子だった。
おそらく彼が言いたいのは、チレッタを含めて今まで相対してきた魔法使いの中で、正確に言えば彼が北出身だとわかっている魔法使いの中で、そういう温厚な予想を立てる方が珍しいということだろう。案の定、このように言葉は続いた。
「レノが言ってくれたのは南の国らしい、優しさある理由だね。そういうことにしておくよ」
この話はおしまい、というように木箱に標本を収めながらフィガロは言う。
隠された本当の理由を聞くのは無駄になるのでやめた。何が本当なのか判断に迷うはぐらかし方をするのは彼の十八番だったし、標本の出どころを探っても仕方のないことで、おまけに言外に聞いてくるなと釘を刺されたので。
そのかわり、フィガロから木箱を受け取って元の場所に仕舞いながら、冗談めかして言った。
「それじゃあ、俺が先生からこの水魔の習性を教わった最初の一人なんですね」
「そういうことになるね」
「忘れないようにします。先生の優しさが無駄にならないように」
最後に水魔の名称が書かれたラベルを読んでからそうっと蓋を閉める。「別に名前なんて覚えなくても、レノはそもそも正直者だから大丈夫だよ」と背中に声をかけられたので振り返って彼を見ると、どこから取り出したのか釣り竿を渡された。
「先に準備してくる」
そう言って物置から出ていくフィガロは、機嫌がよさそうな足取りだった。改めて窓の外を眺めてみると、驚いたことに、今にも雨が上がりそうな空模様になっていた。
レノックスがフィガロの隣に歩幅一歩分の距離をおいて湖岸に腰を下ろし、釣り竿を垂らす時分には、結局雨が上がっていた。青空はそこまで見えないものの、重く厚い雲がやわらかく千切れて綿菓子になろうとしていて、光の柱が一つ、雲をつんざいて湖の水面を眩いばかりに照らしていた。
天使の梯子が現れたことに精霊が踊るようにざわめき、穏やかな風に背中を押される。むせかえるような雨上がりの湿った緑の匂いがする。白い鳥がぴんと翼を張って、風に乗って滑るように遠くまで飛んでいく。
こういう景色を見ると、彼が診療所をここに建てた理由がわかるような気がした。
「雨は止んだけど、湖は濁ったままだ。釣果はよさそうだね」
レノックスの釣り竿と同じ釣り竿を使っているなら、金属でできた疑似餌と釣り針だけの簡素な作りのはずなのに、ずいぶんと調子がいいことを言う。
フィガロと釣りをしたはじめの頃は、いつも魔法を使っていたと記憶している。その方が楽に早く釣れて効率がいいし、魚の種類もさまざまなものが釣れる。しかししばらく経つと、魔法を使わない釣りもするようになった。わざわざお互いに口にはしなかったが、相手と釣りをしていて、別にすぐに切り上げなくても疲れることはないと気がついたからだ。
にしても、とフィガロは続けた。
「前に診療所の扉を蹴破ったわりには、俺のこと優しいって買ってくれてるよね」
「さっきの標本の話ですか」
「そうそう」
よほど先ほどのような予想を立てられるのが珍しいうえに、気に入ったらしい。釣り竿を左右に振りつつ、心底不思議そうに問いかけてきた。
「俺が何かをしたら、あの予想が変わることはあったと思う?」
今後の参考にするから教えてよ、と投げかけられたのはなかなかに難しい質問だった。なにせ、診療所の扉を蹴破るくらいに腹が立ったり、絶対に諦めたくないと思っていたファウストのことを諦めたほうがいいんじゃないと言われてもなお、彼は南の医者として信頼のおける人物だと思ってしまっているので。
そう思う理由として、思い浮かぶことは当たり前のようにたくさんあった。診察室に子どもたちから贈られた折り紙をいつまでも貼っていること。診療所が人間でも使えるように変に魔法で弄っていないこと。長く生きた経験を使うだけでなく、新しく分厚い医学書に載っている知識も学んで活かしていること。
今日診療所で見てきたものと結びつけていろいろ考えるうちに、ふと朝一番に見た彼の筆跡が頭に浮かんだ。旅の途中、手紙で連絡を取り合っていたころの変わらない筆跡と文面も。旅を続けるなかで何千回と言われ続けた言葉が、そこにはなかったことを思い出すと同時に、気がついたら口をついて言葉にしていた。レノックスにとっては、かつて大切なことだったからだ。
「昔、フィガロ先生からもらった手紙に」
「うん」
「ファウスト様のことを『忘れてしまえ』と書かれたことがあったら、きっとさっきの答えとは違うことを言っていたと思います」
「……書いたことなかったっけ」
そんなこと気にしたこともなかったという様子の相手に、レノックスは頷いた。もし書かれていたとしたら、そもそもそんな考えを持ちつつ実際に忘れさせることができる大魔法使いを相手に、迂闊に会いに行かない。
「それ、誰かに言われたの?」
「いろいろな人から、です」
人間にも言われたし、魔法使いにも言われたし、精霊にも言われた。二百年過ぎたあたりからならまだしも、旅の最初のあたりは本当に多かった。たいていこのように言われるものだ。過ぎたものを悔やんでも仕方がない、失ったものを嘆いてもしょうがない、辛いなら忘れてしまえ。
家族や友人や恋人と離別した者にかけられる決まり文句のようなものだったので、そのように言ってくる相手のこちらを思いやる気持ちもわかっていた。そのため黙って受け流したり、ときにはありがとう、忘れるわけにはいかないのだと返したりすることもあった。
そういった日々を繰り返すうちは何も感じていないように思っていたが、レイタ山脈の中で羊の群れを眺めているうち、自分がどうしようもなく疲れていたことを知った。フィガロとの連絡が途切れなかったのも、その言葉が文面になかったのも理由のひとつのように思えた。
そのことをぽつぽつと喋ると、彼は神妙に頷いた。
「失くしたことが辛いから全部丸ごと忘れてしまえってさ」
「はい」
「嬉しかったりした瞬間があったはずの、失くしたものに対して失礼だよね」
行き場のないやるせなさが腑に落ちた思いがして、レノックスはフィガロを見た。神妙に頷いたあたりから半分予想できていたことだったが、――彼はにまにまとした笑みを浮かべていた。
「ねえ、いまの俺の発言、すっごくいい人みたいじゃなかった?」
「……そうですね。でも、そうすぐ茶化すのは……」
うわー、こんな話ばっかり聞いていたいなあ。隣から上がるそんな声を聞いているとかなり真面目に話していた自分がちょっと恥ずかしくなる。だが、実際に彼の言葉は的を射ていて、心のなかに清々しい風が吹いたような心地がするのも本当だった。
南の国の日々はこんな風に、四百年の旅の中では気が付かなかったものに気付かせてくれる。それがきっと、直接的なのか間接的なのかはわからないけれど、ファウストに出会うことにだってつながっていると信じられる。だから今だって、定住を勧めてくれた彼には感謝をしている。たぶん、それが無意識にも南の国らしいという標本の予想につながったのだ。
ざくっと湖岸の砂利に釣り竿を突き刺して、彼は立ち上がって思いっきり伸びをした。それと同時に身体を攫うような強い風が吹いて、肩にかけた白衣が飛んでいく。水に浸る直前、魔法にかかったそれはふわりと持ち主のもとに返ってくる。
「まあ、俺はたくさんのものを忘れてきたから言えたことじゃないんだけど」
白衣を肩にかけつつなんでもないように呟かれた一言が、レノックスの耳に残った。風に紛れるように呟かれたのだから流すべきだったのかもしれないが、その中に滲んだ寂しさを少しでも拭ってやりたくなった。
たった今、彼の言葉で気持ちが軽くなったから。
「それでも、そういう気遣いに俺は助けられましたよ」
返事が返ってくるとは思っていなかったのだろう、ちょっと驚いた気配がしたあと、座る自分の肩を叩いてきた。顔を見なくても仕草でわかる。嬉しそうだった。
「ねえ、気分がいいからあそこで釣りをしない?」
あそこ、と彼が指さしたのは雲の間から光が差し込んだ天使の梯子のたもと、ちょうどスポットライトで照らされたようになっているところだった。まさしく気分がよくないと行けないような、舞台の登場人物になれるかのような明るい場所に笑って、「いいですよ」と返す。
「魚がいるかはわからないけど本当にいい?」
「行かないことにはわかりません。行ってみましょう」
どうせ彼との釣りは釣れても釣れなくてもどっちでもいい。その時間が楽しめるから。そう思ったところで、地面に突き刺したままのフィガロの竿が引いていることに気がついて一悶着が起こる。
雨上がりに釣りをしたのがよかったのか、天使の梯子のもとで釣りをしたのがよかったのか、それとも南の精霊の機嫌がよかったのか。真相は定かではないが、この日の釣果はすこぶるよく、しばらくレノックスは保存食として調理した魚を食べるたびに、機嫌がよさそうなフィガロの表情を思い出すことになったらしい。
Fin.