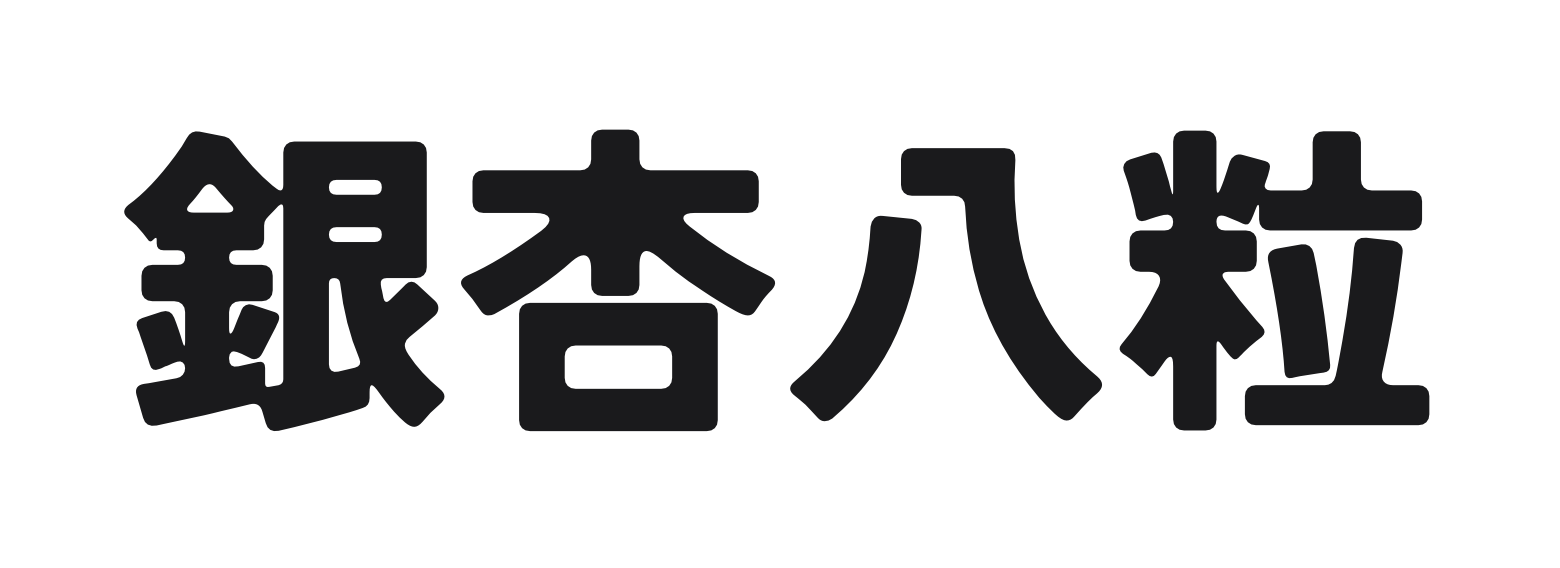「俺と初めてキスしたとき、なんて思った?」
この部屋の主よりもよほど主らしい態度でソファに仰向けに寝そべるフィガロが、何の脈絡もなくぽつりと呟いた。他愛ない雑談の延長、視線をよこして確認するまでもないといった声音で問いかけてくるが、レノックスは困ってしまう。彼はときどき、どう返事をしたらよいか迷うような問いかけをしてくる。今日のそれは一等答えにくい質問だった。
正直に言うか、嘘をつかない程度に当たり障りなく言うか。レノックスは逡巡したうえで、正直に言うことを選択した。
「思ったより不快じゃないな、と」
ワンテンポ遅れて笑い声がソファから聞こえてきた。
どうやら正解の方を答えることができたらしい。彼は「俺もだよ」と笑いながら起き上がり、隣を指さす。どうやら晩酌を所望しているようなので、仕事道具を磨く手を止めて、大人しくそこに腰掛けることにした。
初めから鈍感
席に着くと、フィガロは表情に笑みを残したまま、自身の手土産を魔法で開封し始めていた。あっちの村で用事があったからついでに来たとか、誰それの往診の帰りでちょっと休みたいから休ませてくれないかとか、何かにつけて小屋の玄関の扉を叩く医者はたいてい律儀に手土産を持ってくる。今日持ってきたのは見覚えのある包装を見るに、おそらく南の国のロースハムと赤ワインだろう。よく彼の患者から差し入れされているものだ。
同時に棚から皿とグラスとマスタードの瓶が浮かんできて、行儀よくテーブルに並びながら盛り付けがなされる。ちなみに彼はもうとっくに小屋にある食器類や調味料の定位置は把握している。唯一把握されていない、最近おすそわけでもらったソーセージと水を鍋に入れて鍋敷きとともにテーブルに置けば、ポッシデオの声と共にぐらぐらとすぐに沸騰し始めた。魔法を使おうと思い立って準備しても、彼の魔法を使うスピードには遠く及ばない。
「何分?」
「弱火で三分が美味しいらしいです」
頷き、フィガロがグラスを指先で持った。目を合わせて乾杯しないと七年間いいセックスができなくなるらしいよ、という冗談だか反応に困る言い伝えを彼に言及させないために(目を合わせなかったときに一度言われた)、グラスを軽く持ち上げて彼の瞳を見ながら乾杯する。
まだにやにやしているのを見て、ついさっき聞かれた質問を思い出した。いろいろと久しい付き合いになったが、今晩の肴は初めてキスをしたときの話題で確定らしい。
「おまえからやってきたくせに、初めてのキスの感想が不快じゃなかったとかいい度胸じゃない?」
「あれはほぼ事故だったと思います」
紛うことなき事実だったので、レノックスは淀みなく答えた。
久しい付き合いになる前のころ、具体的には、たまに晩酌はするけれども間違っても隣には座らない程度の仲のころ。その時分は二人とも今より幾分か慎重に距離を取ってそれを保ち、互いに対する理解を深めようとしていた。
フィガロはレノックスを実直な羊飼いとして信頼を置くようになり、レノックスはフィガロをいざというときには頼りになる医者として信頼を置くようになった。互いの職業に敬意を払っていたし、互いにどうしようもない考え方の違いが存在することも理解するようになった。
そんな矢先に事故が起こった。
きっかけは双方何だったかもう覚えていないが、今晩のように晩酌をしていたある日のこと。酔ったフィガロが誤ってワインボトルを倒しそうになって、魔法を使い忘れたレノックスが手を伸ばし、勢い余ってうっかり唇が触れてしまった。
幸い事故にありがちな怪我はなく、その確認をした後、そのまま晩酌は何事もなかったかのように続いてお開きになった。が、あとから思い返してみると発見がいくつかあった。レノックスが言ったように、そこまで不快にならない程度の仲だったのかとか。
魔法使いは心で魔法を使うので、幸か不幸か、二人ともが咄嗟に魔法を使っていなかったことが確固たる証拠になってしまっていた。
「レノがあんまりいけ好かないやつだったら」鍋の中のウインナーをフォークで転がしながらフィガロは言う。「石にしてたかもね」
「確かに、朝起きてなぜ俺は石になっていないのだろうとは一瞬思いました」
「えっ、俺うっかりでそんなことするやつだと思ってた?」
「……冗談には冗談で返そうかなと」
レノの冗談はわかりにくい、という相手に、先生の冗談もギリギリですよ、と返す。
できるかできないかの話で言うならば、フィガロは大抵の魔法使いを石にできるのだ。そしておそらくレノックスも、本気で嫌なことに対して魔法で咄嗟に防ぐぐらいはできる。いつも使うのを忘れているので、希望的観測かもしれないけれど。
できると思われるからこそ、二人とも無意識にしなかったことに好奇心が湧いた。相手と自分がどこまで許容できるのか、かなり興味を持って試したくなってしまっていた。それぞれお互いに直接聞きはせず、ゲームのようにそれとなく探り合う日々がしばらく続くようになった。
たとえば相手のソファに居座ってだらだら喋っても本気で嫌がるような顔をしないかとか、距離を詰めて隣に座っても違和感を持たず当たり前のように接するかとか、からかい半分で相手の手を取ってみたとき、どんな表情をするかとか、等々。
どちらも長く生きていたので当然のように気は長く、ずいぶん回りくどい方法で親しさを測っていたが、それを破ったのはフィガロだった。
横でぱりっと弾ける音がしたので隣を見ると、すでに彼がウインナーを食べ始めていた。
「ちょうどいい感じだ。やっぱり茹でた方がいいのかな」
「焼く派ですか?」
「そうだね、早いし」
レノックスも実際に取り出して食べてみると、張った皮がぱりっと破けたあと、しっかりと旨味ある肉汁が溢れてきた。調理方法が高温すぎるとこうも美味くはならない。もちろん焼いても食べられるが、肉汁を閉じ込めるためのタンパク質が壊れてしまうのだ、とむかし家具づくりを手伝った精肉店の店主が教えてくれたことを思い出す。
「本当は、低温で十分くらい茹でると一番いいそうです」
「なんでそっちを言ってくれなかったの?」
「料理に関しては、気が早いようだったので」
一瞬反論するような気配がしたが、直前にウインナーをいつも焼く理由が早いからだと言ったことを思い返したのだろう。図星だった相手はちょっと黙った後、「いいよ。次一緒に食べるときは十分くらいしっかり茹でよう」と約束に満たない宣言をする。
レノックスはそんな彼の様子と会話の流れで、思いつくことが一つあった。初めてのキスの話で今晩このままからかわれっぱなしというのも癪なので、流れを変えるつもりで口にする。
「――そういえば、素面で一番初めのキスは先生からだったじゃないですか」
隣から、それ訊くの? という無言の視線を感じたが、こちらとしてはこれくらいの圧力に屈するくらいではこの口の上手い男に切り返すことすらできない。視線を無視して言い切った。
「あのとき、なんて思ってたんですか?」
レノックスが答えたときのように、少しの沈黙が降りた。不意打ちに加えて答えをうやむやにすると不実になる質問だと悟ったようで、緩やかにフィガロの目が泳ぐ。
「……酔ってなくても、」
迷いながらも言い始めた言葉は途切れ、宙に浮かび、霧散した。彼の顔が若干赤いのは、アルコールだけのせいというわけではないだろう。
距離感を探り合う日々のなか、不意にまたキスをしてきたのはフィガロからだった。
ある昼下がり、喉が乾いたから何か一杯くれないかと彼は小屋に立ち寄った。飲んだらすぐに帰って仕事の邪魔はしないからと言った本人もそこそこ忙しそうだったので、レノックスはすぐ出せるコーヒーを一杯注いで、労う気持ちでシュガーをいくつか入れて手渡した。
ぐーっと一息に飲み干し、レノックスに礼を言って空になったマグカップを返して、そのまま箒で即座に飛ぶかと思った彼は、予想に反して途中でぴたりと足を止めた。どうしたのかと尋ねる前に、振り向きざまに一瞬で口付けされた。次の瞬間には彼が飛び立っていたほどの早業だった。さすがにレノックスも動揺したので、白衣の医者の後ろ姿が風景の一部となるまで、そのまま呆然と見送った。
確かにあの晩は互いに酔っていたから、距離感が少々可笑しくなっても別に気にならなかったのではないかという疑問もあった。遅かれ早かれ、さりげなく冗談を装って、もし過ちがあったとしても気心の知れた関係が壊れないようにいくつかの予防線を張ったうえで、確かめるようにもう一度口付けるだろうという予感があった。どこまで許されるのか試すうちに、それだけ興味が湧く間柄に二人はなってしまっていた。
レノックスはまず思ったよりも行動が早かったことに驚き、次いで自分の心のうちに嬉しさがあることにさらに驚くことになる。したくないことに対しては腰が重いフィガロが、わざわざ立ち止まってまでしてくれたことが嬉しいと感じるくらいには、だいぶ彼を知って親しくなったのだなと自覚した。奇妙なことに、親しさを測っているうちに、より親しくなってしまったようだった。
それでも次に顔を合わせたとき、彼が冗談にするなら別にそれでいいと思っていた。けれどもその申告はなく、戯れのようにキスをしたり、やりかえしたりするようになった。レノックスが嬉しさを感じたように、彼にも琴線に触れるなにかはあったのだろうということは容易に察せられた。
そんな状態が、今日まで続いている。
レノックスは辛抱強く「酔ってなくても」の続きを待ったが、フィガロは言いづらそうにしばらく考えたのち「野暮だからパスしていい?」と彼にしては素直に降参した。
「初めのキスの感想を訊くのもだいぶ野暮でしたが」
「わかったわかった、この話題は止そう」
投げやりでいつもより少し早口の締めの言葉を聞きながら、ワイングラスを傾ける。無理に聞き出そうという気はなかった。レノックスもフィガロがわざわざキスをしてくること自体が嬉しいと言う気はさらさらないので、ちょっとした秘密があるのはお互い様だ。
「仕切り直し」とフィガロが内緒話をするかのように手招きをしてきた。急に答える気にでもなったのかと顔を寄せれば、ごく自然な動作で手を添えられ、キスをされる。
顔を離したあと、彼の悪戯が成功したかのように上機嫌そうな表情を見て、レノックスはひとつ理解したことがあった。
きっと、彼は最初からキスがしたくて、質問をし始めたに違いない。