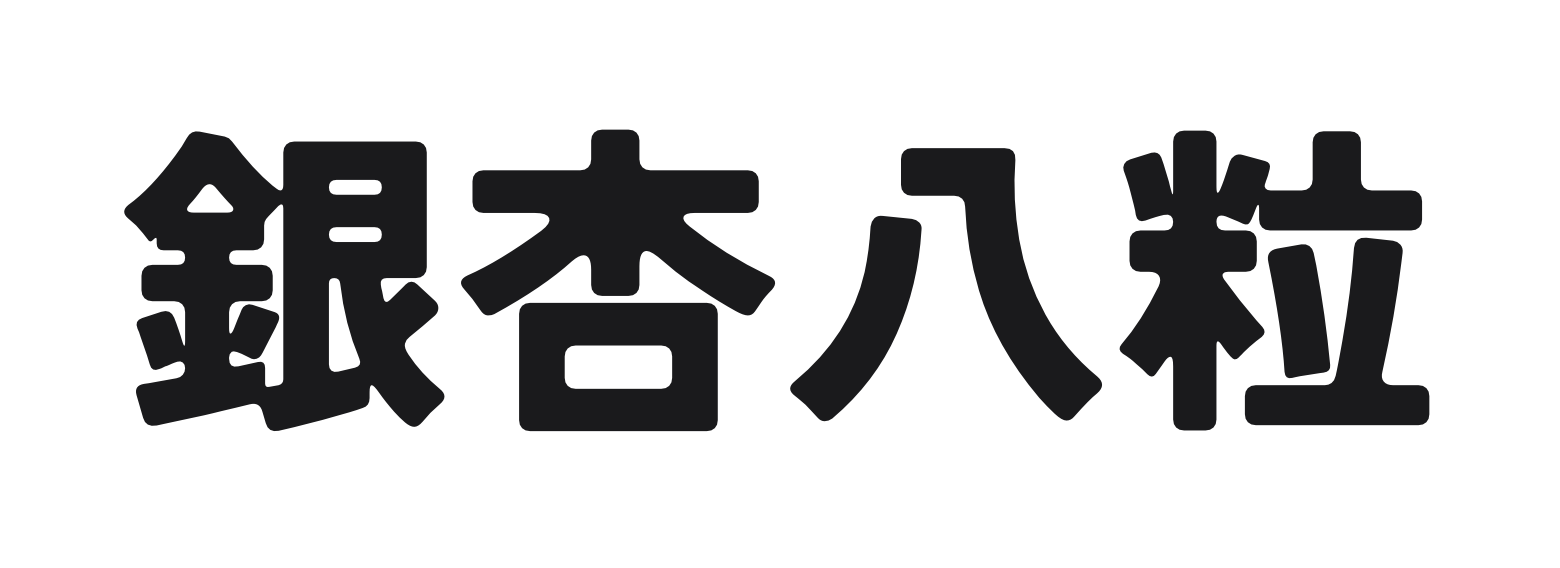ラスティカがチェンバロを弾き始めると、辺りは奇跡が起こり始める。
彼が鍵盤を叩いたその瞬間から、彼の音を待ち望んでいたかのように、世界はその旋律を彩る額縁になる。
鬱蒼とした夜の森の中でも、小鳥のさえずり、木々のざわめき、風に吹かれて飛んでいく木の葉の一つさえ、彼の音楽とぴったりと調和し心地よい空間を作り上げていく。
クロエにはこれがラスティカの魔法によるものなのか、本当に世界が彼にあわせて歌っているのか分からない。けれど、彼は無理やり自然を自分の指揮下に置かないだろう。魔法は使っていないような気がした。
ラスティカの音楽は世界に愛されている。
旋律が緩やかに終止線を迎える。月光に照らされながら穏やかに閉じていく音楽の中で、その様子を木陰で見ていたクロエはいいな、とひっそり呟いた。
音楽家の心得
ラスティカの花嫁を探す旅は、一人の弟子をとり、幾星霜と一人で過ごしてきた日々に比べてわずかばかりの年月を経た。世界中を旅する生活には二人とも慣れたもので、今日のような野営も珍しいことではない。
魔法使いが人間のふりをして泊まれる宿がないときもあれば、今日のように辺境の土地へ向かう途中、宿自体がないこともある。
そんなとき、魔法使いであることは本当に便利だ、とクロエは思う。ラスティカに教わらなければ一生知る由もなかっただろう。
人間が朝露をしのぎ、凍死しないように暖かい空気を留まらせるためのテントだって必要がなかった。ランチョンマットを大きくしたような敷布さえ一枚あれば、宿屋のベッドにさえ劣らない寝床が作れるのが魔法使いだった。
敷布に意味はあるのか、と聞いたことがある。うーん、と考えてラスティカは答えた。魔法は心で使うものだから、その想像の土台になるものがあるといいんだよ。
確かにその通りだった。一回うっかり汚した敷布を洗った日、試しに何もない原っぱで一晩越せるような環境を作ろうとしたが、いつもの何倍も時間がかかった。ちょっと焦れたラスティカが敷布を乾かそうとしたので、クロエは慌ててその敷布を乾かすことになった。
ふわふわおっとりしているようで、クロエの師匠は全ての魔法に通じる何かを的確に教えてくれる。その割に家事はいつまで経ってもできないので、旅の途中の選択やら何やらはクロエの仕事から外れることはなかったが。
宿もない、人もいない、そんな森で野営することになったらやることはほとんどないに等しい。
しかし二人は表現者だったので、紙とペン、そして楽器と裁縫箱があればどんな夜も楽しむことができた。クロエが新作の構想を練っているすぐそばで、ラスティカがチェンバロを弾く。それだけで何もない時間があっという間に過ぎていく。
特にラスティカのチェンバロをはらはらせずに聴けるのはこういうときだけだった。バイオリンやフルート、トランペットなどはタイミングさえ計れば人間の前でも魔法で出しても怪しまれない。本当は必要ないのだが、旅人のふりをするために持ち運んでいるトランクに入っていたんですよ、の体でなんとか誤魔化せる。
しかしチェンバロは別だった。まさかトランクに入る大きさではなかったし、魔法で瞬間的に出しても違和感しかない。そもそも高価な楽器で持ち運ぶ人間はいない。
それでもラスティカはその気分になりさえすればどこにいようと呼び出すのだが、そのたびにクロエはちょっと冷や冷やする。
クロエはラスティカが演奏する楽器の音色は何でも好きだったが、チェンバロは別格だった。
これはラスティカが最も得意なのがチェンバロだ、というだけではなかった。主旋律と副旋律がハーモニーを奏でるのはこの楽器だけで、それだけで音楽が豊かに聞こえる。
二人の旅が始まって少し経つまでは、寝る時間になってもチェンバロの演奏を止めないでほしいとねだったものだ。それに対するラスティカの返事は今でも覚えている。
「また明日の楽しみにしておいて」
思えばこの旅が夢のようで、無意識のうちに目が覚めたら終わってしまうと感じていたのかもしれない。今ではこの楽しい旅がずっと続けられるのを以前よりも心から信じられるようになったので、そういう意味でもっとと言うことはなくなっていた。
木を背もたれにして、ランプの明かりを頼りにデザインを練っていると、集中がふっと解けたときに耳に入るのはいつも優しい旋律だった。
古くから謂れある自然の中で演奏すると、精霊に嫌われた奏者だとどんなに高価な楽器で楽譜通りに奏でようにも滅茶苦茶に、精霊に好かれた奏者だと即興で作った曲でも自然と調和した音が響く。精霊の匙加減で音の反響の度合いが決められてしまうのだ。
今日入ったのはたまたまそんな森だったらしい。常より一層やわらかく情感あふれて響く音色は、クロエにも抱いたことのない思いを芽生えさせた。
世界と調和してみたい。もっと俗っぽく言えば、ラスティカのようにチェンバロを演奏してみたい。
願望がついぽろっと零れてしまった「いいな」は、ラスティカにも聞こえたらしい。ラスティカは、どんなにひっそり言われてもクロエの願いは敏く拾ってきた。それは単に音楽家としていい耳を持っていたからかもしれなかったし、たった一人の弟子を大事に思っていたからかもしれなかった。
「クロエも弾いてみるかい?」
なにも気負わず、ラスティカが言う。そんな様子にクロエは勢いよく首を横に振った。
「いや、いいよ、俺あんたみたいに弾けないし」
ラスティカの耳がいいことはもう何度も身に染みて分かっているので、実現するのにちょっと手間がかかる願いはあまり口にしないようにしている。
例えばあれが食べてみたい、と言うと大抵ラスティカがすぐに優先して叶えてくれる。クロエにはそれが本人の意志よりも優先されているようで引け目に感じてしまう。
言わないでおこう、と決意したことは何度もあったが、彼の隣にいるとなぜか今回のように自然と口に出してしまう。それが不思議でならなかった。
「誰も僕みたいに弾けないし、僕もクロエみたいに弾けないよ。ひとつとして同じ音楽はないからね」
「いやそうなんだけどさ、上手くない音楽を演奏しても誰も楽しくないし」
ラスティカはぱちりと目を瞬かせる。
「僕はクロエが奏でる音楽ならどんなものでも楽しめる自信があるよ」
「ありがたいけど、そういう意味じゃない……」
クロエはどっと脱力する。ラスティカのこういうところが好きで苦手だ。
全てを肯定して逃げ道を塞いでしまう。反論してもさすが相手は何百歳も年上で、のれんに腕押しの状態になってしまう。「この舞台の主人公はクロエだよ」といった風に、あっというまに表舞台の上に立たされてしまう。
そもそもこの森で初心者が弾いたらどうなるかがわからない。精霊が激昂して雨が降ったり蜂の群れが飛んでくるかもしれない。俯いてぐるぐると悪い方向に考えてしまう。ああ自分の悪い癖だ、と自覚するうちにすっかり萎縮してしまう。
「大丈夫」
夜の森に凛とした声が響いた。その声でクロエは思い出した。立たされた舞台で、実際に立ってみて、悪い結果になったことはあったかと。しばらく思い返してみても、思い当る節はなかった。
そっと顔を上げる。そこには大いなる厄災の光をやわらかに後ろから浴びた、いつものようにほほ笑むラスティカがいた。
神秘的な光景といつもの師匠のギャップになんだか気が抜けて、笑ってしまった。
「俺楽譜も読めないよ。ラスティカみたいにたくさんのメロディを覚えている訳じゃない」
「クロエは僕みたいに弾きたいんだね。とっても嬉しいよ。だから楽譜なしでも弾ける、チェンバロの秘密を教えてあげる」
差し出された手を自然に取って、クロエは立ち上がった。
月光を浴びて森の中で佇むチェンバロは、それだけで神聖な絵画そのものだった。この完璧な調和を崩したくないという思いが、またじわりと胸に滲んでくる心地がする。
チェンバロが弾けるようになる魔法でもかけてくれるのかな、という考えが一瞬脳裏によぎった。しかしラスティカはそんなことをしないだろう。クロエ自身の音楽を楽しむ人だから。
「座ったら、まず背筋を伸ばして」
そっと肩に手が置かれる。クロエは実家で何度もこのように手を置かれて精神的な圧力を感じたものだが、ラスティカのは違う。不安を払う手だ。ぴんとクロエの背筋が伸びる。
「いい感じ。そうしたら、これは秘密なんだけど、使うのは黒鍵だけにするんだ」
急に具体的な話になって、クロエはちょっとおどろいてラスティカを見る。彼はしい、と指を立てて「他の西の音楽家に怒られちゃうんだけどね」と悪戯っぽく言った。
「白鍵は音楽に深みを与えるもので、扱うのにはちょっと技術が必要なんだ。だから初めて演奏するときはただの飾りだと思えばいい。黒鍵はクロエの想いをよく汲みとってくれる」
つ、とラスティカがチェンバロを指さす。それを追ってクロエも見ると、さっきまでは得体の知れない神々しいものに感じた楽器が、なんだかちょっと親しみが持てる楽器になっていた。
「どんな音楽を奏でたいか、想像して。そうだな、この森を散歩するくらいのスピードで、それを演奏するイメージで」
どんな音楽を奏でたいかと言われて真っ先に出てくるのはラスティカが弾いてきた数々の曲だ。細かい旋律は覚えていないが、クロエの中にしっかりと留まるそれらは集まって、抽象的だがはっきりとしたイメージになる。
「大切なのはそれらしくなればいい、って心から信じること。細かいところは別にいいんだ。僕みたいに弾きたいのなら、ざっくり僕みたいに弾けばいい。……アドバイスは終わり。大丈夫、クロエなら弾けるよ」
最後の最後で難しいことを言う。それらしくなればいいと、ラスティカみたいに弾けばいい、が繋がらない。でも、世界一信用できる大丈夫を聞いたら、なんだかやってみたらできる気がした。それらしく。そっちの方が大事らしい。心に刻むことにする。
クロエは勇気をもってチェンバロの黒鍵を叩いた。
ポーン……と単音が静謐な森に響く。
このあとの続け方がわからなくて軽くパニックになるが、ラスティカは演奏するとき、単音を響かせるだけだっただろうか、と思い至った。
思い切って近い音ふたつを同時に叩く。
重厚な音が重なった瞬間、先の単音とあわせてそれはメロディーになった。旋律は音の連なりであることを、そのとき初めて実感を伴って理解した。
もっと奏でてみたい、きっとできる。そう思えた。
こんな音が響いたとき、このあとにちょっと高い音を出したラスティカの曲を聴いたことがある気がする。手を右側に寄せて音を鳴らす。
想像とは若干違うが、それらしいような感覚がする。
少しだけ待って、左側の黒鍵を波のようにまた再び鳴らしてみる。それからは頭の中のイメージを追いかけるようにして、次々と旋律が生み出されていった。
世界は新たな奏者の誕生を祝福し、歓迎した。
クロエが重い音を奏でれば風の流れはゆっくりになり、アクセントのように明るい音を響かせると踊るように軽やかに舞う。木々のざわめきもスピードを合わせたものになる――そう、散歩するくらいのスピードに。
クロエの音楽は技巧的にはなにも特別なものがない。二度と同じ音は響かないし、テンポも一定ではなく、それらしさを追いかけているので奏でる音楽は一所として同じイメージを持たないように聴こえる。
けれど、湛えられた情感の豊かさにははっと目を目を見張るものがある。心から楽しんいる者にしか奏でられない旋律の連なりは、まるで花束のようにラスティカに響いた。
曲が閉じていく。閉じ方もクロエにはなんとなくわかる。
ゆっくりと箒で空へ飛ぶように、高い音をのぼっていく。そして星の瞬きのように、ちかりと最も高い音二つを跳ねさせた。
何かを足したら、完璧になる。そう感じた。その瞬間、最後まで手を出さなかったラスティカが一音だけ、とても低い音を鳴らす。
曲に終止線が打たれた。
夜の森はしん、と静謐さを保って横たわっている。拍手喝采もアンコールもなかったが、奏者の演奏を称えた穏やかな風が一陣、吹き抜けていった。
その風を見送り、振り返ったラスティカが言う。
「素晴らしい演奏だったよ」
「ありがとう。俺もそう思う。……そう思えるようにしてくれたのは、ラスティカのおかげ」
追いかけるイメージが途切れなかったのは、彼がたくさんの曲をクロエに聞かせてくれていたからだった。
えへへ、とクロエがラスティカに笑いかける。
ラスティカはこの無垢な魂を見ていると、どうしようもなく心が満たされる心地がする。その想いを手のひらに載せて、クロエの赤い髪をやさしく撫でた。
その夜、二人はとても素敵な夢を見たという。
Fin.