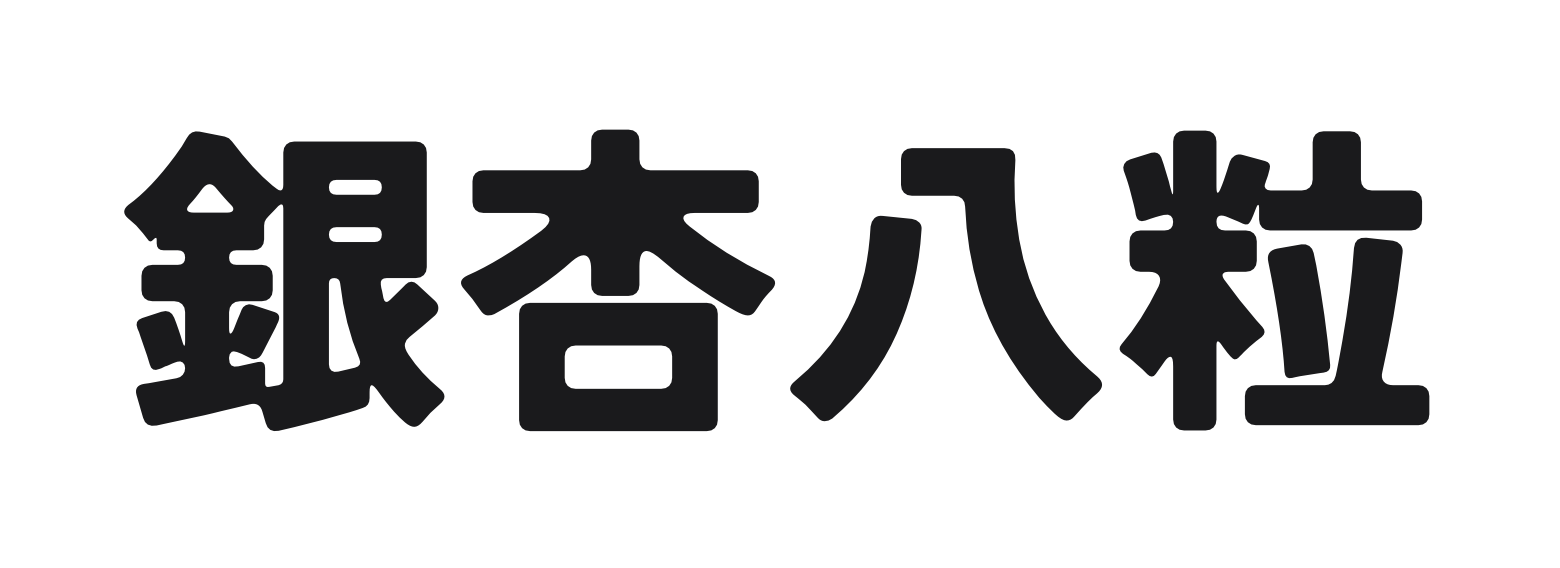一歩先の視界すらも危うい猛吹雪の夜の色の髪、敵の鮮血を浴び続けて染まったかのような真っ赤な瞳。この男の名前を聞いたら震えて眠れなんていうけれど、目の前に立たれたら何をすればいいのだろうか。死んだふりか、命乞いか。多分そんなものは通用しない。
「スプーンが凶器になることくらい知ってんだよ」
ネロが放ったスプーンを完璧に見切って銃の柄で防いだ男――ブラッドリー・ベインはそう言った。
鼻にある向こう傷からしてたいへん怖そう。現実逃避をして余裕のある他人事みたいな感想を頭で考えながら、ネロはどうして自分はこの瞬間も死んでいないのだろう、と不思議に思った。男の長銃を壊せるほどネロの魔法は強くない。
ひょっとするともうすでに撃たれて死んでいるのかもしれない。そう考えた方が逆に不思議ではない、そんな状況だった。うっかりした事故とはいえ、自分は盗賊団の頭領に、凶器を突き付けたのだから。
盗賊の心得
吐き気がするほど腹が減っているが、口の中はからからで歯が痛み、とてもじゃないが食欲はない。そんな行き倒れの典型みたいな症状を抱えて、ネロは路地裏の一角に座り込んでいた。
治安の悪すぎた家を町ごと飛び出して、行くあてもなく町を転々と移動する生活にもそろそろ終止符が打たれそうだった。
何のことはない。自分自身の死によって。
そもそも子供が北の国であてもなく一人で生きていこうなんて土台無理な話だったのだ。どの町でもありつける仕事はなく、路銀は減る一方。なんなら三日前に尽きた。食事も同じ分だけしていない。
なんとなく、上を見上げる。路地裏の空は、建築物やそれに吊るされた洗濯物で短冊状に切り取られた狭い空だ。それでもその先に目を凝らせば、抜けるような白昼の蒼穹が確かにあった。雲一つないその空の青さを見ていると、ここで死ぬのも悪くない、そんな風に思った。
二日前には名前も知らなかったこの町の路地裏は、存外死に場所にはいい場所だった。
生まれ故郷の路地裏のように娼婦や酔漢はたむろしておらず、怒鳴り声や喧しい声がない。ちょうど頭上に窓がないために、上から投げ捨てられる汚物桶の中身についての心配もいらない。中央通りから一本外れた路地裏かつ馬車も通らない狭い道だったので、馬糞や馬尿が散らばっていることもない。
もちろん何も辛いことがないというわけではない。日光が真上から差し込んでいるとはいえ、一晩かけて冷え込んだ石畳の冷たさは文字通り底冷えのものだったし、背を預けている民家の壁なんて氷の壁のよう。そしてなにより、雪の溶け残りが体の熱をゆっくり奪う。これらは自分の貧弱な魔法を貫通して、どんどん心身を凍てつかせていく。
しかし、いまのネロにとって、馬鹿みたいに寒くて辛いことなんて、どうでもいいことだった。
このまま路地に座り込んでいれば、北の寒さはシンプルかつ綺麗さっぱり命を奪う。石になるから穢される尊厳もない。
何もかもがうるさくて汚い故郷で一生を終えることが嫌になって飛び出して来たのだから、そこそこ静かで綺麗なここで死ぬというのは、とても魅力的な終わりに思えた。
だが北の国はどこに行ってもうんざりするほど厳しいのには変わりはない。いくら人気のない路地裏だろうと、目ざとく死にかけの子供から何かを巻き上げようとする奴は何人もいた。
なんにも持っていないのに。そう思ったが、追い剥ぎに届くような大声を出す気力も体力もなかったので、そこらに落ちていたカトラリーを魔法で操り追っ払うことにした。改めて意識して魔法を使うと、結局自分は魔法使いだろうが空腹をどうにかできないくらいに無力だと自覚させられて苛立ってくる。
その苛立ちも何かを感じることももうひたすらに嫌だったので、追い払うにはやりすぎな魔法を使ったような気もする。いつしか辺りは静かになった。
よかったと安堵の息を吐いたのも束の間、最後の最後で脅しが効かない男が現れた。あろうことか、脅してからそれに気付いた。本当についていないと、己の身の上を呪う気力すら起きなかった。
「スプーンが凶器になることくらい知ってんだよ」、そう言い放ってから意外にも何もしてこない男に、ネロは目線を逸らしてやけくそ気味に呟く。
「どっか行ってくれよ、穏やかに死にたいんだ」
本心だった。あのブラッドリー・ベインに歯向かって穏やかな死を望める可能性は皆無に近かったが、どうせ死ぬので見逃してほしかった。
が、当然それは許されないらしい。雪と一緒にカトラリーを蹴り付け遠ざけながら、ブラッドリーは言う。
「自分以外には大層穏やかじゃねえな。――ナイフよか注意は逸れるスプーンで殺しにかかってくるとはよ」
ネロは蹴とばされたカトラリーを目線で追った。それはもはや魔法で飛ばしても軽々避けられるくらいの距離に離されてしまった。ネロの脅しは不意打ちかつ至近距離じゃないと意味がない。
一分ほど前、ネロがブラッドリーに放ったカトラリーは三本。フォークとナイフ、それからスプーン。大抵の追い剥ぎは先端の尖ったフォークとナイフを気にして、無意識にスプーンは視界から外してもいいという判断を下す。
だから、もっとも死角から眼に突き付けやすいのはスプーンだとネロはわかっていた。
だが、子供の小手先の悪知恵は、本物の悪党にかかればあっさり看破された。
スプーンはいまも、ブラッドリーの銃の柄に突き刺さったままだ。勢いを付けすぎたので、魔法を使ってもネロはもうそれを操れない。またひとつ増えた己の無力さの象徴を見つめていると、どうして見切られたのかが気になった。
聞いてみるほど胆力はなかったのだが、知らないうちに口から零れていたらしい。それを丁寧に拾ったブラッドリーは、簡潔にあっさりと告げた。
「お前、綺麗すぎ。ただのガキにしては三発ぐらい殴られてねえと不自然」
北の国の路地裏はたいてい、暴力沙汰など日常茶飯事の無法地帯である。
幾ら人目につかないところであろうとも、普通無気力に座り込んでいれば追い剝ぎやら何かしらにぼこぼこにされ、持っているものを取り上げられるだけ取り上げられる。奴らは取り上げた相手の生死なんかを構っちゃいない。そのあと何日後かはわからないがやってくる清掃人は、道端にある死体をそこらに散らばるゴミクズと一緒に焼却炉へ投げ込むだろう。
これは石だろうがタンパク質の塊だろうが、同じオチを辿る。いや、もしかしたらマナ石は誰かの胃の腑に投げ込まれるのかもしれない。このあとのネロのように。
そんな場所で、やつれているとはいえ殴られた形跡さえもなく座っている子供を警戒するのも当たり前の話だった。
はは、とネロは咳とも声ともつかない音を零す。水も飲めずに久々に喋った喉は、先ほどから乾ききっている。
「盗賊団の頭でも、てめえを殺そうとした奴の話、意外と聞いてくれるんだな」
「もう俺を殺す気概もないだろ」
「確かに」
返事と同時にこほ、と咳をする。ネロは段々、この男の銃でぱっと殺されるのも悪くはないかなと思うようになっていた。
頭を狙ってくれさえすれば苦痛は寒さで凍えてじわじわ死ぬよりもずっと短いだろうし、きっと身体は綺麗さっぱり食べられる。自分が死んだ後にその抜け殻がどう扱われようが知ったこっちゃないが、どこの馬の骨とも知らない、それこそ自分が追い払った輩なんかに食べられるのはちょっと癪に障る。それよりかはずっとマシ。
そんな考えを中断させるように、ブラッドリーは銃を右肩に担いだまましゃがんだ。そのままネロの瞳を探るように覗き込んでくる。
「なあ、どうして死にたいんだお前」
北の国で武名を上げる盗賊団の頭領は、誰に対しても本当によく話を聞いてくる男らしい。改めてそう思いながら、ネロは素直に答えた。
「疲れたんだ。……居場所を懸けて戦い続けることが」
兄弟姉妹らしい人物たちが入れ替わり立ち替わり入り浸っている場所は家だったかもしれないが、間違いなく居場所ではなかった。生まれた場所が居場所ではないのなら、北の国は腕ずくで居場所を勝ち取らなければならない、そういう国だった。
戦い続けることがいやになったのは、誰かの居場所を奪うからいやだったとか、そんな優しさからくる理由では決してなかった。
本当に、ただ、疲れたのだ。
ふと視界の端で、ブラッドリーが口の端を上げた気配がした。ネロは胡乱に視線を上げる。初めてそこで、まともに紅い瞳とかち合った。
――きれいだな。
そのときふっと、そう思った。ブラッドリーの鮮やかな色をした瞳を敵の血を大量に浴びたからそうなったと称した誰かさんは、たぶんブラッドリー本人と相対したことがない。
意味もなく怒鳴り立てる酔っ払いの頬の色、路上に散らばったゴミから覗く腐った野菜の色、姉らしき人物が唇に引いていた安っぽい口紅の色。ネロが見てきた薄汚れた世界のどんな赤色よりも、彼の瞳は一片の濁りもない赤だった。
敵の血を浴びてできる色ではない。きっと、彼自身の燃えるようでいて真っすぐな性格通りの血の赤さを反映している。死にかけの自分にさえも、こんなにも透き通って見える。
ほんの少しばかり恍惚とした気持ちになって、柄にもないことを考えたせいか、ブラッドリーの次の言葉に反応するのが一拍遅れた。
「じゃあ俺と来い」
「……は、」
「俺がお人好しだからじゃねえ、ちょうど魔法使いが必要だった。だから俺と来いよ、居場所を与えてやる」
ぽかんとした表情になった目の前の子供を見ながら、ブラッドリーは笑う。
この子供の存在を知ったのは偶然だった。
死の盗賊団はたまたまこの町に留まることになった。次の作戦で魔法使いがもう一人いれば成功する見込みがあるので探していたのもある。そんな折、路地裏にいた子供がまさか魔法使いだったなんて、あのまま衰弱して死んだらマナ石を頂戴しようか、ならず者のそんな会話を盗み聞いた仲間がいた。
なんでその場で話をつけなかったと仲間を小突きつつ、総出で探し回ること二時間。路地裏でやつれているわりに殴られた形跡のない子供は、みごと盗賊団の頭に発見された。
初手で攻撃されるのは予想外だったが、つくづく運がいい子供だ。見つけたのが自分じゃなければ八割方の仲間がカウンターで殺していただろう。
ブラッドリーがそうしなかったのは、普通に魔法使いがいないと作戦がご破算になるのがわかっていたことがあったから。
そしてあえてもうひとつ理由をあげるとするなら、矜持もそれを最期まで守る気骨もある魔法使いが野垂れ死ぬのは勿体ない、そう思ったからだ。
幾度となく死線を越えてきて、ブラッドリーは死の間際に追い詰められた生き物の姿をたくさん見てきた。別に生きるために矜持を捨てて命乞いしようが諦めてされるがままになろうがそれも一つの選択で、貴賤はないと思っている。
しかし、最期までなにかを守ろうと一本筋の通った行動ができる奴が稀なのは事実だ。
ひとは瞳を宝石に例えるが、血の通った瞳が光を反射させる様子は宝石の輝きと同じかそれ以上に面白い。「先日盗み出した指輪にはまっていたシトリンのような」瞳は、攻撃してきた子供を拾うなんて馬鹿なんじゃないかという疑心と、困惑と、生存本能から来るほんの少しの期待で揺らぐ光を複雑に映している。
ゼロのまま終わるか、ゼロからの始まりを選ぶか。ブラッドリーにしてみればどちらを選ぶかなんてわかりきったも同然のことだったが、今まさに死にかけの子供にとってはそうではないらしい。なかなか決心がつかないようだった。
元々の性格なのか環境がそうさせたのかはわからないが、生きることも諦めてしまっては困る。駄目押しの一言を告げる。
「あーもうめんどくせえなてめえ。俺が来いって言ってる。悪いようにしねえから来ると言え」
選択肢なんかないことにようやっと気付き、瞳の中の均衡が崩れる。微かに開いた口が、掠れた言葉を紡ぐ。
「……よろしくおねがい、します」
敬語に直してきた彼は、存外したたからしい。
悪くない。そう思いながら、ブラッドリーは彼の手を引っ張り上げた。
Fin.