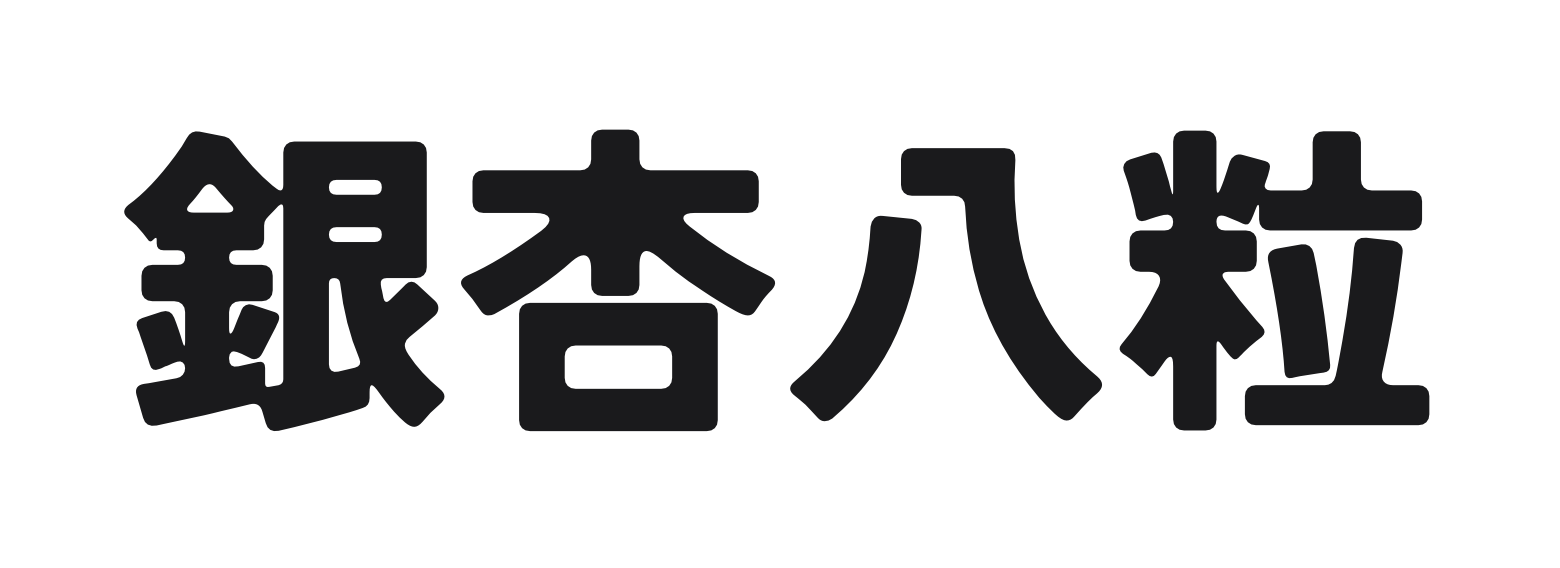完璧に固定された厄災の骸のすぐそばで、東の魔法使いが輪になって集まっていた。
指し示めすわけでもなく自然に集まった四人は、誰も怪我らしい怪我をせずに完全な勝利を打ち立てたにも関わらず、顔を見合わせているだけだった。
ありがとう、すごかった、よくやった、さすがだった――そういった相手に伝えたい感情が複雑に混じり合うせいで、どれから言っていいのか全員が分からなかったのだ。驚くべきことに、はっきりと自己主張するシノでさえそうだった。この巨大な感情を表す言葉はもはやなく、他のどんな言葉を掛けても薄っぺらくなってしまうような気がした。
この場にいるのは全員、慎重すぎるほどに言葉を選びがちな、東の魔法使いだった。
それでも瞳は言葉よりも雄弁だった。自身が感じているものと他の三人が感じているものが同じように瞳に宿っているのは、全員がわかっていた。
こういうとき、どうすればいいかを知っているのはファウストとネロだった。ファウストは革命軍時代、ネロは盗賊団時代に何度もやったそれを、無言のうちに行う。
具体的に言うと、手のひらを胸の高さまで持ち上げた。もちろん両方。
保護者組二人が無言でそうするのを不思議そうに眺めていたシノとヒースクリフだったが、やがて合点がいった様子で同じようにする。
全員が同じようにした一拍後、ぱん、と軽やかなハイタッチが四つ重なった音が森に鳴り渡る。
その一呼吸後、森に高らかな笑い声が響いた。その音に驚いて、鳥が木から白む空に飛び立っていく。
世界で一番早い東の国の夜明けが、すぐそこまで迫っていた。
Fin.