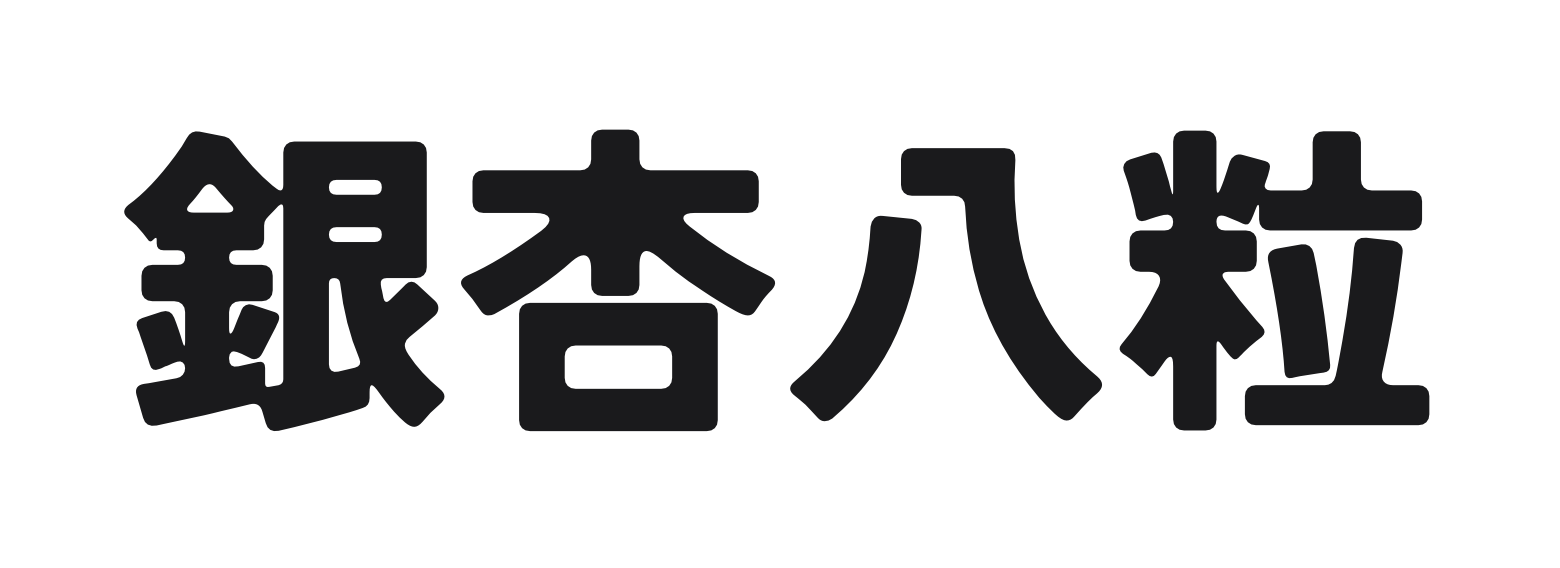状況は芳しくないが、各々が最善を尽くした。
ネロは自身の箒の上に仁王立ちし、眼下に存在する厄災を眺める。森に延焼しないように囮をするのは空中にすると決めたので、いまいるのは厄災の射程ギリギリだと思われる高度の上空だった。今一度、仲間たちの様子を確認する。
シノは肉眼で確認できない。必殺の一撃を放つのに最適な場所にいると思われる。「攻撃する直前までは地上から離れないでくれ」と頼んだネロの言葉に素直に頷いていたので、どこかの木陰に潜んでいるのだろう。
シノは森番を長年務めてきただけあって、元盗賊の目からしても驚くほど気配がなかった。普通、ネロがいまいるほど高いところにいけば、どんなに隠れようとしていても気付くものがある。隠しきれないナイフや武器のきらめきなんかがその典型だ。
実際、死の盗賊団が壊滅させた別の盗賊団の敗北原因がそれだったこともある。しかもシノは大鎌を持っているはずで、その光が反射していないのは、何かしらの工夫をしている証拠だった。
ネロは舌を巻く。こういうのは知っていないと出来ないし、いつもやっていないと土壇場で出来ないものだ。彼のマナエリアは森だったことも思い出し、もしかしたらこの場で一番全力の実力が出せるのはシノかもしれない、とも思った。
ファウストとヒースクリフは共に箒に乗って、攻撃の射程外だと思われる、厄災と同程度の高度にいた。こちらはネロも目を凝らせば見える。
ヒースクリフは集中して森の精霊のざわめきを鎮めている。先ほども周囲の自然を自身の額縁とさせるほどの静謐さを纏っていたので、精霊を馴らすことも難なくできるだろう。
おそらくこの森の精霊はヒースクリフを気に入ったのではないかと思う。一般的に精霊は魔力量の多い魔法使いに率先して従うが、たまに精霊の気まぐれともいうべき現象が起こることがある。
木の葉の擦れる音さえも遠ざかったような先ほどの静寂は、ヒースクリフの力もあるだろうが、精霊が嬉々として演出したような気もする。基本的に森は静謐さを好む傾向がある。それに合致したのだろう、いまも魔法任せに無理に馴らしているというのに、上空に吹く風も穏やかなままだった。
不思議の力さえも従えるヒースクリフの力に少しだけ空恐ろしい感覚がするが、将来領主たる器とはそういうものなのだろう。ネロは納得してファウストに視線を移した。
ファウストはこちらをじっと静かに見つめている。へまをしないか見張っているようでいてちょっと照れるが、実際はそうではないことをネロはうすうす察していた。
自分に囮を任せるときに肩口に触れた、微かに震えた手を思い出す。
彼は指揮官に乗り気ではない。乗り気ではない癖して、その役割を果たせるのが自分しかいなくて時間の余裕もないとき、その役割を受けることをしてしまう。そしてそれに付随する責任も、しっかり果たそうとする。
ファウストは自身への関心が低い割に周囲をよく見ているタイプで、大切な他者が傷付くことよりも自分が傷付くことを優先する判断が恐ろしく早い。視野が広いので、そこまで責任を感じるかと思うようなところまで責任を負おうとする。
ネロが思うに、指揮を執るのに乗り気ではない理由は、責任が果たせないと考えるからだろうと感じる。分かりやすい表面に出てくる性格は捻くれているが、水面下の性根は愚直であるのだ。どことなく中央の気質に似通ったそれが不思議でならないが、ともかくいま彼が感じている責任が重要だった。
おそらく彼はネロが大怪我をしようものなら、囮という役割を任せた責任を果たそうとするだろう。具体的に何をするのかはよくわからないが、極めてよくないものだということはわかる。
ネロを中心にシノとヒースクリフにも何重もの火除けや幸運のまじないをかけ、それでも口惜しそうにしていたファウスト。祝福と呪詛は表裏一体でどちらも扱えるが、やはり祝福は呪詛よりも多少効果が落ちてしまうと悔しそうに零すほど、こちらが驚くほどに仲間想いで責任感の強い彼の持つ重いものが少しでもなくなればいい、とネロは思う。
そのために、いまのネロに出来ることは、余裕たっぷりに囮役をすることだ。
若干の論理の飛躍を自覚するが、ファウストやヒースクリフほど理路整然に考えを組み立てられるタイプでもないので、直感でいかせてもらう。
自分が余裕を見せれば、多少なりともファウストが安心する自信があった。一番傷付きやすいのはもちろん囮役だからだ。ファウストだけではなく、ヒースクリフやシノも安心するだろう。やはりこれが最適解だ。
さて、「余裕を見せる」とはどんな風にやるか。ネロは両手を組んで前に伸ばしながら考える。ただ逃げ回るだけじゃいけない。怪我をしてもいけない。そうなるとできることは限られてくる。
ふと、盗賊団時代に箒を使って度胸試しをしていたことを思い出す。箒に難なく仁王立ちできるのもそのおかげでもある。長らくやる機会もなかったが、無意識に仁王立ちしているあたり、身体が覚えているのだろう。
ネロは口の端を上げた。
年下のファウストが苦手な立ち回りでも責任をしっかり果たそうとしているのだ。何だかんだこの場で一番年上の自分が、ここで出し惜しみしてどうする、と心の中で軽く喝を入れる。
風が穏やかに吹き、髪を緩やかになびかせた。
「踊るか」
彼のために。子供たちのために。気負いなく自然と、そんな言葉が口から洩れた。
ファウストはネロが立つ上空を見上げていた。隣ではヒースクリフが森の精霊を宥めていて、そのおかげで風は穏やかに吹き続けている。流石は自慢の生徒で、特にこれといって問題はなく、あと少ししたら完全に馴らすことができるだろう。
その穏やかな森の様子に反してファウストは、今晩の敵に対して囮役を立てなければならない己の力不足に吐き気がしそうだった。シノが例えたように、炎が凝縮した敵の攻撃が当たれば火だるまになることは確実である。
それから連想されるのは、自らの四百年前の火刑であった。
もちろん、ネロにかけたまじないは当時の自分の火炙りの炎など弾き返すくらいには頑丈なものであるし、彼も自分でそうやすやすと破れることのない防御魔法を張るだろう。
しかし、どうしても、思い出さずにはいられない。自らの身体を舐める煌々と光る炎、その想像もつかなかったほどに高い温度を肌で感じ、どっと背筋に伝う冷や汗。それから遅れてやってくる、神経を直接刺されるような痛み。
そう、炎に焼かれるのは、とんでもなく痛いのだ。文字通りに、身も心も。
それが分かっていながら、囮役をネロに任せた。それは四人の勝率を上げるためという大義名分があったとしても、彼にどれほど頑丈なまじないをかけたとしても、拭いきれない大罪に思えた。
そして、この場において確実な命の保証ができないのはネロだけではない。ヒースクリフやシノだって、多少安全だといえるものの、戦いのさなかでは何が起こるかわからない。
だから、この戦いに対して目を逸らすことは許されない。
それが彼らに対する責任――償いだと、ファウストは思った。
知らず、呼吸が浅くなっていた。隣にいるヒースクリフに気付かれないよう、ゆっくりと深呼吸をする。
眦を決して、ネロを眼鏡の奥からしかと見つめる。眼鏡に展望のための魔法をかけているので、彼の表情もはっきりと見て取れる。
そのとき、ネロが笑ったような気がした。ファウストは小さく息をのんだ。授業中どうでもいい悪戯を思いついたときのような、楽しそうな、いつもの笑みだったので。
囮はネロ自身のタイミングで始めることになっていたため、特に合図もなく彼は箒に立ち乗りしたまま柄を下に向け、厄災に向かって降下していく。自身の姿を見せつけるかのように、厄災の上部をゆっくりと旋回する。厄災は動かない。出方を伺っている。
ちょうどファウストとヒースクリフがいる位置と厄災を結んだ直線の右側にさしかかったとき、ネロのカラトリーが流星のように閃いた。
照明弾の、一発目。
白い尾を引いて照明弾が落ちていく。そしてちょうど、厄災の目の高さで炸裂した。
瞬間、真夜中の辺りが真昼の明るさになる。マグネシウムの発火のような白い光を正確に再現してみせたネロ手製の照明弾は、小さな太陽だと言っても過言ではなく、光量も位置も申し分のない一発だった。
余韻を残してその輝きが薄れていく狭間で、ネロの位置を割り出したのだろう厄災が、攻撃を始めた。
幾千もの光線がけたたましい音を立ててネロを追う。太いものと細いものが混じり合ったそれに対して、囮役のネロは全力を出さずにゆっくりと、光線を見つめたまま後ろ向きに上へと飛ぶ。着弾まで二秒もない。そんな中で、彼は何かのタイミングを見計らっているとファウストは気付いた。
何のだ、とファウストが眉を顰めた次の瞬間、ネロが箒を蹴り上げて飛んだ。
非の打ち所がない後方宙返りを、完璧なタイミングで彼はした。
箒のしなりを活かして高く飛んだ彼の後を、カトラリーがぴったりと追従する様子はあまりにも優美で、ひと時これが戦いの渦中だと忘れさせる。
避け切れなかった幾筋もの黄金の光線の全てが白銀のカトラリーに当たり、弾け、火の粉を散らす。それでも太い光線の全てを完璧に避けたネロは、着地するのに計算されつくした位置に呼んだ箒の柄に再び降り立つ。
第二射が迫る。一瞬のうちに細い光線しかないと見切ったネロは、指揮者がタクトを振るうように右腕を横に振る。すると一糸乱れぬ動きでカトラリーがネロを環状に囲み、展開して砲撃を迎え撃つ。
光線を真正面から受け止めて、ネロの胸まで光の粒子が飛び散る。が、その全ての火の粉は、万華鏡のように複雑かつ精緻な軌跡を描いて動き続けるカトラリーに防がれる。黄金の光の奔流のただ中にあって、星の瞬きのようにはっきりと見える白銀の輝きが目に残る。
「すごい」
隣で思わず呟かれた素直なヒースクリフの感想が、ファウストの耳を打つ。それが遠く聞こえるほど、ファウストは彼の飛翔に見入っていた。
不思議な飛び方だった。光線の動きを見ながら後ろ向きになって、滑らかに箒を走らせながら絶妙なタイミングで派手な回避を行うのは、北の国のスケートを思わせる。それと同時に、突然ぴたりと止まって、そこから細やかなステップを踏み、軽やかに光線を避けていくのはワルツのようだとも思える。
今宵の夜空は彼の舞踏場だった。彼に追従するカトラリーも舞い散る火の粉も、致死の光線までもが、全て彼を引き立てる舞台装置と化していた。
――踊っている。
疑いようもなく、ファウストはそう思った。きっと、ネロは肩口に触れたときに震えた自分の手に気付いていたのだろう。そうでなければ、わざわざこんな大掛かりで曲芸じみた回避をする理由がない。心配する必要なないと、大胆な行動で示すのがネロらしかった。
加えてファウストの脳裏に浮かぶのは、もはや四百年前の己の火刑の光景ではなかった。
火刑よりも少し前、かつての仲間と焚火を囲んで踊っていた無邪気な自分と、炎のむこうで踊っている楽し気なネロの姿が、重なったような気がした。
胸が灼けるような心地がする。それは炎に焼ける感覚よりももっと優しく、それでいて力強く、こころを打つ何かだった。
チカリとネロがいるところから強い白光が見えた。尾を引いて落ちるそれは、照明弾の二発目。
再び夜空を白光に塗り替えた照明弾の投下場所は完璧な位置で、ファウストに厄災の奥行をはっきりと伝える。もはや厄災は、その姿かたちを正確に暴かれていた。
これで魔法陣を外したら、呪い屋の名折れになる。
三百年間看板さえも掲げずにやってきた自分の稼業に、今更そう思ってしまうのがちょっと笑えた。そう笑えるのもネロのおかげだった。
彼の踊りに応えるためにも、全身全霊をかけて魔法陣を張ろう。自然と素直にそう思えた。
「……上出来だ、ネロ。ヒース、補佐してくれ」
「わかりました」
魔道具を呼び寄せ、その鏡面に彼が厄災と共に舞う様子を映す。心を奮い立たせるものの勢いに任せ、自らの呪文を唱えた。
「《サティルクナート・ムルクリード》」
遥か下の地面が明るく光り、魔法陣が現れた。ほつれがなく繊細なそれは、ファウストのものだ。ネロはほっと一息をつく。位置に大きなブレもないので、照明弾二発の投下は成功したのだろう。
これからシノがとどめを刺すまで、囮役として逃げ回らなければならない。しかし、もう照明弾を気にしなくてもよくなったので、厄災の攻撃を自身に集中させながら、どうやって飛ぶかは完全に自由だ。
大技をいくつか決めてきたが、明らかに面白いほどファウストの幸運操作が効いている。そもそも何百年もブランクがあるのにここまで動けるのがおかしい。何度タイミングを計っても外れることはなく、箒を操り忘れてもちょうどよい場所に落下しており、急ブレーキをかけても運よく靴が滑らない。
ブラッドリーの強化魔法とは違った感触のそれに、ネロは真実楽しんでいた。もっとこの空を、飛んでいたいと思いさえした。
だが、へまをするのは大抵そういう時である。
十何射目かわからない敵の攻撃が夜空を裂いてやってくる。カトラリーで受け止めようとした着弾の二秒前、今まで全部避け切ってきた太い光線が混ざっていることに気付いた。カモフラージュのように細い光線の中に巧妙に隠されたそれは、どのように避けても避け切れない。
ぬかった。そう頭で諦めたように声がするが、身体と魔法は防御態勢をとる。細い光線と太い光線が芸術的な螺旋を描いているのが嫌にはっきりと見える。視界が黄金に染まる。
着弾。
カトラリーの防御に当たる前に、光線は目の前で水飴のように裂けた。
驚く間もなく、両脇を光線が走っていく。ネロ自身は透明な繭玉の中にいるかのように当たらない。幸運操作で説明できないそれを、ネロは正確に理解した。火除けの呪いだ。
嘘だろどれだけかけたんだよと言いたくなるくらいの、途方もない威力だった。
三百年間呪い屋をやってきた経験をもとに、粋を尽くして練り上げられた呪いは、ある一定の強さの光線でないと発動しないらしい。
「細かい火の粉までしっかり弾いてしまうと、防御を過信して逆に危ないだろう。僕の呪いをあてにしないでくれ。あくまで最後の砦だ」と言っていた意味がいまわかった。彼の呪いがあれば、例え火の中であろうともどこまでも行けるだろうと信じられてしまう。それくらい強力だった。
ただその通りに火の中に突っ込めば長くはもたない、命綱のような呪いなのだろう。火除けのくせに「油断するな」というメッセージが込められた呪いが、彼らしくて小さく笑ってしまった。
実際油断してへまをした訳だが、彼のおかげで助かったと同時に得たものがあった。
足元から胸まで迫る黄金の光が裂けた様子。
それは、麦穂をかき分けて進む、黄金の麦畑を連想させた。
我ながら、だいぶ現金だなと思う。もちろん頬を撫でる熱風の激しさや飛び交う火の粉、夜空の暗さに反する光線の眩しさは麦畑のそれではない。
が、魔法は心で使う。この極限の状況下において、いつも心を落ち着けて寝っ転がっている麦畑が想像さえできれば、すでにこちらのものだった。
集中力が増していく。もう油断はしない。その決意を込め、自らの呪文を唱えた。
「《アドノディス・オムニス》」
シノはファウストの魔法陣からやや外れた木陰に身を潜めていた。ネロにより照明弾が二発撃たれ、ファウストの魔法陣も展開された。あとはタイミングを見計らい、自分がかの厄災にとどめを刺すまでだ。
「落ち着け、落ち着け……」
自らに言い聞かせるように何回か口の中で呟く。今もすぐにでも飛び出していきたい。けれどギリギリの理性が今ではないと告げている。最もネロに光線が集中し、防御が薄まるその瞬間を狙わないといけない。
逸る心をなだめながら、逆に、ヒースクリフの激励やネロの見事な箒さばきの数々、ファウストの盤石な魔法陣を見て気持ちが昂らない方がおかしいんじゃないかとさえ思う。自分もあんな風に、仲間の心を奮い立たせるような何かを、あの夜空でしたい。
――戦いの中では醒めろ、シノ。
そんな中、レノックスの静かな声が耳朶を打った気がした。体術訓練で何回も言われたので覚えている。シノが勢い任せに技を決めれば必ず言われるそれを、ふと思い出した。
初めに言われたときは醒めなくてはならない意味が分からず、理由を聞き返した。
レノックスは、戦いの興奮に飲まれた者から身を滅ぼすことになるからだと答えた。
その時は本当かどうか分からなかったが、レノックスの方が体術では優れているのは明白だったので、言われた通りにしていた。
けれど、なかなかどうしてこれが難しい。獲物、弱点、その他狙うべきものが見えた瞬間に突っ込むのがシノの性分だったので。
中々出来ずに焦れたシノは、コツはあるのか、とレノックスに問いかけた。彼は少し考えた後、「魔道具」と呟いた。
「魔道具には思い入れがあるだろう。それを思い返して冷静になるんだ」
「レノックスには、それに冷静になれる思い入れがあるのか?」
それ、と目線で見つめた先にはレノックスの魔道具である鍵があった。ちょうど彼が手に持っていたのだ。随分と年季の入った鍵で、冷静になれる要素はないように思えた。だがレノックスは「ある。……内容は秘密だが」と即答したのが意外だった。
シノの大鎌の柄には、ヒースクリフが彫った部分がある。それをなぞるように撫でても嬉しさと懐かしさがこみ上げるばかりで、全然醒めない。むしろわくわくしてくる、と言うとレノックスはちょっと困ったような顔をして、別に魔道具でなくてもいい、と言った。
賢者に貰った勲章も胸を高鳴らせるものであるので、元々持ち物が少ないシノはそこで手詰まりになる。ファウストに教えてもらったアミュレットも、常に持ち運べる訳ではない。
結局自分は何をきっかけに醒めるようにしたのか。時間をかけて頑張って捻りだしてくれたレノックスの横顔が頭に浮かんだ。確かこう言ったのだ。
「ヒースクリフが言った言葉でも思い出せばいいのではないか」と。
――武運を。
この一言で、自分はどこまでも行ける。
きんと冷たい井戸水を頭から被ったときのように、一瞬で火照っていた頭と心が冴え冴えとしてくる。葉の擦れる音、大気の温度湿度、風の強さ向きまで正確に肌で感じられるようだった。意識が鳥瞰するかのように、すっと高い位置に持っていかれる。
いっとき前までは身体の中で熱が暴れ周り、周囲のことなんて目に入っていなかった。いまもその熱自体は失われていない。ただ、焼けつくように燃えるそれを、主君に与えられた清流のごとく透明で澄んだ力に突っ込んだだけだ。
ずっと慣れ親しんできた夜の森の感覚が、シノの元に帰ってきた。ヒースクリフの言葉には、それだけの力があった。
シノはもはや、完全に醒めていた。感覚が常よりもはるかに鋭敏だった。ファウストとヒースクリフが設え、ネロが踊った舞台の隅々まで見渡し、理解し、それに加わる絶妙なタイミングまでもが手に取るようにわかる。
無意識のうちに箒を呼ぶ。手に馴染むそれと大鎌は、もう確認せずともどんな風に自分の力になってくれるかがわかる。
戦いに対する興奮も恐れも全て飛び越えた、澄み切った力を込めて自らの呪文を唱えた。
「《マッツァー・スディーパス》」
ヒースクリフはファウストの魔法陣の展開の補佐を終え、厄災とネロの舞踏を眺めていた。
ただ眺めているだけではない。絵画のように風景全体を均一に見渡し、何か異変があったときにすぐ気付けるように意識を広げているのだ。
戦いの中でも臆病な性質が尾を引く自分が情けなくて、ファウストとネロにそれぞれ相談したことがある。
ファウストは臆病な理由を深堀りしてくれて、危機察知能力に優れていると言ってくれた。ネロは全体を俯瞰すれば、自分の感情に振り回されることなく集中できるはずだと言ってくれた。
どちらも自分の臆病さを押さえつけるのではなく、対処する道を教えてくれた。
それが自分の胸を押す。思い出すと熱い何かが自分の内から零れてくるような気がするが、それに構わずヒースクリフは全体を俯瞰し続ける。自分以外の三人のために、自分が最大限出来ることはこれだと冷静な理性が告げていた。
ネロの踊りはクライマックスが近い。厄災も近くを飛び回ってなおずっと撃ち落されない魔法使いに焦れたようで、先ほどから攻撃が激しくなっていた。
集中砲火が激しくなるにつれて、ネロは針に糸を通すような回避をするようになった。それが一番体力も魔力も使わず、効率がいい避け方なのだろう。その分彼はかなりの集中力を使っているはずだが、表情はなおも楽し気だった。
ぐるりと厄災の周囲を回った後、ネロは上へ上へと上昇していく。光線がその後を追う。ネロを射程の外に出したくないのだろう、今回の光線の量は今までの比にならない。
ネロに光線が迫る。張り詰めた弓のように、時間が止まりにいっているかのように、着弾するまでの一瞬一瞬の流れが遅くなる。
厄災も、ネロも、ファウストも、ヒースクリフも、この場にいる全員がそう感じたに違いなかった。
一人を除いて。
刹那、厄災の目の中心に大きな一条の光が走る。光が薄まっていくと同時、厄災の目が裂け始めるのが見えた。光線の勢いが崩れるように消えていく。
大気を震わせる断末魔が、厄災を中心に放たれた。遠くの鳥も驚いて飛び立っていくのが見える。魔法使いたちは耳に魔法をかけて保護し、大気の振動に耐えた。
厄災自身でさえ、何が起こったか正確には分かっていなかっただろう。しかし全体を俯瞰していたヒースクリフはこの場においてただ一人、ことの全てを見守っていた。
攻撃を仕掛けたのはもちろんシノだ。そのタイミングがこの上なく秀逸だった。
ネロに攻撃が集まり、全員が固唾を飲んで、それ以外のことに関してはまったくの無防備だった膠着した瞬間。それを狙ってシノは箒の最大スピードで森から飛び出し、夜空を一瞬で駆け抜け、厄災の目に攻撃を仕掛けた。
厄災は防御魔法の展開も間に合うどころか、視覚さえもできなかったのではないかと思われる。全力のシノの攻撃を防御もなしに受ければ、絶命は必至である。
それは主人に心配もさせる間もないほどに完璧な、とどめの一撃だった。あの言葉を、正しく受け取ってくれた。そう思うとヒースクリフのこころに温かいものが広がる。
百五十メートルの高さを、ゆっくりと厄災の骸がファウストの魔法陣めがけて落下していく。
そのとき、何かを知らせるように冷涼な風が一陣、ヒースクリフの頬を撫でた。
何かが足りない。直感的にそう思った。けれどその何かが分からない。
ぐっと視点を引き上げ、この風景の違和感を探る。それを探すのに、それほど時間はかからなかった。
厄災の予想される落下地点が、魔法陣をわずかに逸れていた。きっとシノの攻撃で若干ずれたのだろう。
恐らくファウストは魔法陣に集中して気付いていない。気付かないところを見るに、重大な欠落ではない。ヒースクリフが見積もってみても、成功率は七割といったところだろう。ファウストがもし気付いたとしても、張りなおす手間と成功率を天秤にかけ、七割の方に賭けそうではある。
厄災がゆっくりと落下していく。
成功率七割は確かに賭けるに値する割合だが、失敗率三割と考えると判断が難しいような気がした。
ここで自分が魔法を使って厄災の位置をずらせば。
そう考えたヒースクリフの頭に、引っ込み思案で臆病な自分の声が反論する。もし失敗して成功率を下げたら。余計な横やりだったら。誰も何も言っていないのだから、別に何もしなくとも――。
いや、とその声を振り抜いた。
シノも、ネロも、ファウストも、この場において素晴らしい活躍を見せた。
ならば、最後の幕引きまで、完璧にしなければ。
先ほど胸から零れた熱いもの。シノの勇姿を見てこころに広がったもの。それは全て、勇気に変わっていくような気がした。溢れる想いに任せ、自らの呪文を唱えた。
「《レプセヴァイヴルプ・スノス》」