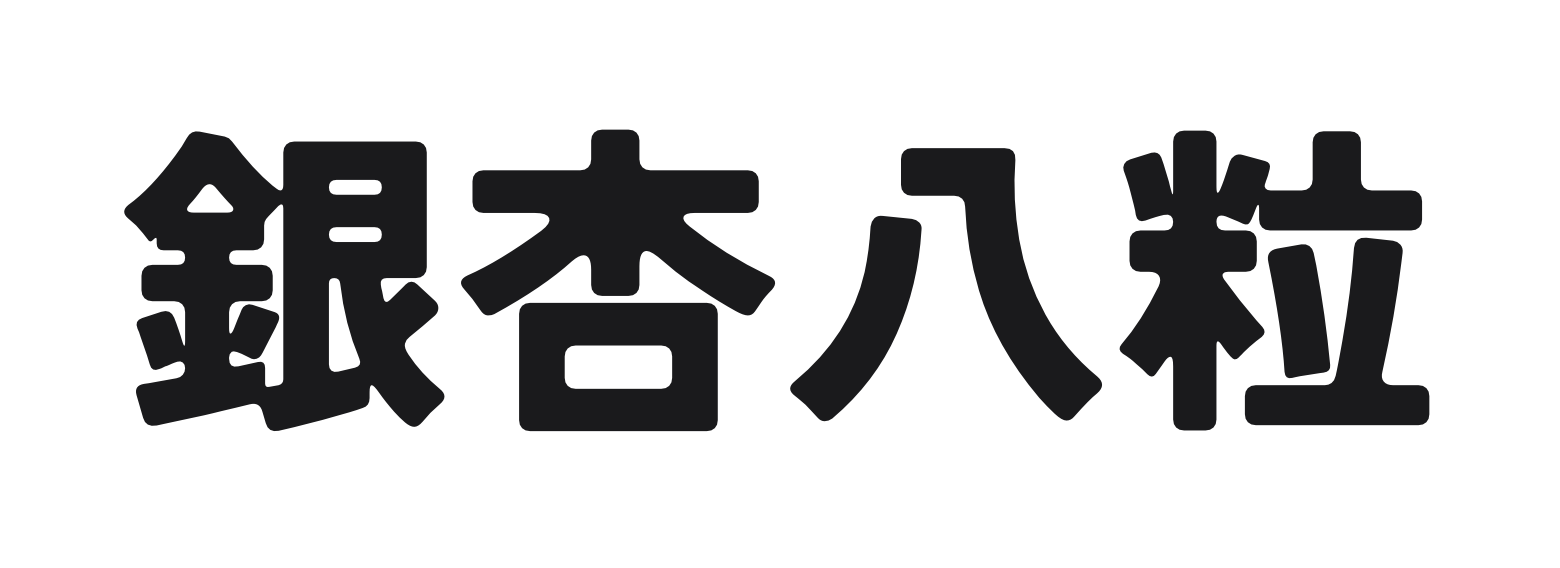・ヒースがシノに1.5部の無茶振りのようなものをする
・東の魔法使い全員に夢を見ている
しくじった。
反射的にそう思う。それでも手に馴染む大鎌に掛ける重さは緩めない。ギャリ、と甲高い嫌な音を立て始めるが、敵の大きな目玉に刃は届かない。強力な防御魔法が掛かっているのか、僅かに隙間が空いていることが分かる。
シノは舌打ちする。それでも引かず、重力を味方に付けて、大鎌の重みを増すように全身の力を一点に込める。ゆっくりと防御魔法ごと沈めるように。汗が噴き出る。大鎌を持つ手が震える。時間が流れるのがとんでもなく遅く感じる。
そのとき、初めて敵と目が合った、と感じた。
目くらましの魔法を貫通して、虚ろな視線がシノに焦点を合わせる。明確な死の気配にぞわりと総毛立ったシノは、ほとんど反射的に箒を呼び寄せ、その細い柄を蹴り上げて離脱する。
ぐわりと視界が回る。上空三百メートルからの自由落下の中においても、シノは冷静に再び箒を呼び寄せ、両手で掴む。いつもなら逆上がりの要領で態勢を整えるのだが、敵の動向を確認するために、そのままの格好で自分がいた場所を見上げる。
閃光が夜の闇を引き裂いていた。
途轍もない轟音を立てて、シノが先ほどまでいた場所に幾百もの光の束が走っていた。恐らくあれは、生命と言う生命を即死させるエネルギーが一本一本に詰まっている。砂漠の中を連想させるほどの熱風、蝶の鱗粉のように舞う細かな火の粉、夜の中でも一瞬真昼のようだと錯覚するほどの眩い光がその破壊力を物語る。
その光景に息が詰まると同時、暗闇の中で急に強烈な光を浴びてシノの目はひと時麻痺する。夜目を効かす魔法が裏目に出て、視界が真白に塗り潰されたまま回復しない。敵がこの状況で追撃してきたらまずい、と脳みそが危険信号を鳴らし身体が強張り始めるその一瞬前、背中にやわらかい感触が当たった。
「お疲れさん」
ネロの手だった。敵がまだ生きているのに労われることが不満で、シノは鼻を鳴らす。それにネロが小さく笑った気配がした。
東の魔法使いと深夜戦線
「状況を確認しよう」
厄災の視野から少し離れた木陰で、明かり用の松明が空中で小さく揺らめく中、先生役であるファウストが重々しく言う。東の魔法使いたちは円になるように炎を囲んで座っており、それぞれの影が不安定に、大きくなったり小さくなったりしていた。
東の森の上空に何か得体の知れない物体があるから調査してほしい、という依頼を受けたのが今日、ネロの夕食を食べ終えたすぐ後だった。こういう依頼は次の日の午前中にその仕事を回すのが普通の話だったのだが、今回は「日が出たらその物体が進んでいるような気がする。進行方向には街があり、一応住民を避難させてはいるが、どのくらいの速さで何が向かってきているのかも分からない。夜のうちに討伐してほしい」と来た。
賢者は緊急の依頼と捉え、東の国の魔法使い全員を向かわせた。
この「得体の知れない物体」は、案の定厄災だった。しかも、シノの渾身の一撃に耐えるレベルで耐久力があり、無数の強力な光線を打ち込めるほど攻撃力があるという、相当厄介な方に分類される厄災である。
この時点で東の魔法使いたちは、魔法舎に応援を呼ぼうとした。しかし北の魔法使いたちもオズも(ファウストとネロはフィガロもその候補に入れたが)全員出払っていることに気付き、やめた。夜明けまで時間がないこの状況で、一人でも欠けるのは得策ではないと判断したのだ。
幸いなことに突撃をかましたシノをネロが回収してから、厄災の追撃はなかった。厄災はいま、先ほどまで甚大な破壊力を示していたのに反して、不気味に沈黙を保って宙に浮いている。その様子が木の葉の陰から見え隠れしていた。
「シノ。敵の状況を報告してくれ」
「……今回の場合はどう報告すればいいんだ」
「そうだな、まずはあの光線についてどう思ったか知りたい」
「多分、細かい光線の中に太い光線が混ざってた。細かい光線は普通の防御魔法で何とかなると思う。太い光線はまともに防ぐよりも躱した方がいい」
「なるほど。太い光線はどのぐらいの幅だった?」
このくらい、とシノが手で示した幅はおよそ三十センチ。確かに腹に食らったら、大穴が空くどころか上半身と下半身が泣き別れすることになるだろう。
厄災は、賢者の世界の言葉を借りて説明をするなら、超弩級戦艦のごとき戦力を携えた空に浮かぶピラミッドの様相を呈していた。三角錐型で一辺約百五十メートルの大きさの本体。その側面の二つに大きな目が一つずつついている。ちょうど三百六十度見渡せる形だ。そのほかに本体に光線を出す機関などは見受けられず、目さえ付いていなければ建造物だと間違えそうな厄災が、おおよそ百五十メートル付近の上空に浮かんでいる。
ファウストが再度シノに尋ねる。
「防御魔法の強さは?」
「……オレがこの刃全体で押しても破れなかった。でも、防御の膜自体は押せたような感覚はあったから、一点集中で負荷を掛ければ破れると思う」
だからもう一回行かせてくれ、という目でシノはファウストを見つめるが、そのファウストは目線を伏せて考え込んでしまった。
そもそもシノは我慢が嫌いなたちなので、いつもならば速攻で敵にもう一撃をお見舞いしに飛び出している。それでも行かないのは、魔法舎を出る前、「先制攻撃の役目を渡す。それが通らなかったら大人しく撤退してきてくれ」とファウストに頼まれたからだ。
頼まれた一番銛の役割が果たせなかったので言われた通りにしているが、シノはものすごく不満で腹が立っている。すぐに攻撃の許可をくれないファウストにもそうだが、いっとう苛立つのは自分の不甲斐なさだ。
今すぐにでもかの敵を討ち取り、この雪辱を晴らしたい。そして、一番に手柄を立てたい。
だがそんなシノの心情は他の三人にもわかっていたので、光に麻痺したシノの目を治癒する魔法をかける者はいなかった。しばらく安静にしていればこれといった後遺症も残らず治る類の症状であったので。
視界が回復したらすぐにでも駆けていきそうなシノのぎらぎらした赤い瞳を、目線を上げたファウストがひたと見つめる。その瞳の深い紫の色は、シノの薄っすらと白む視界の中でも不思議とくっきり見えた。
「――僕が舞台を作ろう」
森のざわめきがしんと消えたように錯覚する、小さくともはっきりと響く声だった。
「きみが武勲を求める気持ちはわかっている。それを無下にするつもりはない。ただ、今夜の敵に対して力任せで押し切ることは愚策だ。だから、僕が英雄の活躍できる場を設えよう」
言外にそれでも不満か、という圧を滲ませる。この四人が空中分解したら今夜を越えられないと考えたファウストが、彼向けに何とか絞り出した言葉だった。その内容を咀嚼するように、シノが軽く目線を伏せる。
芝居がかったその台詞にヒースクリフは素直に感嘆したが、ネロは内心吹き出しそうになっていた。明らかに陰気な呪い屋の柄ではない。それでもシノの心に訴えるために相当慎重に選んだ言葉なのはわかっていたので、表には出さなかった。が、何か感じるものがあったらしいファウストに、静かに睨みを効かされた。
言葉をかみ砕き終わったシノが、再びファウストの双眸を真っすぐに見つめる。
「……それは四人で英雄になる舞台、ってことか?」
思わぬ返答に、ファウストは空から星が降ってきたように一瞬固まる。まさか自分も英雄の一人にカウントされるとは思っていなかったのだ。シノに向けて異議を唱えさせないように滲ませた重圧も、空気を読むことが苦手だと自覚があるほど胆力のある彼にかかれば、一瞬で木端微塵に粉砕された。
「いや、僕は…………そうだ」
反射で英雄になることを否定しそうになる口と、シノの協力が必要だと思う頭の板挟みになり、混乱してついうっかり素直に肯定してしまった。いつもならそれとなく迂回させるように説明する余裕があるのだが、いまのファウストにはそれはなかった。
しかし、相対する相手はその様子を特に不自然だとは思わなかったらしい。シノが、すんなりと言葉が沁みたように頷いた。
シノは以前まで、手柄は最初に討伐した一人だけのものだと考えていた節があり、いの一番にそれ目掛けて駆けていた。だがしかし、魔法舎でひょっとすると家族のような共同生活を送るうち、この四人で名誉を一緒に受けとるのも、中々悪いことではないのではないか、とも思うようにもなっていた。
「わかった。頑張って協力する」
その一言を聞いて、ヒースクリフとネロは心の中でファウストに拍手喝采を贈る。シノから討伐に関して我慢を引き出す難しさは、二人とも長い付き合いで身に染みるほど分かっていた。
予想外の変化球を受け返した疲れを散らすように、そっと一息をついたファウストは、それでもまだ安堵はできない状況に色付き眼鏡を掛けなおした。
現状は最低最悪の極みであると言っていい。光線を使ってくる敵に対して、この月明かりのない夜は攻略の難度を跳ね上げている。夜目を効かす魔法が封じられたので、至近距離でもない限り、敵の位置をおおよそ勘頼りにして攻撃するしかない。
せめて月が覗いてくれたらと空を見上げてみても、今日に限ってその大いなる厄災は分厚い雲に覆われている。
「……あれが万が一にでも街に向かわないように、討伐できたとしてもその死体を固定しなければならない。これは僕がやろう」
条件は考えたくないほど絶望的だが、まずは結論から攻める。不思議の力に満ちているこの世界においては万が一の用心はしてもしきれないようなものだが、これが最低限のゴールだった。封印やら何やらその他後始末は後からすればいい。
「討伐とその固定のためにはあれの体力を削らなければならないが――」
そこでヒースクリフが挙手したので、「ヒースクリフ」と呼びかける。魔法舎に来てから長い間染みついた授業の流れが、この危機的状況においても活きていた。
「厄災の攻撃手段が光線なら、鏡のようなもので反射させればいいのではないでしょうか」
「いや、やめた方がいい」
ファウストが意見を述べる前に、間近で光線を見たシノが反論する。
「あの光線は多分、光が集まったものじゃなくて火が集まったものだと思う。火の粉も見えた」
視界が白く塗りつぶされる直前に見た光景を、鮮明に思い出しながら言う。それに加えて、シノはあの光線が放たれた直後に息が詰まった。あんなもので息が詰まるほど物怖じする性格ではないと自分でも知っているので、物理的に酸素が奪われたのだと直感していた。
炎が凝縮された光線、という言葉を聞いてファウストが顔をしかめた。と同時にネロが挙手したので当てる。
「ヒースクリフの考えは良かったが……そうなると厄介だな。ネロ」
「火ってことは周りの酸素をなくせば……」
ネロは、ガスが出なければいくら着火させようとしても火が持続しない台所のガスコンロを想像しながら発言した。が、ファウストの真顔で聞く態度に途中で自信をなくし、「……悪い。馬鹿言った」と気付いたら言っていた。
全身黒ずくめの先生役は、夜の森を背景に真顔になっているだけで迫力がある。その言葉を聞いてファウストは眉を寄せた。
「何も言っていないのになぜ謝るんだきみは」
「いやー……現実的じゃないだろ?」
「そうでもないよ。砲門のようなものがあればその手は確かに有効だったはずだ。だけど、今回の敵はそれがないからあの敵の周り全体の酸素をコントロールしなければいけない。僕らにそんな魔力はない。よって却下だ」
「結局却下じゃん……砲門?」と呟く料理人に、「大砲の銃口って意味」と武門で有名な名家の子息が的確に答える。呪い屋はその会話をあえて無視した。
そう、この厄災はどこから光線が飛んでくるかわからない。シノが突撃したとき、他三人も注視していたが、厄災の側面からおおよそ三メートル程度離れた何もないところから発射された。
「なんであんな目があるんだろうな」
ぽつりとシノが言った。三人の顔がシノに向かう。ファウストが視線でその先を促した。
「目は、弱点だ。どんな生き物でも。でも、あの厄災はあんなにでかい目を持っている」
言われてみれば、確かにそうだった。まるで『ここを狙って攻撃してください』と言わんばかりのそれは、要塞のようなかの厄災において不自然なものだった。
「じゃあ、あれは囮でほかに弱点があるのか」
「あの目が見せかけなら。シノ、どうだ、あの目は機能していると思うか」
結論を急ぐネロの言葉にファウストが待ったをかけた。
シノは思い出す。近付いても虚空を見つめていた目。しかし離脱する直前に思ったのだ、「目が合った」と。
「あれは、見るための目だと思う」
「……わかった。じゃあヒースクリフ、それをふまえて大きな目を持つ理由は何だと思う」
ファウストから急に指名されたヒースクリフは、少し目線を右上に持ち上げた。考えていたのは僅かな時間で、すぐに答えが出てきた。
「光をより取り込むため、でしょうか」
「正解だ。恐らくあの厄災は視力だけに頼っていて、他の五感は鈍い。多分、攻撃と防御に魔力を使いすぎるんだろう」
シノが攻撃したとき、彼は夜の闇に紛れていたのと目くらましをかけていたので、かなり見えにくかった。それでも普通の生き物ならば、彼の音や振動で、攻撃されていると感じ取れる機会はあったはず。その割には反撃が遅かった。そう考えると、あの厄災は視力だけに頼っていると結論が付く。
ぴんと閃いたネロが、身を乗り出して言う。
「じゃあシノがやられたように、強烈な光でも浴びさせればいいのかね」
「……どうだろう。あの厄災自身の攻撃だけでも相当な光の強さだった割に、目は閉じていなかったような気がするんだが……」
「よく光を取り込むから、ある程度の光の耐性もあることも考えられますね」
「確かにそうかもしれない。そして仮に、光で視界を奪ったとしても、その先に防御魔法があるから結局体力は削れないな」
「……強い、ですね」
見えた希望が掴む前に遠いところに行ってしまったようで、ぽつりとヒースクリフが零す。感応性が高く、危機察知能力に優れているので、この状況がどれほど絶望的なのかがまざまざとわかるのだろう。そのまま俯きそうになったヒースクリフの頭を、勢いよくくしゃりと撫でたのはネロだった。
「わ」
「どんなに強くても、つけ入る弱みはあるもんだぜ。坊ちゃんのヒースには分からんだろうが、どんなに堅牢な屋敷でも絶対に抜け穴はある」
「おい。オレの前で言うかそれ」
「おまえだって、わかってるんじゃないか?ブランシェット城の、まあ抜け穴とまでは言わないまでも、特に侵入しやすい場所。それで、とりわけ慎重に警備しているような場所」
「……」
シノの沈黙が答えだった。ヒースクリフは「あるんだ……」と呟く。さすがに家庭教師も教科書も、実家の城の陥落のさせ方は教えなかったらしい。
もう俯く様子のないヒースクリフの横顔を満足げに見て、ネロは話を振った。
「屋敷が屋敷であるならば、そういうもんさ。生き物が生き物ならもっとわかりやすい――はずだ。だろ?先生」
「例えが倫理的ではないが、そうだな」
ファウストはため息をつきながらも、渋々同意した。そして、授業中に黒板の図を使うのと同じ要領で厄災の方向を指さし、その見えない輪郭をなぞる様に指を動かしながら話始める。
「防御魔法と攻撃魔法を両立させるために視力以外の器官を捨てた、といま僕らは考えた。だが、それでもあれほどの防御魔法と攻撃魔法を同時展開させるのは本来難しいくらいの魔力量に僕は感じる」
厄災は、いまも不気味に沈黙を保っている。基本的に攻撃されたら反撃するだけらしいが、昼になれば街へ向かいだすというのだから何をしでかすか分からない。夜は静かに佇むだけという性質は、昼に使う魔力の貯蓄のためだろうというのはファウストにも見当が付いていた。
が、実際相対してみるとそれほどまで魔力がある厄災とは思えなかった。
もちろん通常の厄災よりも魔力量は多い。ずっと多い。しかし、それでも魔力量に比べて、攻撃と防御が桁外れに強力だった。北の魔法使いを想起させるような強力な攻撃や防御に比べて、「近付いたら不味い」という威圧感が圧倒的に足りない。
北の魔法使いがまき散らす威圧感が異常なのかとファウストが首を捻ったとき、シノが「同時展開」と呟いた。
「なあ、同時展開って言ったか」
「ああ。それがどうした」
「同時展開はしてなかったぞ」
一瞬時間の流れが止まった。シノ以外の三人がその言葉を飲み込むのに時間がかかったのだ。それでもさすが一番初めに立ち直ったヒースクリフが質問する。
「シノの攻撃を防いだのと同時に光線を撃ってきたんだよね?」
「そうだが……正確に言うと、オレが攻撃、防御魔法が発動、オレが回避、攻撃魔法が発動、だった」
たどたどしいシノの説明でも全員が理解した。
――シノは攻撃が放たれるよりも先に回避していたのだ!
遠くから見ていたので全員が気が付けなかったそれは、まさしく神業だった。初見の敵の、初めて見る攻撃パターンのタイミングを完璧に読む。言うは易く行うは難しの典型である。
シノは突然皆の雰囲気が変わったことに驚いた様子だったが、感嘆し始めたということにすぐに気付いたようで、口角を上げた。そして思わずネロの手がシノの頭に伸びて、そのまま撫で繰り回すことになった。
「すっげぇなおまえ……」
「もっと褒めろ」
「いやほんとすげえよ……」
ネロは同じようなことを繰り返すが、自分のなした技に感激してそうなっているのがわかるのか、それとも頭を撫でられるのが嬉しいのか、シノは「ふふん」と得意げだった。
「シノの殺気を捉える力ももちろん優れているが、そもそも咄嗟の判断に従えるだけの高い瞬発力がないと、できないことだ。流石だな。――そしてこれで、勝機が見えた」
ファウストがこほんと咳払いをして言う。全員の視線が集中する。
「あの魔力量では、攻撃と防御は同じレベルでの同時展開は不可能だ。ということは、どこかに光線を集中させている間に、厄災を攻撃すればいい」
「オレがとどめを刺すぞ」
「そこに今更、異論はないさ。となると、攻撃を一身に受ける囮役を」
言葉を切って、ぽん、とネロの肩を叩いた。
「君に頼む」
「俺かい。……まあ、なんとなくわかってたけどさ」
ファウストは他人が想像するよりもずっと、東の国の子供たちを大切にしている。なるべくなら危険なことをさせたくないのだろう。本当はネロにだってやらせたくなはいと考えているだろうが、彼の立ち位置はファウストと同じ保護者だ。
それには納得するものがあるので、ネロは素直に頷いた。
肩口から手を離したファウストはその様子を確認し、唇の動きだけで「すまない」というので、ネロは口の端を上げた。頼んでおいて謝罪する不実さと、それでも言わざるを得ないというどっちつかずの倒錯を、ファウスト自身が感じているのを正確に汲み取る。
ブラッドリーは絶対に言わなかったり、悟らせないそれ。しかし、ネロはファウストのそういうところを好んでいる。ひっくり返って、逆に誠実だと感じられるのだ。なので、全く不満はない。
「それで?どうせ、ただ囮ってわけじゃないんだろ?」
想像よりも乗り気なネロに驚いたようにぱちりと目を瞬かせた後、その雰囲気を瞬時にかき消して、いつものようにファウストが答える。
「そうだね。僕が魔法陣を張るために、あれの奥行きが正確に知りたいから……照明弾を二発、間隔を開けて打ち上げてほしい」
打ち上げるというより打ち落とすかな、と続けながらネロを見る。案の定わからないというように困惑した顔をしていたので、詳しく説明を加える。
「厄災の手前で一発、奥に行って一発だ。そうすれば夜目の魔法よりも、正確に位置感覚がつかめる」
夜目の魔法は、欠点がある。全ての物体が奥行を失い、のっぺりと見えることだ。その様子は、どれだけ写実的に描いても結局は平面の絵画に似ている。
月も見えない夜に、敵の奥行きを知るためにはこの方法しかなかった。
「なるほど。なんとなくはわかった。花火でも打ち上げりゃいいのか?」
「いや、理想は……」
ファウストは一瞬ためらった。平時の彼のペーパーテストの点数を思い出したからだ。これから言うことは、絶対に思い出せないのが手に取るようにわかる。
けれどここで黙っても仕方がないので、一呼吸置いて言った。
「マグネシウムの塊を発火させたような光の玉、だ。花火よりも明るい。授業でやったんだが」
「思い出せねぇな」
「反射で思い出すことを放棄するな」
言う前から思い出せないだろうと考えていた自分を棚に上げてファウストは突っ込んだ。
「マグネシウム……まぐねしうむ……?」と呟くペーパーテストの点数だけなら紛うことなき落第生に、「えっと、炎色反応実験で、一番白く光ってたやつ」と注釈さえもいらない紛うことなき優等生が的確に答える。
「えんしょくはんのう……」と下を向いてまだ呟き続けるネロに被せるように、「なんか色々なものに火を点けてたあれか」と彼より早くに思い出せたシノが言う。その言葉を聞いて、ネロはがばりと顔を上げた。
「あ」
「思い出したか」
「あー……わかった。思い出した。でも俺マグネシウムをそのまんまなんか出せないんだけど」
「別に、そのままでなくてもいいんだ。あれくらいの光だと想像できれば」
魔法は心で使う。花火よりも何よりも強く、小さな太陽のように白く輝く光が想像さえできれば、すでにこちらのものだった。
「ファウスト」
挙手をしてシノが問いかけた。
「囮は一人じゃなくて、オレとヒースも一緒にやった方がいいんじゃないか」
「……光線の射線が交差する中で複数人が逃げるのはあまり得策ではないと考えるが」
そうだな、とシノは引き下がった。もともと確認に近い質問であったので。それに続くように、先生と呼びかけると同時にヒースクリフが言う。
「俺はどうしましょうか」
ファウストは少し考えた後、答えた。
「魔法陣を張るところの場を整えてもらおう。とはいっても、僕らの中で一番危険を察知しやすいのはヒース、きみだ。全体を俯瞰して見て、何かあったら知らせてほしい」
「わかりました」
「ネロ、火除けの呪いをかける。来てくれ」
ネロはあいよ、と立ち上がってファウストの元に向かう。
そんなさなか、その場に残ったシノがヒースクリフに話しかけた。
「ヒース」
「何?」
「『無茶振り』、やってくれ」
保護者組二人は、思わず振り返った。
シノがこのように言うことは、あのオヴィシウスとの戦い以降、何度かあった。二人がそのとき交わしたらしき「無茶振り」の詳細は、戦いのあと夕食を共にしたときシノが自慢するように言っていたので、ネロとファウストも知っていた(恥ずかしがったヒースクリフが常に遮ろうとしたので、すべての文言は聞き取れなかったが)。
だが、そんなことがなくても大体どんなことを言ったかは察せただろう。シノは、主君の鼓舞がほしいときにいつもそう頼む。
が、ヒースクリフはそれを断ってきた。
全てかどうかは分からないが、少なくとも他人の前で「無茶振り」をしたことはなかった。
ヒースクリフが一言「嫌だ」と返すと、シノは「まあ、もったいないもんな」とあっさり引き下がるので、別にわざわざしなくてもいいものだったのだ。
今回もそうだろう、とヒースクリフは予想する。きっと、この幼馴染は今日も自分が一言「嫌だ」と言えば文句も言わずに撤回するだろう。少し残念そうな顔をして。別に、そんな顔をされても幼馴染なので、自分の胸に響くものは、きっと少ししかないが。
ただ、今夜の敵はシノの望みを叶えてもいいくらいの強敵に思えた。いや、叶えてもいいなんて邪な思いじゃないと、ヒースクリフは自分でその考えをすぐに否定する。
シノに心を奮い立たせる鼓舞が必要だというのなら、惜しみなくあげたい。
心の底から、そう思った。
ヒースクリフは目を閉じる。無茶振りといっても、シノに無茶をしてほしい訳ではない。それでもいまのシノを、最も勇気付けるものは何か。それだけを追いかけて意識の深層に潜ってみると、心の奥底から透明で澄んだなにかが湧き上がってくるような気がした。
いつもと違うヒースクリフに勘付くものがあったのだろう、シノが居住まいを正す気配がする。そんなシノに応えたい。そう考える自分の声が身体に響き、湧き上がる想いと共鳴し、より反響して大きくなっていく。
主君と臣下、幼馴染、約束を交わした仲。積み重ねた思い出全てが激しい勢いで胸の内を満たし、みずみずしく清らかな力に変わっていく。
ヒースクリフはゆっくりと目を開ける。こころを駆け巡る奔流のような力、その全てを使った一言が放たれる。
「武運を」
たった四文字の静かな言葉に、これ以上ないほどの威厳が湛えられていた。
この一言で、遠くから見ていた保護者二人にさえも背筋にぴりりとした雷光が走った。近くで一心に聞き、しかもその言葉が自分に向けられているシノが受けた衝撃は想像するまでもない。
ヒースクリフの瞳は澄みきった朝の湖面のような静謐さを映しながら、その最奥にはっきりとシノに対する激情が宿っている。感情を表に出さない立ち振る舞いが、逆に込められた想いの深さを表現しているかのようだった。
ヒースクリフの言葉は正確には無茶振りではなかったが、この言葉を、この瞳でかけられて失敗できる臣下がいるだろうか。その意味では何よりも勝る無茶振りだと言えた。
並外れた権威の重圧を持つ言祝ぎ。ファウストはこの光景を見て、想起される人物が四人いた。アーサー、カイン、リケ、そしてアレク。この四人は絶望に折れた他者さえも立ち上がらせ、奮い立たせうる言葉を掛けることができる。生まれ持った立場か、天性の才能か。どの時代も、それを率いてきた人物は持ち合わせることが多い中央の資質を、ヒースクリフの中にもはっきりと見た。
加えて、ヒースクリフ自身のいまの美しさ――今晩の大いなる厄災が雲に隠れたのも、近くにある花が蕾のまま閉じているのも、その美しさに恥じらったからだと言われても不思議ではない、至上の光輝ともとれるほどの美しさ――が、威厳の桁を跳ね上げている。
その双眸に見つめられれば、理性を飛び越え、心から彼に従属したくなる人物がいてもおかしくはなかった。家名の宣言も、あまつさえ命じることさえしなかったが、人の上に立つ者が持つ威光を覗かせたその一言に対して、全てを投げ打ってでも彼のために何かをしたいと思う人物がいてもおかしくはなかった。
シノは喜びに身を震わせる。は自分に無茶をしてほしくないだろうというのは分かっていた。それでも自身を想い、折り合いをつけてこのように振る舞い、勇気付けてくれる。そんな彼のために、力を振るえるという果報を改めてこころに刻む。その想いを己の主人に伝えるための言葉を、魂の最奥から叫ぶ。
「――恐悦至極!」
何よりもひたむきに、真っすぐに、自分の瞳を貫いてくる深紅の瞳。それを見てヒースクリフはふっと、目元を緩めた。