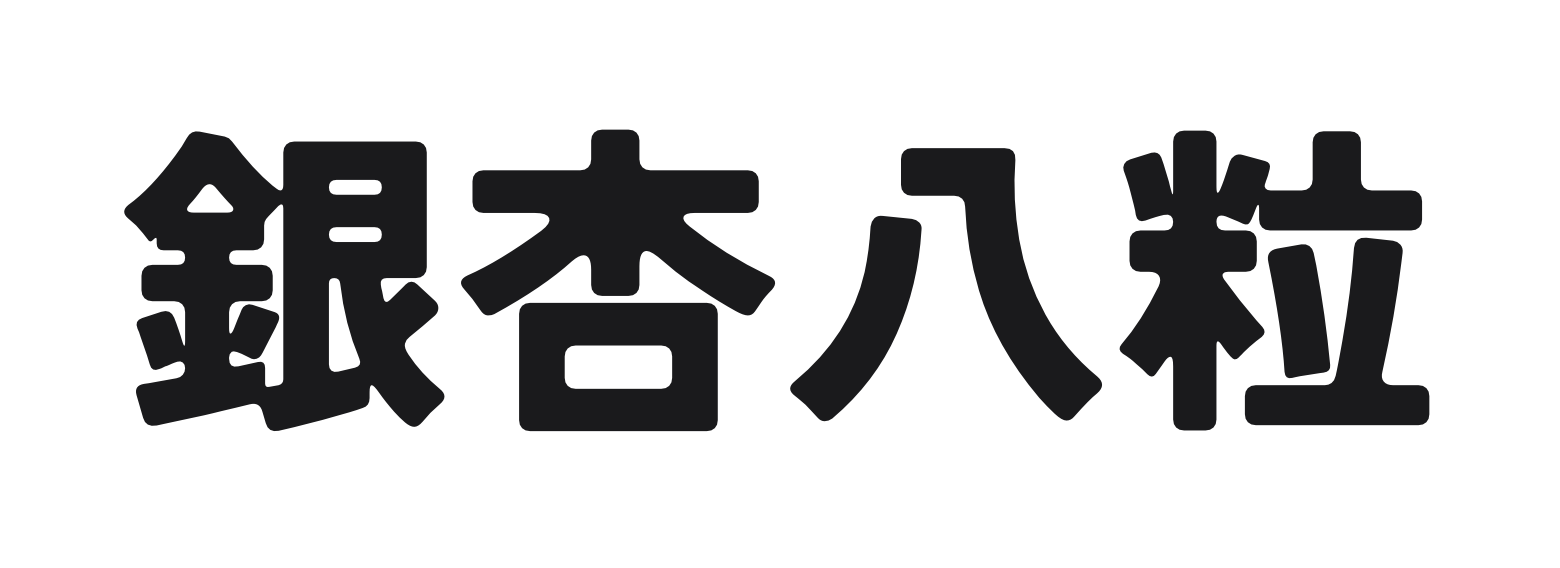「ここってなんにも考えたくないときにいいよねえ……」
「はあ」
フィガロがしみじみ呟くので、大した返答は必要ないだろうと無意識に判断したレノックスは気のない返事を返す。
ベンチに座る二人の目の先には、広大な草原と、そこに散らばる羊たち、そしてその更に奥には朝の空気に霞がかった南の国が誇る壮麗な山脈が広がっていた。盛夏の抜けるような蒼穹を、鳥が群れをなして飛んでいく。
確かに魔法使いも人間もちっぽけにさせるスケールの大きい自然は、何も考えない時間には最適かもしれないが。
流した会話だったが、引っかかるものは感じたのでそのまま言葉にする。
「……俺、仕事中なんですが」
「さっきの言葉は褒め言葉だから許して」
屁理屈にもなってないようなセリフを白々しく言う医者に、羊飼いはため息をこぼした。
午前十時のくだらない噺
夏の間、高山で暮らすレノックスに来客は多い。その理由のひとつは、フィガロの言う通り、「何も考えたくない」ときに訪ねたくなる場所だからだろう。
雄大な自然の中で暮らす男は、特に断る理由がなければ羊の観察のために置かれているベンチの隣を貸してくれる。寡黙で会話に困るかと言われればそうかもしれないが、本人は羊を見守ることが本職なので、沈黙が降りても苦にしていない。というか気にしていない。
これは南の国で彼に会ったことのある人物は皆知るところで、そういった雰囲気を好み標高の高い地まで登ることができる彼の友人は、人間魔法使い問わず時折レノックスの小屋まで訪ねてくる。
賢者の魔法使いになってからはこの地に羊もレノックスもいることがまちまちになったので、訪れる人物は減った。
ただ、代わりに羊を放牧しに南へ一旦行ってくるというと、魔法舎の面々がたまに着いてくるようになった。
以前は目を休ませたいと言って着いてきた賢者がこの地の冷涼な風に驚いていたし、自然の中に本格的に入ったことがないというリケは大きな入道雲に目を輝かせていた。前者はルチルとミスラ、後者はミチルと一緒だった。
珍しいところで言うとネロが着いてきたこともある。これは隣室付き合いの延長だったが、レノックスも知らなかった食べられる高山植物を発見して盛り上がった。
今日もいつものように賢者に知らせに行くと、たまたま通りがかったフィガロが「俺も行こうかな」なんてひょっこり顔を出した。
国中を飛び回る医者は以前からレノックスの小屋にもたびたび訪れる来客だったので、特に何の感慨もなく了承した。彼は今日魔法舎の仕事は非番らしく、また診療所を開けるのも午後かららしい。
いつものように羊を放し、二人そろってベンチに腰掛けた瞬間に言ったのが冒頭のセリフである。
流石にちょっと無礼が過ぎたのを自覚したのか、フィガロはしばらくの間黙って太陽の方向を見上げていた。この場合の「しばらくの間」は、この凄まじい速さで口が回る男にとってのことで、実際にはほんの二・三分のことである。
「レノはさ、辺り一面雪しかない所に行ったことある?」
そしてフィガロは唐突に話を切り出す。長い付き合いなので何らかの思考回路があってそこから導き出される話題なのはレノックスも分かっているが、いつも面食らって少々反応が遅れる。
「……あります」
「やっぱり北の国?」
「ええ」
人探しをする四百年のうちに世界のあちこちに足を運んでいたので、有名な山も海も森も川も洞窟もだいたい覚えがある。もちろん雪原もそれに含まれる。
レノックスは彼の地に訪れたとき、水分を多く含んだ重い雪が降っていたのを思い出す。
殴りつけてくるような猛吹雪は、確かに大昔から人間が生きていくのに適した環境ではないと言われているのも納得するぐらいに魔力と体力を消耗した。それでもレノックスは魔法使いだったので、なんとか探し人がいないことを確認し、生きて帰って来ることが出来た。
しかしどうやらフィガロが考えているのはそういった雪原ではないらしい。
「快晴だった?」
「いえ。――俺が行ったときは一日も快晴の日はありませんでしたね」
「そっか。言ったことあったっけ?北の国の一番寒いときの話」
「『雲一つない晴天の日』でしたか」
レノックスはかつてフィガロが喋っていた内容から引き出して言った。北出身の彼曰く、快晴の日が一番寒いらしい。よく晴れた日に双子に連れられて野外で修業をすると、空気があまりにも冷たいのと綺麗すぎるのとで逆に肺が痛むかと思った、と温かい珈琲を啜りながら言っていたような気がする。いつだったかははっきりしないが、この同じベンチで。
覚えていたレノックスが意外だったのか、フィガロはへえ、という顔をする。
「よく覚えているね」
「確か三回は聞きましたよ。全部話の展開は違ったような気がしますが」
「ほんと?じゃあその理由も覚えてる?」
レノックスは羊に向けたままの目を細め、少し考えて言った。
「『大気が雲に蓋をされないから』、だったような」
その答えを聞いたフィガロは一瞬驚いたように目を瞬かせた後、目尻を下げる。
「レノは話を聞くのが上手いね。正解だよ」
いつものフィガロのこちらを冷やかしてくる言動と組み合わせると、話相手に都合が良いね、という副音声が聞こえるような気がする。レノックスはあえてそれを無視した。
そうそう、話を戻すと、とフィガロが続ける。
「こうも日差しが眩しいと、空に雲一つない雪原のことを思い出すんだ。水平線から上は真っ青な空、水平線から下は雪以外何もない銀世界。視界の先にも何もなくて、振り返るとちょっとだけ山脈と森が見える、浮世離れした景色」
レノックスははて、と首を傾げた。そんな場所はあっただろうかと思ったのだ。いくら天候の違いがあるとはいえ、そこまで何もない地は記憶になかった。
ふと、違和感の正体を探るための質問を思いついた。
「先生、それいつの話ですか?」
「二千年前くらい?」
何の気なしにこれを言ってくる点において非常にたちが悪いとレノックスは思っている。
三十二歳の仮面をかなぐり捨てることができる自分の前では、彼の話は今の時間軸を飛び越えてあっちこっち行ったり来たりした後、いつの間にか現在の話になっていたりする。オズや双子の師匠と話すときもそうなのだろうか。昔々の話ならまだましな方だが、いきなり太古の話にすっ飛ぶのは彼の五回りは年下に対する話題としてかなり不親切である。
それでも、まあ、彼の話は面白い。
レノックスはからかってくる相手に若干不服ながらもその話の面白さは否めない。なので、飛び飛びの時間軸にはいつも目を瞑ることにしている。
今日は割と会話の序盤の方で気付けたので良かったことにしている気持ちを知ってか知らずか、フィガロは話を続ける。
「そういう環境にいると最初にやられたのが日差しだった」
「日に焼けたんですか?」
「眼がね。寒さはやられるとまずいのは最初から分かっていたから魔法をかけられたんだけど、日差しに眼が焼けるなんて知らなかったし」
二千年前となると紫外線の概念があったことすら怪しいところだ。今も二人は標高の高いところにいるということで目を保護する魔法を無意識に使っているが、それはそうした方が良いと知っていて、なおかつその方法を知っているからだ。魔法は心で使う。心が知らないことは当然できない。
「歩きながら文字通り雪目になってさ、涙が勝手に出てくるんだ」
風が一陣強く吹いて、目の前の草原に波のような影を落としていく。遠くまで伝播していくその風が、いつもより冷たく感じるのは気のせいだろう。
レノックスは想像してみた。二千年前のフィガロが、北の国の雪原を歩いている。見渡す限り日差しが照りつける白銀の世界と、雲一つない蒼い空のコントラスト。振り返ればひたすらに続く自分の足跡と、はるか遠くにちんまりと森と山脈が見える。
音もない。匂いもない。空恐ろしい程の静謐さの中、自分以外の生き物の気配もない。目に染みる光に泣きながら、それでも原因が分からず、ただ先へと歩くしかない。
「どうしてその中を歩いてたんですか?」
レノックスから至極当然の質問が出た。何故歩いていたのかが一向に話題に上がらない。今日も双子の修行の話かと思ったのだが、いつまで経っても他の登場人物が出てこない。
フィガロは少しだけ黙った後、真実おどけた声音で言った。
「うーん。失恋してね」
どうやら本当のことを言うつもりは端からないらしい。羊を見ているレノックスはその表情を見ず、振り返って確認することもない。突っ込んだところではぐらかされるのは分かりきっているからだ。
フィガロがわざとらしく誤魔化しているときは「その話題に触るな」という合図で、冷静に真っ向からそこを指摘しても本人はそのわざとらしさを隠すことなく延々と、そして堂々と誤魔化し続ける。レノックスは一回それをやらかしたことがあり、根負けして以降、追求しないことにしている。
相槌も打たずに黙ったままのレノックスにわずかばかり口角を上げて、フィガロは続けた。
「振られちゃって、二度と彼女がいた村に帰るもんか、いや帰れないってどんどん吹雪の中を進んで」
「……箒で進まなかったんですね」
「箒もない時代だったんだよ。で、何日かしたら急に晴れた。そのとき振り返って思ったのは――」
レノックスにはその時代に箒で飛ぶという魔法すらなかったのか、フィガロが箒で飛ぶという基本的なこともできない子供時代の話をしているのか判別がつかない。けれどなんとなくそのときのフィガロが目に浮かぶ。
視界が開けた瞬間、きっとどれだけ進んできたかを振り返って見るだろう。もし、肉眼でまだ出発地点が確認できる程度だったらどう思うか。フィガロならばこう思うだろう。
「――『がっかりした』」
「正解。それで俺もやる気がなくなっちゃって、いいやと思って投げだした」
この男の性根は二千年前でも四百年前でも今でもさほど変わらないらしい。レノックスにはその投げ出すタイミングのスイッチがよく理解できていなかった。心が離れるきっかけはなんとなく分かるといえば分かるのだが、なぜそう思うのかは未だに理解できていない。
「だけど投げ出す方向がだいぶ自棄でね、ひたすら歩くことにしたんだ。止まらずに」
「歩けたんですか?」
「晴れてから丸二日歩いてたかな。綺麗な地獄だったよ」
すごく朦朧としてたし、と続ける。魔法で冷気を遮れるとはいえ、極寒の雪原の中で丸二日歩き続けることがどれだけ過酷かは当の本人の言葉から想像するしかなかった。
「本当に目の前に何にもないと、勝手に脳みそがぐるぐる動き続けるんだよね。なんで振られちゃったのかなとか、一番美味しかったマーシアの実はどれだったかとか、最後に見た村人と交わした言葉はなんだったかとか、とにかく色々。そう、あの羊みたいに」
あの羊、がどの羊を指すかは一目で分かった。二人の目の先では、一頭の羊が自分の尻尾を追いかけるようにくるくる回っていた。しかし黙って見つめているとすぐに、飽きたかのように草原の上に伏せる。
当時、フィガロは考えることに対して飽きることも止めることもできなかったのだろう。だからこの景色はいい、と語る。適度に散らばる羊と、風に遊ばれて絶え間なく変化する草原が気を狂わせないからだと。
「それで、どうしたんですか」
「正気と体力がどんどん削れていっても、魔力は残っていたから凍傷にはならずに済んでいたし別に二日以上歩けたと思うんだけど」
そこでフィガロははあ、と息を吐きながら空を見上げた。
「目の前に雪のベッドがあるって思ったら寝たくならない?」
「今でもミチルに起こされる先生が言うと重みが違いますね」
反射的にレノックスは言ってしまった。案の定フィガロが露骨に不満げな顔をしてくるので、冗談です、と前置きして続けた。
「その状況で寝たらいくら魔法があったとしても致命的でしょう。夜だったんですか?」
「いや、太陽が真上にあったね。日光の乱反射でくらくらするのにもうんざりして、いい加減もういいかと思って目の前にそのまま倒れた」
二人は羊に目を向けながら話し続ける。
話は佳境に入っているが、それに対して雰囲気は穏やかだった。フィガロはただ昔話をしているだけで、レノックスは話の中で生死の境を彷徨っている男も二千年後には隣に座っているのが分かっていたので。
「それで、どうやってスノウ様とホワイト様に見つけてもらったんですか?」
「こら、結論を急ぐんじゃない」
ちょっと怒ったような口調に反して、ふは、とフィガロが笑う気配がする。やっぱりオチは分かっちゃうかあ、という声に対して、どこにもたどり着かないと考えれば逆算で、と返事をする。
「そう、ちょうどその時上空を通りがかったらしい双子先生に見つけてもらったんだよ」
フィガロが言うには、晴れた雪原で行き倒れた自分はさぞや見つけやすかっただろうとのことだ。
「気付けにブランデーみたいなものを飲ませてくれたんだよね。でも俺気絶する直前でさ、飲ませるんじゃなくて匂いを嗅がせてくれた方が絶対良かった。ものすごいむせたし」
あの双子ならやりかねない、とレノックスは思う。一応敬意は払っているものの、かつての弟子から思い出したように語られる修行の数々は、世の一般的な魔法使いが死屍累々になりそうなものばかりだった。もっと俗っぽく言えばえげつないの一言に尽きる。
意識を飛ばす寸前のフィガロの口に、「まあなんとかなるじゃろ」と躊躇いなくとんでもない度数のブランデーの瓶を突っ込む双子が難なく想像できる。
「……二千年前にもブランデーってあったんですか?」
「そこ?俺も断言できるくらいはっきりとは覚えていないけれど……色々使えるくらいには度数が高い酒だったと思う」
色々、とは怪我の消毒だったり食べ物の殺菌だったりそれこそ気付けだったりするのだろう。確かにレノックスもそういうアルコールには心当たりがあり、一応小屋の棚の中に入っている。
「あれより美味しく感じた酒はないかな。だから俺にとってあれはブランデー」
その味を思い出したのか、フィガロは足を組んでその膝の上で頬杖をつき、上機嫌に話を締めくくった。
「レノ、ブランデー頂戴」
「だめです」
喋りすぎて喉が渇いた、酒じゃなくても珈琲をもらってもいいかとフィガロが尋ねれば隣の男は不承不承の体で重々しく「……どうぞ」と言う。さすがに午後から診療所に行く予定がある癖に酒を飲むつもりはなかったのだが、彼の声音からやらかしかねないと思ったんだろうなあと推測する。冗談を訂正する機会はないので苦く笑って、自分の呪文を一言唱えた。
「《ポッシデオ》」
くるっと手首を回せば右手に握られたマグは二つ。夏の暑い盛りなので、中身はアイスコーヒーである。今頃レノックスの小屋の中の珈琲豆はマグ二杯分減っているだろう。牛乳や羊の乳は単純に小屋にないので入れなかった。
はい、と手渡すと本人は頼んでもないのにありがとうございます、と礼が返ってきた。律儀なことである。
「……レノも何か、面白い話してよ」
フィガロの脳内で賢者が「それ、だる絡みって言うんですよ」と小言を言う。性分なので仕方がない。
対するレノックスは、静かに珈琲を啜りながら羊を見つめていた。一見いつもと変わらないが、僅かに困っている気配がする。それもそのはずで、彼は自他共に話役ではなく聞き役の方が得意だと考えられている。
けれどフィガロはこの寡黙な男から話を引き出すコツを知っていた。彼が苦手なのは「何を言えばいいのか分からない」というときに語る話で、具体的な話題を提示してやれば、端的に話をしてくれることが多い。
さてどう話を振ろうか、と思っているさなか、頭上を一羽の大きな鷲が通り過ぎた。翼をぴんと張ったまま、羽ばたきもせず空を滑るように目の前の広大な山脈へと向かっていく。鷲の影はその後を追うようにして、二人が座るベンチを越えて小さく波を立てる草原の上を駆けていった。
その一連の光景を見て、フィガロは閃いた。
「炭鉱場にカナリアっていた?」
フィガロは炭鉱場で働いていたころのレノックスについて僅かばかりしか知らなかったので、ちょうど良い話題になるだろうと問いかける。
炭鉱場のカナリアは有名な話で、フィガロは何度かそれに言及した文献を読んだことがある。人間よりも遥かに敏感な肺を持つカナリアは、有毒なガスがあればその美しい鳴き声をすぐに止めてしまう。その場所を参考に、炭鉱夫たちは安全な場所を探りながら掘っていくのだ。
「いましたね」
「それについて何か思い出すことはない?」
レノックスは羊から視線を落とし、じっと珈琲の水面を見つめる。まるでそこが記憶を映す鏡であるかのように。三秒ほど沈黙が下りた後、ふっと羊に視線を上げて語り始めた。
「革命軍が蜂起する少し前、俺の炭鉱は急に掘れる深さが深くなったんです。確か、揚水機が新しくなったとかで」
「ああ。ムルの発明品だったね。確かにあの辺で新しい動力の発明に関する論文を発表していたはずだよ」
くるくると手元の珈琲を揺らしながらフィガロが言うと、レノックスはそうなんですかと意外そうな声音で返した。どうやら現場の職人には仕事を増やした機械がわかってもその作った張本人は知る由がなかったらしい。
この揚水機の構造が後の蒸気機関の発明に繋がるというそこそこ大きい歴史の転換点なのだが、視座の違いを感じたフィガロはレノックスに話の続きを促した。
「掘り進めるうち、体調を崩すものが多く出てくるようになりました。それは揚水機が新しくなる前でもそうでしたが、掘れるスピードが早くなったので病人が出るスピードも早くなったんです」
「なるほど。それで登場したのがカナリア?」
「そうです。元々俺は毒ガスから身を守る魔法を皆によく使っていたので、最初はカナリアを使った炭坑の調査はいらないかと思いましたが、上層部からやれと命令されたらしく」
彼が魔法使いであるということは炭鉱場の上層部は知らなかったはずで、作業効率を高める為には必要な工程と判断されたのだろう。そしてその調査をやらされた人物も何となく想像がつく。
「で、レノに調査の白羽の矢が立ったのか」
「はい。毒ガスを浴びても唯一俺だけは生きていられるので」
何ということもないように言うが、実質人柱である。
もし仮に魔法を使って毒ガスを防いだとしても、掘り進めている途中の坑道は崩落の危険もかなりあっただろうし、そうした事故が起きた場合彼は生きて帰れないくらいの魔法使いだ。先生役を勤めるフィガロは分かる。
彼もその危険に気付いていたのだろうに、語る言葉に恨みつらみは欠片も滲ませていなかった。この男の「他者を守る」ということに関して殊更に実直な性質は、四百年前も今も変わらないらしい。
フィガロはそのことに対して、「俺とはかけ離れた世界で生きているんだな」という感想を抱く。実際には僅かにそうなりたかったという羨望と、僅かにそうはなりたくないという幻滅を同時に感じるのだが、上手いことこの感覚を表現することを諦めていた。
そう思考をする自分に若干嫌気が差し、論点を迂回させるように聞く。
「カナリアは可愛かった?」
「そうですね、恐らく」
「具体的に言ってよ」
強張るフィガロに、レノックスは眼鏡の奥の瞳を曇らせた。上手く説明できないのか、と思ったらそうではないらしい。
「陽の光を浴びたカナリアを見た時間が遥かに少ないので……確か、新鮮な檸檬のような色だったと思います」
「なるほどオーエンの嫌いな色だ。というかそんなに長いこと炭坑を調べていたのか、大変だったね」
「道に迷ったんです」
「えっ」
フィガロは思わず隣の男を見上げた。炭坑道で道に迷う。それは雪原の中で行き倒れて眠りそうになるのと同じくらいの致命傷に思えた。
「よく無事だったね」
「待つのが取り柄なので」
そう言って目元を微かに和らげるレノックスは、少し誇らしげに見えた。いつもなら彼を茶化すのだが、確かに立派なことなので軽口を叩きそうになる口を閉じた。
「先生が歩いていたのは丸二日でしたか。俺はどのくらい迷っていたか覚えていません」
「昼も夜も分からなかったから?」
「そうです」
うわあ、と呟きながらフィガロは珈琲を口に含む。辛さは比較できるものではないが、予想外に飛び出した想像を絶する思い出話に目が回りそうだった。
「道中はどんな感じだった?」
「どんな感じ……。夜目を効かせる魔法を使っていたので炭坑の中はぼんやりと薄暗い感じでした。鳥籠から聞こえるカナリアの鳴き声が常に響いていたので、眠くはなりませんでしたね」
目の前の草原の明るさがワントーン落ちたように感じたので頭上を見上げると、そこそこ大きい平たい雲が太陽を隠していた。
フィガロは彼の少ない言葉から、想像してみた。小さい頃のレノックスが、ぼんやりと薄暗い炭鉱道を一人歩いている。同じ風景が長く続き狭いため、平衡感覚が狂って道が隆起していると同時に陥没しているようにも感じるだろう。息が詰まるような圧迫感も襲ってくるはずだ。
手には鳥籠があり、その中でカナリアが常にピィ、ピューイと美しい声で鳴き続ける。この小鳥が鳴くのをやめたら、それはすなわち危険な場所に足を踏み入れていることになる。
「――カナリアを殺そうとはしなかった?」
「どうしてですか」
「俺だったら気が狂っちゃうよそんなの」
まるきり意味が分からない、という顔をされたのだが、こちらもさっぱり意味が分からない。常に甲高く鳴き続ける小鳥と暗くて狭くて道がわからない坑道の相性は最悪のはずで、精神をじわじわ侵してくるだろう。フィガロは自分がもし同じ状況で道に迷ったのなら三時間も持たずにその小鳥を殺すだろうなと予想する。
魔法で防げる毒ガスの発生地点が分からなくなったとしても、そのことは正気を失うよりかはましなので。
レノックスはちらりと隣を一瞥した後、珈琲を啜りながら改めて羊に目を向けた。その動作はため息を想起させる。
「カナリアが鳴き続ける道が出口に繋がっていると思えば殺せませんでした」
「いや、きみはただの役割のない鳥でも殺さないね」
「……そうかもしれませんね」
レノックスはあっさりと認めた。
フィガロにも一応道徳的には殺さないと言ってそう行動するべきなのは分かっているのだが、頭で分かってても実際にやるとなると途方もない距離があるので、やれそうもない。
ただの雑談で彼我の距離がどんどん開いていくのを危惧して、フィガロはまた論点をずらし、話を進めた。
「それでどうやって助かったのさ。まさかそのままずっと立ち止まっていたわけじゃないだろう?」
「壁に手を当てて歩き回ったら出口に着くでしょう」
「本当にやったの?」
「はい」
フィガロは遠い目をした。額縁越しに見ているように、目の前の羊が散らばる牧歌的な景色が遠くに感じる。
レノックスが試した方法は簡単に言うと炭鉱内をぐるっと二周する方法である。そうすれば絶対に出口には到着する。魔法使いは確かに食事の必要がないので、やろうと思えばやれる。しかし常人の精神力では途中で心が折れるのがオチだ。
元々の彼の天賦の才か、それとも子供だからという純真さがあったからできたのか。恐らくどっちもだろうなと推測してフィガロはマグを口に運ぶ。
「レノはさ」
「はい」
「本当にすごいよ……」
「……ありがとうございます?」
「それで、出口に到着してからカナリアは見なかったの?」
「出口に着いたとたんに眠って倒れてしまって。目が覚めて父親に尋ねたら、上層部に回収されてしまったと」
彼は凪いだ瞳を揺らさなかった。
子供時代のレノックスの心中を思う。この男はどうにも守る対象が自分の手を離れていく運命にあるらしい。何と声を掛けようか迷っているところで、彼が先に口を開いた。
「食べられたのかもしれませんね」
「……カナリアが?上層部に?」
「そうです」
フィガロは思わずぽかりと口を開けた。彼もカナリアがその後炭鉱場でその職務を果たして飼い殺されたのは分かるだろうに、何故そんなことを言うのかが一瞬分からなかった。その様子を見て微かに笑ったレノックスでようやく合点がいった。冗談を言ったのだ。
「分かりにくい」
「すみません」
ともするとはは、という笑い声が漏れる寸前だったのだろう、彼は誤魔化すように珈琲を口に含む。その瞬間、辺りにざあっとさざめきを立てて強い風が吹いた。
「でも、俺は気にしてはいないんです」
風音に紛れそうな小さな声で呟く。
何を、とは言わない。
そんなレノックスをいじらしく感じたフィガロは、隣と距離を詰める。彼は体温が高いので、完全にくっつかなくても多少近ければその温かさが感じられる。
自分とレノックスはかけ離れた存在である。それは生きてきた年月であったり性根だったり、様々な部分でそう感じさせる。それでも彼の高潔な魂を尊重したい時、フィガロはこの体温の側に寄り添うようにしている。彼の体温は、どんなに目に見えない溝が大きかったとしても、その近さを言葉を越えてはっきりと伝えてくれる。
自分たちは、南の魔法使いの家族の一員であると。寄り添ってもいいのだと。
「……どうしたんですか」
「風が冷たいだろう?」
レノックスは、真夏に戯言を吐くフィガロが、ひどく遠回りに自分を労わったことを理解した。肩口にほんの少し、フィガロの体温のぬくさを感じる。慰めの言葉でも気晴らしの言葉でもなく、あまりにも慎ましやかなその行動は、とてつもなく遠くて完全には理解できない他者に対する労いとして真摯なものであると感じられるのが不思議だった。
ここで何かを言われたとしても、言葉が上滑りするのはレノックス自身も分かっている。
「――そうかもしれませんね」
レノックスは戯言を受け取った。
その後二人はいつものようにとりとめのない話を続け、太陽を覆っていた平たい雲が散ったところで解散した。
誰もいなくなった高原にあるベンチは、再び来客が訪れるのを待っている。
Fin.