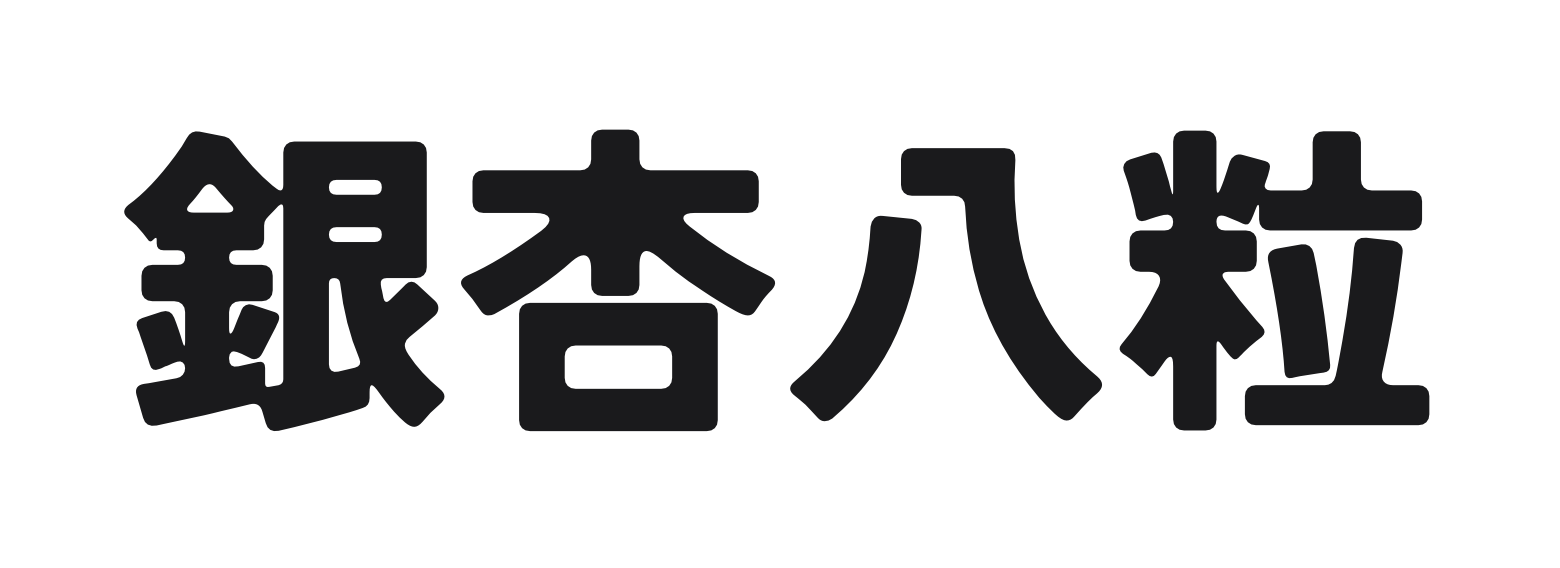「兄様のばか――――っ!」
ミチルは声の限り叫んだ。ぽかんとするルチルを置いて、部屋を飛び出す。
玄関の扉を勢いよく開けてからは、とうとう本気で駆け出した。完全に不意打ちだったので、兄はまだ追ってこない。どこに行くかは決めてなかったが、このままあの家にいたくなかった。
家出とひとくちに言っても、さまざま種類がある。二度と家に帰らない家出、何日かは家族の顔も見たくない家出、そして半日別のところにいれば冷静になれるくらいの家出。
今日のケンカは「半日くらい相手とは別のところにいきたい」くらいの些細なケンカだった――途中までは。
兄弟の心得
ミチルとルチルがお互いの顔も見たくないくらいに怒り心頭のとき、それぞれが行くところは限られている。友だちの家、丘の向こうのフィガロの診療所、そして少しばかり遠いレノックスの小屋。南の国は田舎だった。
今回ミチルが向かったのはレノックスの小屋である。追ってくる兄の裏をかきたくて、多少疲れても行くと決めた。きっとルチルは近所に聞き込みをして、目撃情報がなければフィガロの診療所に向かうだろう。
長いマフラーをしたあの子と箒で飛んで以来、一人で箒に乗れるようになったミチルは「自由も知らなくちゃな」の一言を思い出しながら飛んでいた。これは自由なんかじゃなくてひどく消極的で意味のない行動だとは頭でわかっている。わかっているが飛び出さずにはいられなかった。
レノックスの小屋の戸を叩くと、驚いた顔をした小屋の主人がミチルを迎えた。当たり前だ。塩辛い涙がミチルの目を赤くしていた。
「どうかしたのか」
「……兄様とケンカしました」
レノックスの表情は変わらないが、雰囲気がかすかに緩む。たぶんほっとしている。「ミチルがルチルに怒って、逆に言い負かされてミチルが泣く」ケンカはいつものことだ。そう思っているがはっきりと表には出さない相手の優しさがいまはちょっと憎い。憎いと思ってしまう自分が嫌だった。
しょっぱい涙が溢れてくるので、目を抑えなければならなかった。眼球が染みる。レノックスの手が背に回る。一定のリズムで叩かれると、声は出すものかと決意していても、嗚咽を零さずにいられなかった。
いったん落ち着いたあと、ミチルは小屋の中で羊のミルクを啜っていた。ミチルの好きなマグで、人肌程度に暖められたミルクである。
羊のミルクはとても甘くてとびきり濃厚だった。牛乳みたいに一気飲みができない。そういう意味では、レノックスが淹れるホットミルクは、どんなホットミルクよりも気持ちを落ち着かせる飲み物だった。
机の向かいに座るレノックスは、自分の分のホットミルクを飲みながら何も聞いてこなかった。そしてミチルも、何も言わなかった。
結局のところ、今回も「ミチルがルチルに怒って、逆に言い負かされてミチルが泣く」ケンカだったのであえて詳細を言う必要はなかった。「なんとか言ってやってくださいよ」とせがんでも彼を困らせるだけだとミチルはもう知っている。
だから、この問いかけも独り言に近かった。
「兄様はボクが言うことはどうでもいいんでしょうか」
ルチルに言葉が響いていないような気がする。受け流される。ぞんざいに扱われる。これは言い過ぎかもしれないが、少しばかりそんな気がする。注意をしても言い返すのはそういうことではないのか。それがたまらなく悔しくて腹が立つ。
「そんなことはない、と思う」
意外にも返事はすぐ返ってきた。断定しないんですね、と喉元まで出かかった言葉をホットミルクと一緒に飲み込んだ。レノックスはルチルではない。
「多分、言い返すのは兄としてのプライドとか、案外そういう何かが原因だと思う。言葉を雑に取るというのは、そう見えるだけだ」
「兄様に兄としてのプライドがあるんですか?あれだけだらしないのに?」
そこでレノックスは身体を揺らして笑った。
「プライドというと確かにルチルらしくないな。誇りと言ってもちょっと違うか……でもまあ、兄というものはそういうものだな」
「……レノさん弟だったんですか?」
「一般論だ」
ときどき忘れてしまうが、レノックスはミチルの知らない四百年を生きている。南の国のお年寄りと気安げに話すくらいだから、恐らくミチルが想像するよりずっとたくさんの兄弟姉妹を見てきている。
ミチルとルチルはそのうちの一組だ。二人とも魔法使いなのが珍しいだけで。だからこそ、レノックスの言葉はすんなりとそうかもしれないと思える言葉だった。
「プライドがあるのかは俺よりもルチル本人に聞いたほうがいい。きっと何か、プライドとか誇りとかそうじゃない言葉で説明してくれるはずだ」
ルチルに対する感情が顔なんて見たくない、から、ちょっと聞いてみたい、に変わった。ミチルの小言に言い返してくることは釈然としないけれど。
そういうと、レノックスは頷いた。
「もうそろそろ日が落ちる。今日中に帰るか」
「……はい。レノさん、ありがとうございました」
恐らく、ここで帰らないと言えば街に連絡を入れて泊めてくれるのだろう。そのやさしさに頭を下げると、そのまま頭を撫でられた。
そうしてレノックスに手を振りながら小屋を発った。
だが、気分が落ち込んでいるときには容赦なく悪いことが起こるというのは相場が決まっているらしい。
二十分もすれば、雨が降ってきた。
ミチルは箒を使いながら同時に雨よけの魔法を使うことができない。舗装されていない開拓途中の道をぽつねんと歩くことと、ずぶぬれになりながら自分の家の玄関の扉を叩くのはどっちがみじめかを想像して、ミチルは徒歩で帰ることを選択した。
雲の街の雨の音と、開拓の進んでいない道の雨の音は違う。
街で聞く雨は屋根やレンガに当たってばたばたとうるさくて賑やかなことに対して、自然の中で聞く雨はただひたすらにさ――、という細い音が続く。ミチルは今までどちらの音も好きだと思っていたが、一人きりで聞くこの細い音はより一層ひとりぼっちだと感じさせることを知った。
レノックスの言葉ですこし上向いていた心がまた沈む。魔法で雨や泥が跳ねないとはいえ、荒野のなかを歩いていくことは神経を使う。石につまずかないように気をつけることはもちろん、平坦ではない道を進むことはそもそも疲れる。
「ミチル!」
そんなとき、兄の声が頭上から響いた。ゆっくりと顔を上げる。ルチルは箒にまたがってミチルの側に降りてくるところだった。兄は魔法を同時に二つ以上使える。だから雨にも濡れていない。
「ごめんなさい」
ルチルは地面に降り立つと、ミチルの目を真っすぐに見つめた。
「これからはしっかりするように気をつける。私、かっとなって言いすぎた。ミチルと、ちゃんと話がしたい」
ルチルの瞳はどこまでも真摯で冷静だった。
そんな兄と対峙して、ミチルはわかったことがある。
自分はこんなにも心をめちゃくちゃにして相手のことを考えてしょうがないのに、対するルチルはけろっとして冷静なように見えるのがいらいらするのだ。
飛び出したり怒り出すのはいつも自分なのがなによりの証拠に思えた。兄は心配してくれている。それはわかる。でも、それを超えて不公平だと感じざるを得ない。
雨足が強くなる。
大切にされていないなんて、口が裂けても言うつもりはない。
ないから、このぐちゃぐちゃで絡みきった気持ちを説明することができない。それは話し合おうという兄に対して申し訳なくて、兄よりも冷静じゃない自分が悔しくて、そのうえ涙はもう乾いてしまって、ただ黙ることしかできない。その事実がひたすらに胸を締め付ける。
伝えたかった。伝えられないことが、兄が大事にしていることも傷つけるような気がした。
「兄様」
「うん」
「……」
不甲斐ない自分は言葉を見つけることが出来なかった。地面に答えなんかが書いてあるわけはないのに、俯かずにはいられない。
すると頭上から、よし、という声が降ってきた。
「フィガロ先生から聞いたんだけど、雨は気分を下げちゃうんだって。だから――雨のむこうに行こう!」
「え、わ、っ、兄様⁉」
ミチルの声が思わずひっくり返った。膝裏をすくうように、箒に乗せられたのだ。バランスを崩して思わず掴んだ柄の先の地面はもうすでにミチルが走っているくらいのスピードで流れている。ルチルがはっきりした声で指示する。
「しっかり跨って!」
言われずとも跨らないと落っこちるので、拒否権はなかった。慌てて二人乗りの体制をとると、後ろから抱え込むように、ミチルの掴んだ先の柄をルチルは掴んだ。
体制が整うと、一気に加速する。何もないだだっ広い荒野とはいえ、流石に危ないと言おうとしたがそのまえに「喋らないでね、さん、に、」と何かのカウントダウンが始まったので、ミチルは黙るしかない。
いち、と兄が呟いた瞬間、箒が上を向いた。
あれだけすさまじい速さで流れていた地上の風景が時間を止めたかのようにぴたりと止まると同時に、なにもかもがミチルから離れて小さくちっぽけになっていく。視界の端に、つみ木みたいな雲の街が見えた。それでもルチルの箒は止まらない。重力を切り裂いて、南の空を駆け上がっていく。
急上昇に胃が縮みあがる感じがする。しばらくすると慣れてきて、不快感がだんだん消えていくかわりに、不安感が湧き上がってくる。このままどこまで行ってしまうのだろう。
すぐ目の前まで、灰色の分厚い雲が迫ってきていた。
フィガロもレノックスも、箒で飛ぶときには雲に入らないようにと注意する。平衡感覚がなくなり、下手をすると視界が晴れない中で気が付かないうちに山や木や地面にぶつかる危険があるからだ。
まさか雲に入るつもりじゃないだろうなとミチルの血の気がさあっと引く。
「これもフィガロ先生から教わったんだけど」
風防に守られたかのようにミチルの顔に風は当たらないが、風切り音がごうごうと鳴る。そんななか、兄の声は切れ切れにミチルに届く。
「もし万が一雲の中に入ったら、絶対に箒を上以外に向けちゃいけないって」
雲の中に入った。
一気に辺りが暗くなる。手をのばせば、すぐそこは闇だ。ルチルの箒の先端からさきは、灰色の絵具をぶちまけたかのようになにも見えない。
身体が持ち上がるような感覚以外に、上に向いているという確かなしるべはない。心細く感じるのと比例して、背中にあたる兄の体温があたたかく感じた。
それに冷静さを取り戻す。あまりに全てが唐突だったので、いまのいままで突っ込みができなかったが、それでもミチルは大きな声を張り上げた。
「兄様、本当に反省してますか⁉」
「してる、してる!」
うそだ!と反射的に思った刹那、視界が開ける。あまりの眩しさに目を細める。
そこには焼けつくような色をした空があった。
南の国が誇る三千メートルは下らない霊峰の稜線から、どろりと溶けきったバターの塊みたいな夕陽が覗いている。列をなして飛んでいる漆黒の粒は、渡り鳥の群れだろう。いままさに抜けてきた雲の絨毯は、羊の群れみたいなかたちをして、黄金色に輝いていた。
雨のむこうは、何よりもきれいな夕焼けだった。
その空の色を見ていると、ミチルは胸がすく心地がする。まるで地上に靄とか黒々した想いをぜんぶ置いていったかのように、想いがずっとはっきりとした。あれだけぐちゃぐちゃしていたのに、残ったものはとてもシンプルな答え。
言葉が上手く出てこなかったのは、腹が立ってしょうがなかったのと同時に、兄のことが大好きだったからだ。
ルチルは優しくて、おおらかで、みんなから慕われて、自分のことを育ててくれた大事な家族。だからこそ、あんなに本気で悩み、苦しみ、辛くなってしまった。根っこの部分だけを見れば、ずっと楽に考えられたのだ。地上で考えるよりも、ずっと素直になれた。
しばらく目の前の夕焼けを見つめて、それから振り返ってルチルを見た。
「……ごめんなさい、勝手に飛び出して。それから、ここに連れてきてくれてありがとうございます」
「高いところがミチルは好きでしょう?気分転換になっていればよかった。それで、さっき言いかけたことは?」
言いかけたことは、もう消えてしまっていた。ミチルはそのかわりに、レノックスに言われたことを思い出した。
「……レノさんに聞いたんです。どうしてボクの言葉に言い返してくるんでしょうかって。そしたら、兄のプライドみたいなものがあるんじゃないかって。それ、本当ですか?」
「レノさん……」
ルチルはちょっぴり複雑そうな顔をしてから、ふっと視線を目の前の夕陽に向けて、呟いた。
「《オルトニク・セトマオージェ》」私は母様の子。そして、ミチルの為なら何でもします。
ルチルの指先に、幻影の真っ白な小鳥が一羽とまった。腕を軽く振ると、その小鳥は夕陽を目指して真っすぐに、薄紅色に染まりながら飛んでいく。
それ以上の言葉は、必要なかった。ルチルはどこまでも、自分の兄だった。
遠く離れて消えゆく小鳥を見つめるミチルの目に、水の膜が張る。それはもう、しょっぱくはなかった。
Fin.