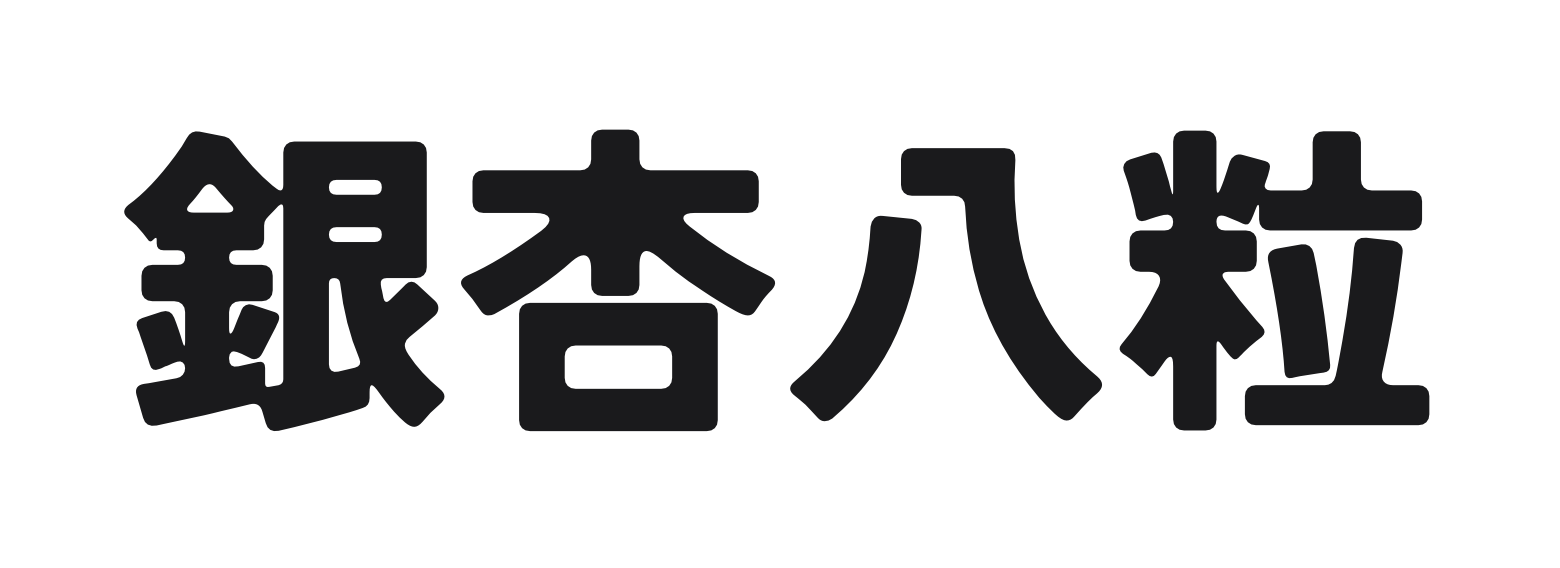「ああ、レノックスはカルパッチョ苦手でしたよね?無理しなくていいですよ」
何気なく言った賢者の言葉で、魔法舎に静かな雷が落ちた。珍しくオズの雷ではなかった。
かくしごとにもならない
厄災の出現も古代の魔法の発動も魔法生物の討伐も特にこれといった任務もない、麗らかな午後。そういう日は、賢者が料理の練習をしていることが多い。この世界の料理は色が奇抜でちょっと気が引けますねと言っていた割に、賢者は早々に順応して今では手料理を振る舞うようになっていた。
最初はカルパッチョ、オムレツといった初歩の初歩から初めて、今では豪華なフルコースまで作れるようになっているというから驚きである。それでも「経験値を貯めたいんですよね」と言って簡単なものをコツコツ作っていることが多い。
リケの大好物であるオムレツは材料が少なく一番作りやすいので一番作るのかと思いきや、意外とそうではない。ネロのオムレツも食べたいのだろうなと察した賢者が頻度を控えているのだ。
そうすると必然的に二番目に作るのが簡単なカルパッチョに練習台のお鉢が回ってくる。
賢者は何故か魔法舎の魔法使いの食べたいものがなんとなく分かるという特殊能力があるらしく、練習として作った料理を食べたいと思っている人物に渡す。
フィガロはカルパッチョならいつでも食べたい気分なので、結果よく食べることになる。賢者がよく自分の大好物のカルパッチョを持って訪ねてくるので、「気があるの?」と軽口を叩いたら、ドミノ倒しのようなこの話を聞かされ思わず真顔になった。
「やっぱりこうも頻度が高いと……迷惑ですよね……」とフィガロの真顔を見て若干正気に戻った賢者への返答は「いや、嬉しいよ」であった。パッと思いついた返事の中で一番いい人らしかったので。
じっくり考えても、別に負担になるということはなかった。元々ネロのおやつは気分によって食べたり食べなかったりだったので(有難いことにネロはその辺りを承知して寛容だった)、その空いた隙間に大好物のカルパッチョを入れるというだけの話になる。
今日もその流れだったのだ。
キッチンでフライパンを振るって自分の好物を作る賢者を見かけて、「それもらっていい?」「食べたいのなら是非」といういつもの会話を交わし。特に用事もなかったのでなんとなくそのまま賢者が作っている様子を観察しているところで、レノックスがやってきた。
羊の散歩を終えて帰ってきたのだろう彼はきっと腹を空かせている。そう推測して、「レノも何か食べに来たの?賢者様に振る舞ってもらったら?」と声をかけた。
そこで出たのが冒頭の「ああ、レノックスはカルパッチョ苦手でしたよね?無理しなくていいですよ」だったのだ。
レノックスの苦手とするものが自分の好きな料理だと、フィガロはこの一言で初めて知った。
では書類仕事があるので、と自分の部屋に帰る賢者に労いの声を掛け、フィガロとレノックスは食堂に二人座ることになった。元々変な時間だったので、珍しく食堂は貸し切り状態である。
フィガロの大好物を作っているのでレノックスの大好物も作りますよと、賢者はさっとラクレットを作った。そのため二人の前にはそれぞれの大好物が置かれている。賢者の特殊能力で、オーブン料理でも驚きの早さで仕上がってしまうのだ。もはや賢者は魔法使いじゃないかと疑いたくなるが、魔法舎の料理道具と賢者がそろって初めてこのシステムは発動するらしい。
閑話休題。
とはいえ、まあ、うすうす察してはいたのだ。「もしかしたら相手は自分の大好物が苦手かもしれない」ということに。
ネロとカナリアは食事当番として非常に優秀なので、誰かの大好物を作った日には同時に別の料理も出してくれる。まず全員が好きな食べ物がないので、どちらか好きな方を選んで食べろということだ。一種のバイキング形式だが、残ったものは次の日の昼食に回されたりするので廃棄は少ない。
南の魔法使いで卓を囲むことはもちろん頻繁にあるので、自分の好物が出た日に好物ではない方の料理を取ったんだなと思うことは多々あった。
「レノ、カルパッチョ苦手だったんだね」
「……はい。先生もラクレット、苦手ですか」
「ああ。嫌いだよ」
長年世間話を交わしながらも、これが初めて自分の苦手な料理を互いにはっきりと主張した時だった。
ちなみにお互いに対してはこんな調子だが、二人ともフローレス兄弟の味の嗜好は完璧に把握している。例えばフィガロは、ルチルが子供の頃にカルパッチョを嫌がった様子がレノックスの眼鏡に対する反応とほとんどそっくりで笑ってしまったことを、昨日のことのように思い出せる。
兄弟と比較すると、二人同士の相互理解はおざなりにされがちだった。
「どうして言わなかったんですか」
「言う必要なくない?相手の好物にわざわざ」
「まあ、そうですね」
「レノは?」
「俺も似たようなものです。フィガロ様の味覚に文句をつけるのは恐れ多くて」
「……冗談?」
「冗談です」
互いに自分の大好物をつつきながら喋る。「これ相手の苦手なものなんだな」と思いながら食べる料理は若干の気まずさがある。二人ともこの雰囲気を回避しようと無意識に黙っていたところがあった。特段隠していたわけでもない。言い出すタイミングがなかっただけだ。
しかし、とレノックスはフィガロの冗談の数々を思い出しながら首をひねった。今までの言動を鑑みるに、彼はこういうことに嬉々として茶々を入れてきそうなものである。「俺食べる気しないんだよねそれ、レノはよく食べられるね」とか、ありきたりなそんな切り口で。
出鱈目を言ってレノックスの肌に不思議な紋様を描かせて村に向かわせるのはセーフなのに、レノックスの味覚についてとやかく言って気まずくなるのはアウトなのか。フィガロはときどき妙なこだわりを見せる。レノックスにはその匙加減がよくわからなかった。
魚の切り身を三枚同時にフォークに乗せてぱくりと食べた気分屋の彼は、ふと思い出したかのように言った。
「何日か前に一緒にカルパッチョ食べたよね、あれは大丈夫だったの?」
「まあ……先生が五分の四は食べたでしょう。あれくらいなら食べれます」
晩酌をして、肴にカルパッチョがあるとごっそり持っていくのはいつもフィガロである。苦手なものであるし代わりに他のものをよこすので、レノックスは特に文句を言ったことはない。
へえ、とフィガロは零す。
「苦手でも食べるんだ、偉いね」
「先生は食べられないんですか?」
「食べたくないなら食べなくてよくない?別に生死に関わりはないし、そもそも食事自体しなくていいし」
少しばかり大魔法使いの高慢な顔を覗かせてフィガロが言う。レノックスが思い返してみても、確かに彼は自分の前でラクレットを食べているのを一度たりとも見たことがない気がした。ラクレットを肴にすることも、作るのが面倒であまりなかった。
彼の立ち回りが上手いのだろうと結論付けたところで、そういえばと思ったレノックスは、タイミングを見計らって疑問を口にした。
「俺がラクレットを食べた後のキスはどうしてたんですか?」
――ごふっ、と水を飲んでいたフィガロがお手本みたいなむせ方をした。レノックスは咳き込む彼のまえに黙ってピッチャーをサーブする。いつも彼のよく回る口にいいようにやられている、ちょっとした仕返しであった。
でもまあ、とレノックスは思う。多分三倍返しくらいになって返ってくるだろう。
果たしてその予想は正しかった。水を再び飲んで復活したフィガロは、一息をついて、いつものにやにやとした笑みを浮かべながら立て板に水の勢いで喋った。
「それは俺の方が気になるなあ、レノ。俺はいつも賢者様にカルパッチョを作ってもらっていて結構な頻度で食べていたんだもの。何日か前の晩酌だってそうだったじゃないか。もしかしてそういうときにおまえ、俺のキスは不味いなあなんて思って俺とキスしてたの?ひどいじゃない」
「いや、そういうわけでは……」
フィガロはたいへん大人気なかったので、レノックスが否定せざるを得ない問いかけで自身への質問をぶった切った。双子の師匠がいたら、「フィガロちゃん、こらっ」とはたかれるレベルの蛮行である。
しかし悲しいかな、食堂にはフィガロを諫めることのできる二千歳越えの魔法使いはいなかったので、レノックスはこの質問に答えるしかなかった。
「別に何の感慨もありませんでしたが。何日か前も、どちらかと言うと先生はワインをよく飲んでいたでしょう」
「それでも残り香みたく味は残っていただろう?」
「そうだったかもしれませんが」
レノックスはそれ以上何も言えない。思えば不思議なことだったが、フィガロに残るカルパッチョの名残に対して、苦手だとか逆に好きだとか何とも思ったことがなかったからだ。しかしフィガロは納得していないようで、にやにやとした笑いを崩さない。
こんなに深追いすると、彼が答える番になったときにあらかたの逃げ道が消えているので、面倒なことになるのはフィガロである。このことを理解しているのか、分かっていてなお知りたいのか。
これは何か言わないと止まらないのだろうな、と思ったレノックスの脳裏に、的確に表すとある一言が閃いた。冷やかしをさっさと切り上げたい一心で、思いついた言葉をそのまま口にする。
「不味いとかではなく、ただ『先生の味だな』と」
その一言で、フィガロはちょっと驚いたような顔をして黙った。そのまま何も言わないのをいいことに、レノックスはラクレットを食べる手を進めることにした。
じゃがいもとベーコン、エバーチーズを均一に切り分けるレノックスの丁寧な食べ方を見ながら、フィガロの頭には強烈な衝撃が駆け抜けていた。
「俺の味」。いま俺、相当なことを言われたのでは。そしてなんでおまえは素面でそんな台詞を言えるんだ。
フィガロの脳は優秀だったので、その答えのヒントとなる過去のある一件を思い出すことに成功した。おしゃべりなローズ――食べると愛を伝えたくなるというふざけた食材――を使ったローズクレープをしれっとした顔で「上品な味で、俺これ結構好きです」と言って食べていたのは誰か。
そういえば、レノックスだった。
シャイロックが好きだと言っていたのは納得した。ラスティカやムルといった他の西の魔法使い辺りが好きだと言ってもおかしくはない。カインだったとしても納得しただろう。しかし、その面子を差し置いて好きだと言ったのはレノックスだったのだ。
直接的には何も関係がない話だったが、もはやこの話を思い出した時点でフィガロは敗北した気分だった。何かに。そしてからかう方向がとんだ藪蛇だったことを悟った。
負け戦なのをフィガロが悟ったとて、当然レノックスは先ほどの質問を聞き返すことになる。自分の発言がどれほどフィガロに衝撃を与えているのかを知ってか知らずか、顔をあげて「先生はどうなんですか」と問いかけた。
「……俺この雰囲気の中言わなきゃならないの?」
「この雰囲気にしたのは先生ですが?」
「……《ポッシデオ》」
無自覚らしい彼を黙らせたかったが、その口を黙らせるために魔法を使ったわけではなかった。
レノックスが口の中に異変を感じたように片手で口をおさえる。異変を起こしたのはフィガロなので、何の疑問もない。
今頃レノックスの口の中は、味の消えたジャガイモとベーコン、そしていつも通りの味がするラクレットチーズという奇妙な味を感じ取っているだろう。
味がしない食べ物の不気味さは知るところであるので、五秒くらいで解いてやる。レノックスは片手をおさえたまま不服だったという目をしてくるので、そんな彼に「百聞は一見に如かずだよね」といつものように軽口を叩く。こういうとき自分は力のある魔法使いで良かったとも思う。言葉にしなくて済むので。
嚥下し終わった彼が水を飲み、口火を切った。
「毎回味を消していたんですか?わざわざ呪文を言って」
「……自分に向けてだったら呪文なしでもできるよ。双子先生なんて無詠唱で身体を変えられるくらいだから、こういうのはよくやらされたんだ。あと、味を消してたんじゃなくて、」
そこで言葉を切った。
言葉にしたくなかったので体験してもらったのだが、正確に伝わらなかったらしい。それを理解したとき、フィガロは何か意味のない奇声を発したい気分になった。これ以上はレノックスではないので素面では言えないが、こう「味覚を切ったままキスをしていた」なんて勘違いしたまま会話を切り上げるのもあまりよろしくない。
一つ自分用に残しておいた逃げ道も潰されてしまった。
板挟みになった結果、フィガロは視線をだいぶゆっくりした動きで明後日の方向に向かせる。結局、自らの口でレノックスの表現に引きずられた正解を言うことになった。
「ラクレットの味だけ消してた。……おまえの味は残したまま」
フィガロのほのかに赤くなった耳を見ながら、レノックスは目の前の男がだいぶ滅茶苦茶な魔法を使っていたことを知った。そのまま「滅茶苦茶じゃないですか」と言うと、「もったいないだろ」と投げやりになったような調子でよくわからない返事が返ってくる。
フィガロはなおも、そっぽを向いたままだった。レノックスはラクレットの最後の一口を頬張りながらその様子を見ていると、なんというか、まあ、という心地になる。
「俺たち、思ったより仲が良かったんですね」
お互いの嗜好とまわりくどくやってきたそれは、黙っていただけで隠し事というほどのことではなかった。間違っても気遣いとは程遠い、相手に伝える面倒くささと横着の産物。それでもそれが露わになったいま、レノックスはこれを「思ったより仲が良かった」と表現するほかなかった。
レノうるさいちょっとだまって、という追い詰められた者が決まって言う罵りが返ってくるのを聞き流しながら、皿を片付けるために立ち上がり、台所へ向かう。
もちろん、その途中でフィガロに口付けを落としたのは、言うまでもない。
Fin.